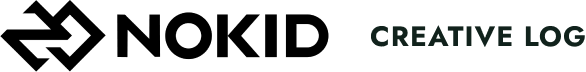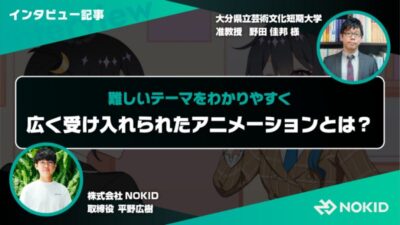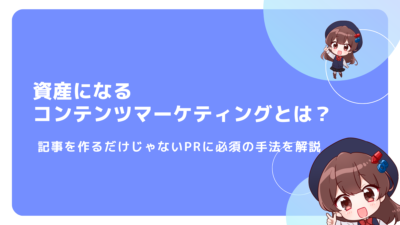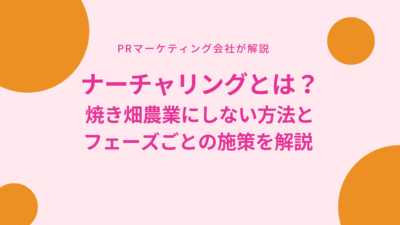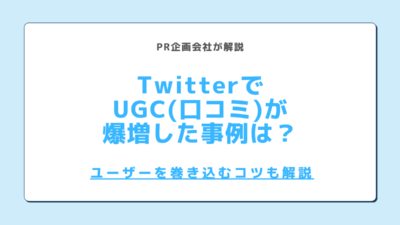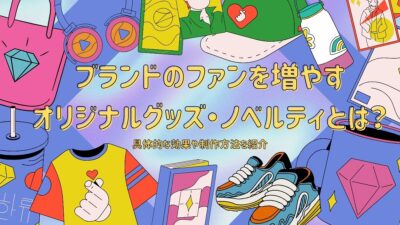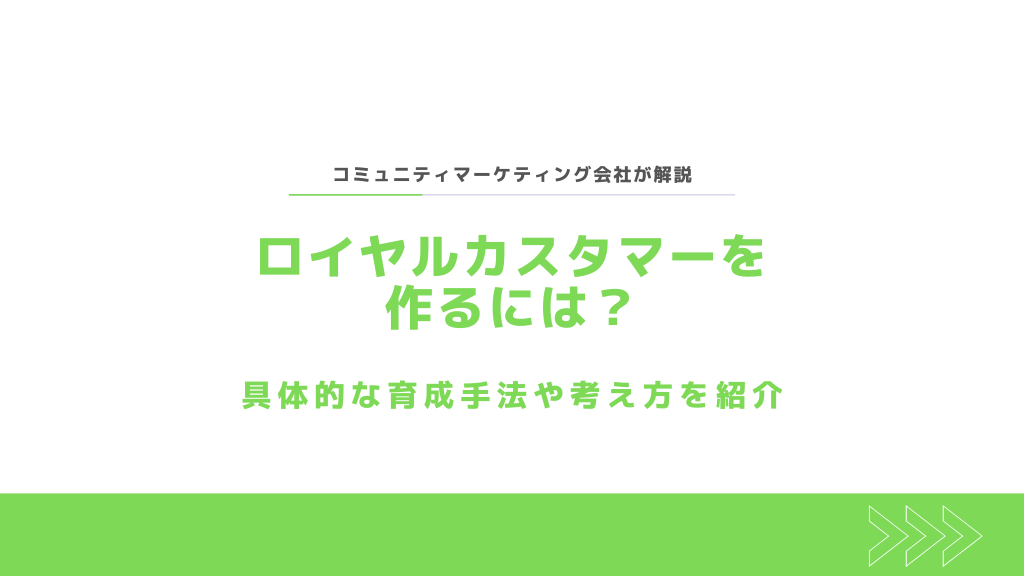
ブランドやプロダクトを持つ上で、ロイヤルカスタマーの存在は欠かせません。ロイヤルカスタマーとは、企業の製品やサービスに対して通常の顧客よりも、信頼と愛着を持つ顧客のことを指します。これは、収益にも大きく影響しており、売上の大半をもたらすと言われています。
ですが、使ってくれる金額の多さ=ロイヤルカスタマーというわけではありません。なぜなら、すべての高額な取引のある顧客が製品やサービスに強い愛着を持っているわけではないからです。
ロイヤルカスタマーの存在は、収益に限らず、ブランドの良さを周囲にアピールしてくれるなど、PRの観点でも重要になります。そのため、企業が拡大していくためには、通常の顧客からロイヤルカスタマー=ファンへ育成していくコミュニケーションを常に練っていく必要があります。
そして、ロイヤルカスタマーのメリットには、ビジネスが撤退するリスクを減少させられることが挙げられます。
このように、ロイヤルカスタマーの育成は、企業の成功に不可欠な要素となっているのです。
そこで今回は、ロイヤルカスタマーをどのように育成していくのか?について、具体的な事例もご紹介していきます。
「見込み客から"選ばれる"PR動画の作り方ガイドブック」では、視聴者にとって興味のない動画は簡単に無視される時代に「"興味を持ってもらいやすい"動画の条件」や「なぜアニメーション動画が興味を持たれやすいのか?」を公開しています。広告効果の悪化が益々懸念される今後の"新たな一手"を考えておきたい場合にご活用ください。 他のテーマも「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ入手してみてください。
ロイヤルカスタマーとは
ロイヤルカスタマーとは、企業が提供する商品・サービスやその企業自体に信頼・愛着を持っている顧客のことを指します。
企業の抱える顧客のうちの2割がロイヤルカスタマーであり、自社売上の8割を占めるといわれています(パレートの法則)。
ロイヤルカスタマーは他社の商品やサービスへの乗り換えを行わず、継続的に自社製品・サービスを利用してくれたり、「もっと他の人にもこの商品やサービスを利用してほしい」と考え、自発的に周りの人に商品・サービスを勧める、口コミで良い評価を付けてくれるという特徴があり、企業の売上・利益の向上に非常に重要な存在です。
似たような言葉に優良顧客という言葉がありますが、ロイヤルカスタマーと優良顧客の意味は完全には一致していません。
優良顧客は契約金額の高い顧客や継続して利用している期間が長い顧客の事を指します。
しかし、全ての優良顧客が必ずしも商品・サービスへの愛着が高いわけではありません。
解約の手続きが面倒だったり、他社の商品・サービスにそこまでいいものがない場合など、様々な理由から仕方なく利用している可能性があります。
このような優良顧客たちは、「契約更新の年をきっかけに解約する」「より良い商品・サービスを見つけたら移行する」といったような行動が考えられます。
これらの事から、企業が利益を向上させるためには自社の商品・サービスに愛着を持たない優良顧客よりも、ロイヤルカスタマーに重点的なアプローチができるような施策を考えていく事が重要となります。
ここからはロイヤルカスタマーには具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのかご紹介していきます。
ロイヤルカスタマーのメリット
事業存続リスクの低減
仮に商品・サービスに愛着のない優良顧客が顧客割合を多く占めていた場合、競合他社が新サービスを提供して乗り換えキャンペーンなども実施していると、大量に顧客が離れていってしまいます。
そこまで多くの売上を占めていた愛着のない優良顧客たちが自社にもたらしていた利益がなくなり事業を存続できなくなってしまいます。
一方、ロイヤルカスタマーは商品・サービスへの愛着が高いため、他社への乗り換えが少なく、継続契約率が高くなります。
加えてLTV(顧客生涯価値)も向上し、安定的な売上の確保と事業の存続に繋がっていきます。
このようにロイヤルカスタマーは事業存続リスクの低減が期待できます。
コスト低減
マーケティング用語に「1:5の法則」というものがあります。
これは、「新規顧客獲得にかかるコストは既存顧客の維持にかかるコストの5倍かかる」という法則で、新規顧客は獲得にかかるコストが高いにも関わらず利益率が低いので、新規顧客の獲得以上に既存顧客の維持が重要であるという考え方です。
新規顧客獲得の際には人々に商品・サービスを認知し、魅力を感じてもらうために広告費など様々なコストが必要となりますが、ロイヤルカスタマーは既に商品・サービスに魅力を感じてくれているので、前述したコストを低くすることができ、結果的に利益率が向上していきます。
さらに、抑えたコストをマーケティング費や開発費など、新サービスの拡充のための資金を捻出できるため、事業の更なる成長も期待できます。
新規顧客の獲得の効率化
「1:5の法則」では新規顧客獲得よりも既存顧客の維持が重要であると言われていますが、もちろん新規顧客の獲得も重要です。
当たり前のことですが、商品・サービスの選定にあたり、選定ミスは利用者・利用企業に大きな影響をもたらすため、実際に商品・サービスを利用した人の評価は非常に有用です。
ロイヤルカスタマーは自社製品・サービスについてのポジティブな口コミの書き込みや周りの人への推奨といったような事を自発的に行ってくれるので、効率的に新規顧客の獲得が期待できます。
商品やサービスの質の向上
ロイヤルカスタマーは自社の商品・サービス、企業自体に愛着を持ってくれているからこそ、積極的に有用なフィードバックをしてくれます。
そのフィードバックを元に改善を行う事で自社の商品・サービスの品質を向上させ、更なる売り上げに繋げることができます。
ロイヤルカスタマーのデメリット
追加コストや負担
ロイヤルカスタマー限定の特典やサービスを提供する場合、追加コストや負担が伴う場合があります。
例えば高価な特典や割引を提供する際には、企業の利益が減少してしまいます。
また、ロイヤルカスタマー向けのサービスの維持には追加の人材やリソースが必要になることも考えられます。
ロイヤルカスタマーが満足し、かつコストを抑えるような施策を事前に考えることが重要となります。
他の顧客の不満
ロイヤルカスタマーに対する優遇が多い場合、ロイヤルカスタマーではない他の顧客が不公平感を感じ、潜在的にロイヤルカスタマーになる可能性のある顧客を失ってしまいます。
ロイヤルカスタマーとそれ以外の顧客に対するアプローチの配分のバランスを考えていく事が重要です。
ロイヤルカスタマーを生み出すステップ
ロイヤルカスタマーを生み出すいは顧客のロイヤルティを高める事が非常に重要です。ここからは、顧客のロイヤルティを高め、ロイヤルカスタマーを生み出すためのステップをご紹介していきます。
- ロイヤルカスタマーを設定する
- 顧客接点(タッチポイント)を計画する
- 顧客を分析して改善する
順に見ていきましょう。
ロイヤルカスタマーを設定する
企業の扱っている商品やサービスごとにロイヤルカスタマーの具体的な定義は異なります。
そこでまず、「自社の扱っている商品やサービスのロイヤルカスタマーとはどういう顧客なのか」を全社員が分かるように明確に設定します。
例として、「1カ月に1回購入する顧客」といったような設定が考えられます。
このように明確に設定するとロイヤルカスタマーを生み出すための一貫した戦略を実現することが可能となります。
顧客接点(タッチポイント)を計画する
自社におけるロイヤルカスタマーを設定できたら、次にタッチポイントを増やすための計画を行います。
顧客の購買行動を正確に可視化できるカスタマージャーニーマップ等を利用し、「顧客の関心ポイント」「顧客の離反ポイント」などを探ることで、どのようなタッチポイントが必要かを考え、増やしていきましょう。
顧客を分析して改善する
次に顧客分析を行います。
自社で設定したロイヤルカスタマーに合致する顧客がどの程度存在するのか、どのようなアクションを取る傾向があるのか、使う金額はどのぐらいなのか、など様々な観点から分析し、現状を把握します。
その後、定期的にこうした顧客分析およびロイヤルカスタマーの定義の見直しを行い、施策が収益向上につながっているのかを確認していきましょう。
そこで改善点があれば適宜改善していくことが必要となります。
ロイヤルカスタマーに顧客を育成する具体的な手法
前述した通り、顧客のロイヤルティを高める事がロイヤルカスタマー創出にあたり必要不可欠です。
ここからは、顧客ロイヤルティを高める具体的な手法をいくつかご紹介していきます。
CRM(顧客関係管理)
CRMは顧客管理手法として多く使われる手法で、購買データから年齢、性別、居住地区、嗜好などで分類を行い、分類に対応するアプローチを行っていきます。
ITシステムを利用して顧客データの分析が簡単にできるようになっており、顧客情報を一元管理することで企業内での情報共有が可能です。
ロイヤルカスタマーに分類された相手にだけ有益な情報のダイレクトメールを送るといったような方法があります。
このように接触機会を増やしていくことで、信頼が生まれていきます。
CEM(顧客経験管理)
CEMはロイヤルカスタマーの創出を目的として、顧客が商品・サービスを購入するプロセスや利用シーンを想定しながら価値ある体験や経験を付加する手法です。
商品やサービスの特性だけでは消費者の欲求を満たすことが難しいため、更なる魅力を付け加える事で愛着を持ってもらうことを前提にしています。
CEMは顧客データでは読み取れない部分も重視しており、顧客がサービスを利用する上でどう感じたのかといったような「顧客の感情」に焦点を当てています。CRMだけでは創出が難しい人がロイヤルカスタマーになる手法で、非常に効果的です。
one to one
one to oneとは顧客一人一人の購買傾向からニーズを読み取り、個々人に対してそれぞれのアプローチを行っていく販促活動の事です。
具体的にはレコメンデーション、LPO(ランディングページ最適化)、リターゲティングなど、個々のニーズに合わせたアプローチを行っていきます。
one to oneは顧客の離脱を防ぐことにもつながっていく手法です。
アンバサダープログラム
アンバサダープログラムとは、自社の商品・サービスのファンをアンバサダーとして起用し、代わりに自社商品の宣伝を行ってもらう手法のことです。
具体的には、商品・サービスに熱心なアンバサダーを募集し、SNSや口コミサイトで定期的に推奨を行ってもらう仕組みで、インフルエンサーとは起用目的が異なります。
インフルエンサーが、商品の認知拡大を目的としており、広く浅いイメージとなります。一方で、アンバサダーは、認知拡大よりも強力な口コミという意味が強くなります。そのため、商品を認知しており検討する前後の層に理解を促して購入を後押しするイメージです。
自社商品の専属広報担当というのがアンバサダーと考えると分かりやすいかもしれません。
アンバサダー達によって、新規客に熱い口コミが伝わるだけでなく、既存顧客への刺激となって活性化にも繋がるため、既存顧客がファン=ロイヤルカスタマーとなる可能性が高まります。
これらの顧客の状態を把握し、1人1人に合った対応を、実際のファンによる協力も得ながら育成していくことが、自社に夢中になってくれるようにしていくということです。
ロイヤルカスタマーを育成する企業の戦略例
ここからは実際にロイヤルカスタマー創出に成功した企業の戦略事例をご紹介していきます。
スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックスコーヒージャパン株式会社は、2017年にロイヤルティプログラム「スターバックスリワード」を開始しました。この企画は、店舗と顧客のつながりを強化し、LTVを向上させることが目的となります。
スターバックスリワードはアプリを活用したパーソナライズドマーケティング施策で、「Star」と表現されるポイントが54円(税込み)につき1つ集まり、ためる事で様々な特典「スターリワード」に換えることができます。

Green Starを集めるGreen会員からスタートし、1年以内にGreen Starを250集めるとGold Starを集められるGold会員となります。Gold Starは150Starsごとに、店舗でドリンク、フード、コーヒー豆など好きな商品1品と交換できます。
スターバックスリワードの会員数が増え、データが貯まってきたタイミングで「どういう嗜好のお客様がどういう情報に反応するか」ということを、たくさんの人に利用されているかという「ビジネス軸」、お客様が喜んでいるかという「お客様軸」、店舗のパートナー「従業員」に受け入れられているかという「パートナー軸」で検証し、それぞれの嗜好にあった情報の提供を行いました。
結果として会員数が750万人まで増えています。(2021年5月末時点)
顧客の個々の感情に焦点を当てたことがここまで会員数が伸びた理由の一つです。ロイヤルティプログラムは社内評価が難しいですが、長期的に考えると会社の売上向上に非常に有効であるといえるでしょう。
ロイヤルカスタマーについてのまとめ
ここまでのポイントをまとめてみます。
- ロイヤルカスタマーはビジネスの成功の鍵となる
- 顧客の信頼を勝ち取ることがロイヤルカスタマー化には必須となる
- 顧客のニーズを深く理解して常にサービス改善を続けることが大切
- 高品質なサービスや商品を提供することは前提となる
- 顧客のフィードバックを活用し改善することで期待に応え続ける
- ロイヤルカスタマーを特別扱いすることで離れられなくする
- 顧客の期待を超えるサービスを提供する
- 気まぐれではなく継続的な関係構築を心がける
- 顧客満足度を常にチェックできる繋がりを築く
- ロイヤルカスタマーの育成は絶えず工夫が必要となる
ロイヤルカスタマーの育成は、単なるビジネスの成功だけでなく、ブランドと顧客との深い絆を築く鍵となります。これらのポイントを心に留め、日々の業務に取り組むことで、顧客との信頼関係をより強固にし、持続的な成功を手に入れることができるでしょう。
顧客に誠実に対応し、様々な視点からロイヤルカスタマー創出を目指すことが成功の秘訣です。
アニメーション動画のおすすめ記事
基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説
アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説
アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説
事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説
種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説
制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説
制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介
依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説
制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介
MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説
実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法
企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由
制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?
採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説
動画制作の基礎についての記事
・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説
・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説
・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。
・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介
・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介
・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介
・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介
・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介
・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介
・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介
動画制作の依頼方法についての記事
・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?
・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介
・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました
・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説
・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説
・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介
・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説
・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説
動画の作り方についての記事
・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介
・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説
・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介
・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説
・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう
・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介
・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介
・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介
・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説
・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介
ショート動画についての記事
・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介
・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意
・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介
・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介
・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!
・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説
・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介
・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!
・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介
・企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説
・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?
・アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説
・アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法
・【種類別】アニメーション動画制作の料金が知りたい!種類別の制作料金と活用例を解説
・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!
・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう
・知名度もない状態でYoutube登録者数を増やすには。1万人登録アカウントを量産した運用者が解説。
・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説
・動画を営業ツールとして活用するには?メリットと作り方を動画制作会社が解説
<コミュニティ作りに関する記事>
・Discordがコミュニティ作りに活用される理由とは?熱狂的なファンが勝手にできる仕組みを解説
・NFTホルダー限定コミュニティの作り方とは?おすすめ管理ツールや事例を紹介
・ファンマーケティングとは?顧客を呼び寄せる口コミ戦略を紹介
<イベント企画に関する記事>
・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?
・【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説
・PR目的のイベントを成功させるには?企画のコツや開催するメリットを解説
・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介
・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介
・セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介
<制作・運用代行会社に関する記事>
・YouTube運用代行会社はどこへ依頼すべき?外注できる内容や費用相場を紹介
・【保存版】ショートアニメの制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介
・Youtube運用代行会社でお願いするときに抑えておきたい3つのこと
・Youtubeの運用コンサル会社は何をしてくれるの?依頼するメリットもご紹介
・アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介
・YouTubeチャンネルと広告の運用代行を選ぶ前に知るべきポイントとは?
・インターネット広告代理店に依頼して成果を出すには?任せるべき部分や選ぶ基準を紹介
・SNSアカウントの運用代理店をどう選べば良い?外注のメリットや依頼時の注意点を解説
・IPビジネスを代理店に依頼するメリットとは?活用するコツや費用感も紹介
・失敗しないイベント企画会社の選び方とは?依頼メリットや注意点まで紹介