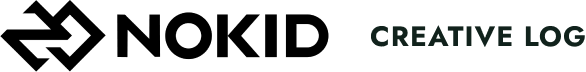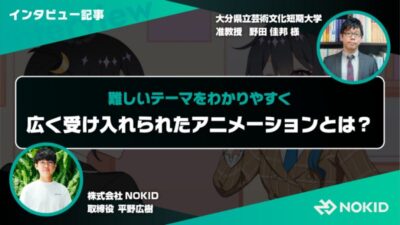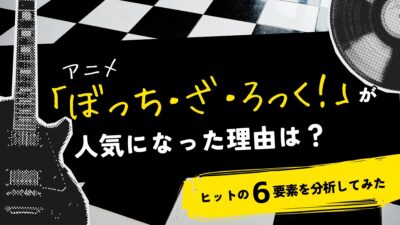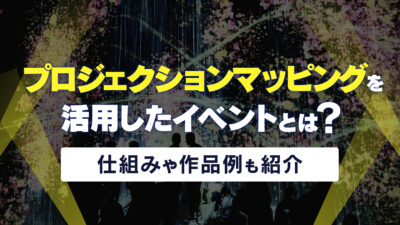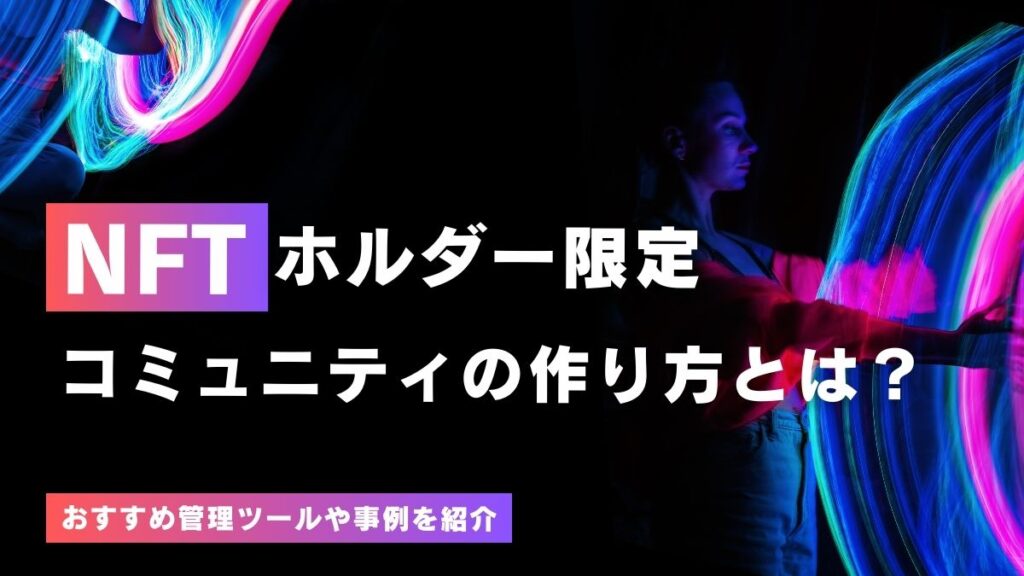
これまでは“販売する商品”としてのNFTに注目が集まっていましたが、現在では、NFTを中心とした“コミュニティ作り”という点に注目が集まっています。コミュニティといえば、「オンラインサロン」が一般に浸透してきている中で、NFTという技術を使ったデジタルアートと、それに集まる人たちがWeb上で会するオープンな場となっており、日本でもすでに多くの人が参加しています。
顧客との関係を深めてブランドを強化する手段として、コミュニティに注目している企業は多く存在しますが、NFTなどの新しい仕組みを取り入れている企業はまだ多くはありません。新たなビジネスチャンスとしてNFTも活用することで、顧客に特別感を演出できれば強固な関係構築に役立つはずです。
ユーザーがNFTという希少なデジタルデータを保有する喜びだけでなく、専用のコミュニティにも参加できる権利を付与したり、他のユーザーと差別化することで優越感に浸ってもらえる点が特徴ですが、新たなコミュニティビジネスの形としてこれからも注目度が上がっていくと考えています。
しかし、NFTを活用したCRM戦略の具体的な方法や、NFTコミュニティを通じて顧客エンゲージメントを高めるためのノウハウは世の中に出回っておらず、確立もされていないため探すのが大変です。
そこで今回は、NFTという出回る数量を限定できる仕組みを使って、コミュニティの帰属意識を高めたり、ユーザー間のエンゲージメントを高める方法を紹介します。実際にコミュニティ運営で活用した経験も考慮して、各事例から読み取れる考察やポイントもお伝えしていきます。
コミュニティをどのように運営するかは「Discordがコミュニティ作りに活用される理由とは?熱狂的なファンが勝手にできる仕組みを解説」がおすすめです。
「見込み客から"選ばれる"PR動画の作り方ガイドブック」では、視聴者にとって興味のない動画は簡単に無視される時代に「"興味を持ってもらいやすい"動画の条件」や「なぜアニメーション動画が興味を持たれやすいのか?」を公開しています。広告効果の悪化が益々懸念される今後の"新たな一手"を考えておきたい場合にご活用ください。 他のテーマも「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ入手してみてください。
NFTホルダー限定コミュニティとは
「NFTホルダー限定コミュニティ」とは、売買可能で非代替性の“NFT”を所有する人々だけが参加できるコミュニティです。該当NFTを保有する人だけが入れるオンラインサロンともいえますが、NFTを所有する人々が特別なアクセスや情報を共有することができる場所として機能します。
この種のコミュニティは、NFTアート、ゲーム、コレクターアイテム、仮想不動産など、様々な分野で見られます。
例えば、ある特定のNFTアートを所有する人々が参加するコミュニティでは、そのアート作品に関するディスカッションや、次の施策に関する意見交流などが行われます。
前述したように、似たサービスに“オンラインサロン”がありますが、参加方法やコミュニティの構造から大きく異なります。
オンラインサロンとNFTコミュニティの違い
まず、オンラインサロンの参加には、入会費や月額費用がかかることが一般的です。オンラインサロンの運営者は参加者からお金をもらうため、「運営者」対「参加者」という構図ができあがりますし、退会しようとすると一定のルールに沿って退会手続きが必要です。
一方、NFTコミュニティでは参加するためにお金を払う必要はありません。
もちろんコミュニティを創設した人達はいますが、誰もがフラットに興味関心のある事についてチャットしたり、プロジェクトに参画したりすることができます。いつでも参加できて、そしていつでも距離を置くことができるのもNFTコミュニティの特徴といえます。
NFTについて
そもそもNFTとは、Non Fungible Token(ノンファンジブルトークン)の略で、簡単に言えば「世界に一つだけのデジタル資産」のことです。ファンジブルが代替可能という意味なので、ノンファンジブルは「代替不可能」、つまりそれぞれが固有で唯一無二の存在ということです。
NFTが注目を集める理由は、デジタルアセットを“所有”することができる点です。
従来、デジタルアセットは容易にコピーされ、オリジナルとの差異が認識できないため、その所有権を証明することができませんでした。
しかし、NFTはブロックチェーン上にデータを保持することで、デジタルアセットの所有権を確認できるようになりました。
NFTは、デジタルアートや音楽、ゲームのアイテムなど、様々なデジタルアセットに適用されます。NFTを発行するためには、ブロックチェーン上でトークンを作成する必要があります。このトークンは、デジタルアセットと一対一で対応しており、ブロックチェーン上に記録された情報に基づいて、オーナーシップを確認することができます。
NFTが話題になっている最大の理由は、前述した通り所有権が明確になることです。これにより、保有だけでなく自分の所有物として他人に売買することが可能になりました。
この二次流通が可能になった点を踏まえ、NFTを保有する人たちで形成されたコミュニティが「NFT保有者限定のコミュニティ」です。
参考:OpenSea
NFTホルダー限定コミュニティのメリット
運営参加権
NFTホルダー限定のコミュニティは、運営者との距離感が異なるのが大きな特徴です。
運営者と参加者ではなく、参加者が運営に携われるのが一番のメリットともいえます。
後ほど事例をご紹介しますが、運営からの特典を受けることだけではなく、自分達で創出した価値を還元することが可能です。
限定アイテムへのアクセス
コミュニティに参加することで、そのNFT保有者にのみ提供される限定アイテムにアクセスすることができます。
例えば、NFTアーティストが保有者限定のデジタルアート作品を作成した場合、そのNFTを保有する人々にのみ提供されることがあります。
特別なアクセス権限が得られる
NFT保有者限定のコミュニティに参加することで、そのNFTに関する特別なアクセス権限や情報にアクセスすることができます。
例えば、NFTアート作品を所有している人は、そのアーティストの制作過程や、限定アート作品の入手方法など、一般の人々よりも詳細な情報を入手することができます。
コミュニティ内での交流
NFT保有者限定のコミュニティは、共通の興味を持つ人々が集まる場所です。
そのため、参加者同士で交流することができ、新しい友人やビジネスパートナーを見つけることもできます。
NFTホルダー限定コミュニティのデメリット
参加資格が制限される
NFT保有者限定のコミュニティに参加するためには、ある特定のNFTを所有している必要があります。
そのため、そのNFTを所有していない人は参加できないため、コミュニティへの参加資格が制限されることがあります。
情報の秘密性
NFT保有者限定のコミュニティは、限定的な人数のみが参加するため、そこで共有される情報やアイテムが秘密に保たれることがあります。
そのため、コミュニティに参加しない人々には、情報が不足する場合があります。
逆に情報が漏洩する可能性もあり、限定であることの価値が薄くなってしまう事例もあります。
コミュニティ内での競合
NFT保有者限定のコミュニティには、同じNFTを所有する人々が参加しているため、コミュニティ内で競合することがあります。
例えば、NFTアート作品を所有している人々が、そのアーティストから限定アート作品を入手するために競合することがあります。
NFTコミュニティの面白い事例
次に、ユニークなNFTコミュニティの事例を二つご紹介します。
デジタル村民
新潟県長岡市にある山古志地域(旧山古志村)は、2004年の新潟中越地震以降、急激に人口が減少しました。
その結果、約2,200人いた地域住民は約800人になり、高齢化率が55%を超えるなど、地域は存続の危機に。
そんな中で2021年12月から取り組まれたのが、山古志村が発祥である「錦鯉」をシンボルにしたNFTアート「Colored Carp」の発行です。
このNFTは、同地域の「電子住民票」の意味合いも兼ねたものです。
定住人口にとらわれずにグローバルな「デジタル関係人口」を生み出し、NFTの販売益をベースに独自の財源とガバナンスを構築することで、持続可能な「山古志」を誕生させることが狙いだといいます。
現在は、リアルな人口を超える900人以上もの「デジタル村民」が世界中に誕生しており、Discord上のコミュニティでは、地域を存続させるためのアイデアや事業プランについて議論が行われているそうです。
また2022年2月には、デジタル村民から具体的なアクションプランを募り、投票によって実行する施策を決定する「山古志デジタル村民総選挙」が実施され、「Colored Carp」第一弾セールの売上の一部を活動予算とする形で、当選した4つのプランを実行中です。
参照:デジタル田園都市国家構想
盆栽を学ぶ
NFTを活用してコミュニティを形成し、国内の盆栽市場の課題に向き合いながらその魅力を海外に届けるプロジェクト、「BONSAI NFT CLUB」。
盆栽業界では、すでに国内外で市場があるものの、盆栽農家の高齢化に伴って海外輸出に積極的に取り組めないという課題が存在しています。
そこで、NFTホルダーでコミュニティを形成し、参加者がそれぞれ盆栽を育成、海外へ輸出するという試みを行っているのがこのプロジェクトです。
具体的には、まずBONSAI NFT CLUBのNFTを購入すると、自宅に本物の盆栽が届きます。そして、育成方法が共有されるDiscordのコミュニティに参加し、ホルダーが盆栽について学びながら育成するという仕組みです。
このBONSAI NFT CLUBが配布している盆栽は、すでに2000本以上の海外用盆栽の育成を経験されている、愛媛県の農業法人、赤石の泉さんにご協力いただいているとのこと。
現在、NFTは段階的に販売されており、初月に販売されたNFTによってコミュニティが形成され、次回の販売時には、コミュニティメンバーがNFTの展開をともに企画したり、新たなプロジェクトに販売益を投資したりといったことが行われるといいます。
参照:NFTを買うと本物の盆栽が送られてくる「BONSAI NFT CLUB」が、第二弾となる8031体のNFTプロジェクト「BONSAI NFT FARM」を10月18日にリリース
NFTコミュニティの運営に活用できるDiscordについて
NFT保有者限定のコミュニティを作る場合によく使用されるのがDiscordと呼ばれるチャットサービスです。まずはこのDiscordについて説明します。
Discordは、アメリカで誕生したボイスチャットサービスです。
音声とテキストの両方によるユーザー間でのコミュニケーションが可能で、1対1だけでなく大人数でのやりとりにも対応しています。
主にオンラインゲームのプレイヤーが使用するサービスとしてアメリカを中心に人気を集めており、日本でもユーザー数が増加し話題を集めていますが、チャットサービスとしてのクオリティの高さや使いやすさなどから、ゲーマーだけでなく、NFTコミュニティを作成する際の主要なツールとして使用されるようになりました。
参照:Discord
Discordがコミュニティ運営に人気の理由
招待制の「サーバー」でコミュニケーションが取れる
Discordでは「サーバー」という単位を用いて他のユーザーとコミュニケーションを取ることができます。
他のユーザーが作ったサーバーに招待してもらったり、自分で作ったサーバーにユーザーを招いたりして使用します。
このサーバーに、NFTを保有する人を招待したり、NFTに興味を持つ人が参加することが可能です。
1対1、少人数、多人数などさまざまな形でサーバーを作ることができる上に、NFT関連のやり取りから、趣味の繋がり、コミュニティ運営に関する業務連絡など幅広い用途で使用されています。
音声とテキストの両方でやりとりが可能
Discordは、音声を用いた「ボイスチャット」と文字を用いた「テキストチャット」の2種類に対応しています。
テキストチャットでは、チャンネルごとに名前を決めることで特定のテーマに関して書き込める掲示板のような使い方が可能です。
ボイスチャットでは音声通話だけでなくビデオ通話にも対応しており、同時通話人数は無制限で行えます。
シンプルで使いやすい操作性
デザインがシンプルで使いやすい操作性もDiscordの魅力の1つです。
少ないタップ数で目的の操作ができるようなデザインになっているので、ゲームをプレイしながらでも緻密な連携が取れるようになっています。
余計な広告表示もなく、視覚的にもストレスが少ないというのもユーザー数が多い理由と言えるでしょう。
メンバーの管理が楽にできる
Discordでは、作成したサーバー内のメンバー管理が楽なことでも知られています。
コミュニティ運営の業務連絡を各セクションに分けて行うような際でも、コミュニティごとに色分けをするなど視覚的にわかりやすくすることもできます。
NFTだけでなく、eスポーツ大会の運営にもDiscordが使われている理由としては、こういった使いやすさも挙げられるでしょう。
関連記事:Discordがコミュニティ作りに活用される理由とは?熱狂的なファンが勝手にできる仕組みを解説
NFTホルダー限定コミュニティについてのまとめ
NFTを活用したコミュニティづくりに関して説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?
単純に売買を行うための商品ではなく、コミュニティ作りのためのNFTという立ち位置が、これからのファンビジネスの主流となる日も近いと言われています。
コミュニティ内で恩恵を受けるファンが、自ら運営にも携わり更にプロジェクトを拡大していく。
今までのコミュニティビジネスとは、視点が異なるコミュニティビジネスといえるでしょう。
自社サービスのファン拡大のミッションを背負っている方は、ぜひNFT保有者限定のコミュニティ作りに挑戦してみてください。
アニメーション動画のおすすめ記事
基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説
アニメ化:原作をどうやってアニメ化する?2つの方法とヒットのコツを成功事例も交えて解説
アニメのPR:海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説
事例解説:【PR動画事例】企業のPRアニメーション動画を制作会社が解説
種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説
制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説
制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介
依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説
制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介
MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説
実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法
企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由
制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?
採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説
動画制作の基礎についての記事
・映像制作に活用されるCGとは?種類や制作会社を選ぶコツまで解説
・Unreal Engine(アンリアルエンジン)は映像制作に向かない?機能の特徴や企業が使うメリットを解説
・アニメーションMVとはなに?尺の短いアニメ作品が急増している理由とは。
・会社・事業説明(案内)の動画とは?採用向けとPR向けをそれぞれ紹介
・おしゃれで芸術性の高いアートアニメーションとは?ブランディング向けな理由や事例を紹介
・HIPHOPのラップ/R&BのMV制作にはリリックビデオ?人気の理由を紹介
・ゲーム実況配信(動画)は売上に影響する?無視できない効果やメリットを紹介
・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介
・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介
・実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介
動画制作の依頼方法についての記事
・アニメーションMVの依頼方法を解説!トラブルなくMVを納品してもらうには?
・動画制作をフリーランスに依頼する際の相場は?発注先の選び方と注意点も紹介
・アニメーション動画を外注依頼する前にすべきことを一覧にまとめました
・アニメーション制作に困っている方へ。独学・外注どちらが良いのかを解説
・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説
・クラウドワークスでアニメーション制作を依頼するリスクとは?制作会社との違いを紹介
・【まとめ版】動画制作をスムーズに依頼するための専門用語を解説
・アニメーション動画制作は外注せず内製化すべき?メリット・デメリットを解説
動画の作り方についての記事
・採用動画を制作しても応募は来ない?内容の考え方や制作事例まで紹介
・動画広告を上手く作りたい!制作ディレクション方法と発注のコツを解説
・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介
・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説
・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう
・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介
・YouTube・イベントのオープニング動画(映像)の作り方は?おしゃれ・かっこいい事例も紹介
・イベント(展示会)を成功させる動画の活用方法とは?目的別に制作のコツを紹介
・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説
・動画制作のための絵コンテとは?目的・書き方のポイントを紹介
ショート動画についての記事
・縦型ショート動画「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介
・ショートアニメ制作のプロセス完全解剖!視聴者の心をつかむ企画・制作・外注の極意
・【保存版】ショートアニメ動画の制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介
・TikTok・YouTubeで「バズる」「伸びやすい」人気ジャンルは?目的別の選び方まで紹介
・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!
・TikTokのショートアニメ動画はどうやって作るべき?種類から収入源まで解説
・【今さら聞けない!】Instagramリールとは?活用するべき理由とテクニックを紹介
・Facebookでも「リール動画」が利用可能に!短尺動画で収益化も!
・YouTubeショート動画の再生数が伸びない原因は2つ?対策すべき指標も紹介
・企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説
・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?
・アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説
・アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法
・【種類別】アニメーション動画制作の料金が知りたい!種類別の制作料金と活用例を解説
・【TikTokアニメ】”バズる”アニメーションの特徴とは?大人気アカウントを一挙ご紹介!
・YouTube漫画動画の作り方を制作会社が解説!何が最も大変なのかを知っておこう
・知名度もない状態でYoutube登録者数を増やすには。1万人登録アカウントを量産した運用者が解説。
・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説
・動画を営業ツールとして活用するには?メリットと作り方を動画制作会社が解説
<コミュニティ作りに関する記事>
・Discordがコミュニティ作りに活用される理由とは?熱狂的なファンが勝手にできる仕組みを解説
・ファンマーケティングとは?顧客を呼び寄せる口コミ戦略を紹介
・顧客のファン化とは?ブランドにとっての効果や手法まで紹介
<イベント企画に関する記事>
・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?
・【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説
・PR目的のイベントを成功させるには?企画のコツや開催するメリットを解説
・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介
・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介
・セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介
・失敗しないイベント企画会社の選び方とは?依頼メリットや注意点まで紹介
<制作・運用代行会社に関する記事>
・YouTube運用代行会社はどこへ依頼すべき?外注できる内容や費用相場を紹介
・【保存版】ショートアニメの制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介
・Youtube運用代行会社でお願いするときに抑えておきたい3つのこと
・Youtubeの運用コンサル会社は何をしてくれるの?依頼するメリットもご紹介
・アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介
・YouTubeチャンネルと広告の運用代行を選ぶ前に知るべきポイントとは?
・インターネット広告代理店に依頼して成果を出すには?任せるべき部分や選ぶ基準を紹介
・SNSアカウントの運用代理店をどう選べば良い?外注のメリットや依頼時の注意点を解説
・IPビジネスを代理店に依頼するメリットとは?活用するコツや費用感も紹介
・失敗しないイベント企画会社の選び方とは?依頼メリットや注意点まで紹介