NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。


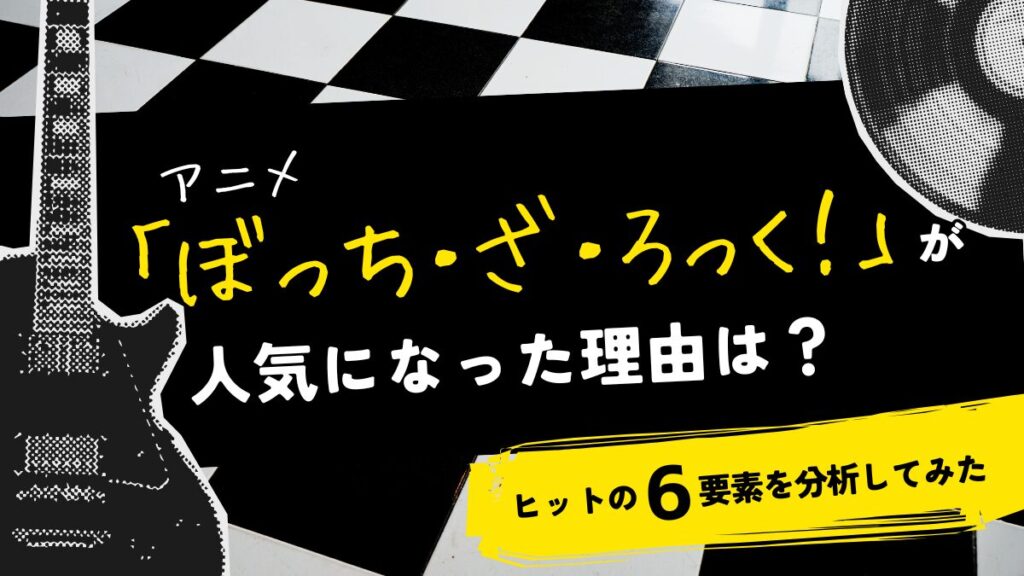
2022年秋クールに放送されたアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」は、当初の想定を大きく上回る反響を生み出し、社会現象とも言える成功を収めました。SNSでは放送のたびに話題を呼び、放送終了後も楽曲のチャート上位ランクインや、原作コミックの販売増加や関連商品の販売へ影響を与えるなど、長期的な熱狂が続いています。
この作品のヒットの要因は、単に原作の人気やトレンドに乗った偶然ではありません。視聴者の「共感」と「共有欲」を意識したSNS拡散設計、作品そのものが持つ構造的魅力、そして段階的に行われた情報開示が三位一体で機能した結果といえます。
特に注目すべきは、キャラクター心理の解像度が高いことと、原作の4コマ形式という断片的な構造を、アニメならではの演出で“物語”として再構築した点です。これにより、原作ファンからの信頼も獲得しつつ、新規視聴者の心も掴みました。
そこで今回は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」がヒットした秘密を深掘りし、今後のアニメ企画や宣伝施策に応用できるヒントを抽出します。なぜこの作品が“語られ、拡がり、記憶された”のか...その構造を知れば、次のヒットが見えてくるはずです。
「ぼっち・ざ・ろっく!」は、一部の人だけが知っている原作からスタートしたにも関わらず、アニメ化によって一躍“社会現象”となりました。その裏には、作品としての魅力を引き出すための緻密な設計が隠れています。
ここからは、作品自体に内在したヒットの要素を紐解き、なぜこれほどまでに多くの視聴者の共感と熱狂を集めたのかを詳しく解説していきます。
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」は、はまじあき氏による「まんがタイムきららMAX」連載の4コマ漫画が原作で、極度の人見知りで陰キャな少女・後藤ひとり(通称:ぼっちちゃん)が、ひょんなことからバンド「結束バンド」に加入し、メンバーとの交流を通じて成長していく物語です。
放送開始当初は、同時期に話題作が多かったことや大々的な宣伝を控えられていたこともあり注目されづらい状況でした。しかし、放送回を重ねるごとにSNS上で大きな盛り上がりを見せました。
例えば、放送後にリリースされた劇中バンド「結束バンド」名義でリリースされたアルバムは、オリコン「上半期ランキング 2023 作品別売上数部門」女性グループ初の「上半期デジタルアルバム」1位や、「2023年上半期 Billboard JAPAN ダウンロード・アルバム・チャート“Download Albums”」で1位を獲得する快挙を成し遂げています。
さらに、帝国データバンクの調査した「「楽器店市場」 動向調査2023」によれば、2022年には作中に登場したギターなどの楽器の売上が前年度を上回り、同作に影響を受けたライト層への販売が増加しています。
このように、アニメのヒットにはファン作りだけでなく、社会に大きく貢献する力を秘めているのです。
参考:【ビルボード 2023年上半期Download Albums】結束バンド「結束バンド」が通算21回のトップ10入りで首位に back number「ユーモア」が続く - billboard JAPAN
参考:「ぼっち・ざ・ろっく!」の結束バンド、女性グループ初の「上半期デジタルアルバム」1位「本当にすごいことが起きておりまして」【オリコン上半期】 - ORICON
「原作を忠実にアニメ化することがファンの期待に応える道だ」と考えていませんか?確かに、原作を尊重する姿勢は大切ですが、視聴者がアニメに求めているのは“映像としての感動体験”であり、“記憶に残る物語”です。
だからこそ、原作通りに作ることが“必ずしも正解”ではなく、アニメという武器を最大限に使って魅力を強化することで、記憶に残る作品となる場合もあるのです。
「ぼっち・ざ・ろっく!」では、原作にない妄想シーンや崩壊ギャグ、デフォルメなど、アニメだからできる表現を大胆に取り入れました。これにより、原作にはなかった“笑いの幅”と“キャラの魅力”が拡張され、ファンの間でも「このシーンはアニメだからこそ面白い」と言われるようになったのです。
例えば、教科書に書かれている知識をそのまま読むより、先生が図やアニメーションで説明してくれたほうが印象に残りますよね。それと同じで、同じ中身でも“伝え方”で記憶の強さは変わります。
| <ポイント> ・原作にない表現は“改変”ではなく“進化”だととらえる ・「これはアニメでしかできない」と言われる演出を目指す |
「私は「結束バンド」のメンバーの中では、性格がぼっちちゃんに一番似ているなと思います。」と原作者が語っているように、他の作品とはジャンルが違うという話よりも「キャラクターの解像度が高い=“感情の描写の細かさ”」こそが、作品の評価を分けたのではないでしょうか。
「ぼっち・ざ・ろっく!」は、青春やバンドという王道のテーマを扱っていながら、他の作品よりも“キャラの気持ち”の描き方が圧倒的に丁寧でした。言葉に出さない小さな不安や、気まずさを感じたときの沈黙、視線や手の動きまで、丁寧に描かれていました。だからこそ、「これ、自分みたい」とリアルに感じられたのかもしれません。
例えば、誰かと話したあと、気まずくて沈黙が続いた経験はありませんか?その気まずさを、何も言わずに画面で“見せる”だけで伝えてくる...そんな繊細な演出が多かったのがこの作品です。
| <ポイント> ・キャラの感情を“セリフで説明”するだけでなく“表情”や“沈黙”で伝える ・キャラの視点から描く世界で没入感を高める |
参考:「ぼっち・ざ・ろっく!」作者・はまじあきインタビュー「 ぼっちちゃんの性格は、私自身の投影です(笑)」 - Real Sound
アニメ化にあたり、“原作を守りつつ、今の時代に合わせて進化させる”ことで、両方の視聴者に受け入れられました。
よくある原作のアニメ化では「原作を変えすぎて批判される」か「そのままでつまらなくなる」か、どちらかに偏ることがよくあります。
「ぼっち・ざ・ろっく!」は、原作の魅力をしっかり残しながら、アニメでしかできない表現(演奏前の緊張や感情の揺れ)を追加することで、新規ファンにも“完成度の高い物語”として届きました。
例えば、マンガで読んだときには気づかなかったシーンが、アニメでは「こんなに深かったんだ」と感じられるような新しい魅力が、新規の視聴者だけでなく原作ファンにも受け入れられたと言えるでしょう。
| <ポイント> ・変える部分と守る部分の“基準”を明確にする(変えるための理由を持つ) ・原作では描かれていない“行間の感情”をアニメで補足する ・原作のファンが“もっと見たかった部分”を丁寧に掘り下げる |
参考:若手社員の熱意がグループを巻き込んで成功した『ぼっち・ざ・ろっく!』を巡る挑戦 - ANIPLEX
参考:アニプレックス若手スタッフが語る――思い描く将来像やアニメづくりにかける情熱 - Sony Music GROUP
| 成功要因 | 詳細 |
| 共感を呼ぶキャラクター設定 | 後藤ひとりの超具体的な「陰キャ」描写と成長物語が、現代の視聴者層に深く共感された |
| 作品と連動した音楽 | 著名アーティスト参加の楽曲と、ストーリーが連動することでファンが音楽を始めたくなる欲求を刺激した |
| 二次創作を促すオーバーな表現 | 後藤ひとりの妄想・奇行といった“誇張された表現”で二次創作の欲求を刺激、世界観を違和感なく表現したことで視聴者を魅了した |
| アニメーション品質と演出 | CloverWorksによる作り込まれた表現で、映像ならではの価値を引き出し、ライブシーンなどを見た目でも楽しませた |
| SNSの口コミが拡散する仕掛け | SNSでの迅速な反応とファンとの対話、切り抜き(二次創作)、楽曲の共有・コメントなどを通じて、ファン主導で話題が拡散・増幅された |
| 原作を尊重&強化したアニメ化 | 原作の魅力を最大限に引き出しつつ、アニメならではの表現を活かし、原作ファンと新規層の両者が楽しめた |
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく」を分析してみると、ヒットした理由には以下の要素が関係していることが分かります。
・キャラへの共感を呼ぶ解像度の高い設定
・楽曲とのシンクロで印象深さを強化
・二次創作を促す誇張&デフォルメされた表現
・細部まで作り込まれたアニメーション技術
・SNSで“ネタになる&語りたくなる”シーンの配置
・“原作再現+α”=忠実さと独自性のバランス
これらの要素が上手く絡み合い、SNSで話題となり経済圏が広がりました。詳しく見ていきましょう。
なぜ「ぼっち・ざ・ろっく!」のキャラクターはこんなにも共感を呼んだのでしょうか?その秘密は、主人公=後藤ひとりの「細かすぎる性格描写」にあります。
人見知り、自己否定、妄想癖など、視聴者も感じている「うまくやれない日常」を、1つ1つ丁寧に描写しています。しかも、ギャグだけで処理することなく、時には真剣な苦しみとして描くことで、視聴者は「これは私のことだ」と心を動かされます。
これまでの“理想の主人公”像とは異なり、“等身大で弱さをさらけ出すキャラ”だからこそ、多くの共感と応援が集まりました。言葉にならない気持ちや表に出せない葛藤を、まるで自分の代弁者のように描いたことで、キャラは「絵」ではなく「人」として記憶され、作品と視聴者が感情的な面でつながったと言えます。
視聴者に強く共感されるキャラクターとは、“完璧なヒーロー”ではなく、“不器用で弱いところを細かく描かれた人物”だと筆者は考えています。親近感や愛着は相手が弱さを見せた時に感じやすいものです。
「みんなの前で話そうとして声が出ない」「何かうまくできなかった時、自分を責めてしまう」──こうした経験を持つ人は多いはずです。ぼっちちゃんは、そんな不器用さを極端に描くことで、「わかる!」と共感されるキャラクターになっているのです。
| <ポイント> ・キャラクターの“できなさ”や“言えなさ”を細かく描くことを恐れない ・共感を呼ぶのは「失敗から学ぼうとする姿勢」であり、かっこよく振る舞うことではない ・心の声や妄想を“ギャグとシリアスの中間”で表現することで、親しみやすさと深みが両立する |
音楽は物語のBGMではなく、キャラクターの感情を“語るパーツ”として設計することで、作品への印象が深くなります。
「ぼっち・ざ・ろっく!」では、音楽が物語の背景ではなく“キャラクターの内面”を表すように、ライブシーンや挿入歌がマッチしていました。こうした工夫も、評価される作品の一因と言えるでしょう。
また、歌詞にはキャラの悩みや成長が織り込まれ、「この曲はこの子の人生そのものなんだ」と感じさせるものでした。視聴者は曲を聴くだけで視聴時の感情がよみがえるようになり、作品の印象が長く記憶に残るのです。
例えば、ある回のライブシーンで、ぼっちちゃんが初めて“仲間と一緒に音を出す”ことに成功します。その時の楽曲は、歌詞もメロディも彼女の「不安と喜び」が詰まっていて、演奏が進むたびに「心を乗せた音楽」として視聴者の胸に響きました。
| <ポイント> ・楽曲は“盛り上げ”ではなく“語り手”として設計する ・キャラクターの内面と歌詞を一致させ、「セリフ以上の感情」を乗せる ・演出・照明・編集のテンポを音楽の流れと連動させ、“感情の山場”を音と映像で一致させる |
ファンが“自分でも描きたくなる”作品とは、キャラやシーンの感情に、自由に解釈できる余白や愛着が存在している作品です。
「ぼっち・ざ・ろっく!」のぼっちちゃんが見せる妄想・崩壊・奇行をアニメ化の際にはオーバーに表現していたことで、「このキャラならもっとこんな反応しそう」「この場面を自分なりに描いてみたい」と思わせる“創作のタネ”になっています。
また、切り抜き画像や模写もしやすく、二次創作に向いた作品になっていました。そして重要なのは、それらの行動の根底には“不安”や“葛藤”といったリアルな感情があることです。だからこそ、ファンはネタにしても「からかう」のではなく、「共感からの愛着」をもって創作できるのです。
例えば、人見知りでツチノコ並に希少種だと自身で考える際の「ツチノコぼっち」へのデフォルメや、ぼっちちゃんがダンボールに入って隠れたい気持ちを表現するといった表現が挙げられます。
この“あるある感”と“絵にしたときのわかりやすさ”が合わさり、SNSでは大量のイラストやコメントが生まれました。
| <ポイント> ・誇張や崩壊表現を「ネタ」としてだけでなく「感情表現」として設計する ・1枚絵や短いセリフでも“そのキャラらしさ”が伝わる瞬間を意図的に入れる ・二次創作に対して寛容な態度を取り「参加しやすい雰囲気」を設ける |
アニメとしての映像クオリティも、「ぼっち・ざ・ろっく!」のヒットを支えた重要な要素です。特にライブシーンでは、演奏中の手の動きや視線の揺れまでリアルに描き切り、まるで“本当に演奏しているような空気感”が視聴者に伝わりました。
アニメの映像は「キャラクターの感情を視聴者に伝えること」ができると、作品の印象と没入感が圧倒的に高まります。CloverWorksの作画力はもちろん、構図、色彩、編集テンポなどがすべて感情の表現と連動しており、「美しい」だけではなく「伝わる」映像となっていました。
「ぼっち・ざ・ろっく!」では、特にライブシーンにおいて、演奏者の手元の動き、視線の泳ぎ、肩の震え、間の取り方までが丁寧に描かれていました。これらは単なる作画のこだわりではなく、「緊張している」「気持ちが乗ってきた」といったキャラの内面を、台詞ではなく動きで伝えるための“機能的な作画”です。
構図や色使いも、その瞬間の感情をより強調するよう設計されており、「ただ見た目が良い」では終わらない“心を動かすビジュアル”として機能していました。
例えば、ぼっちちゃんが初めて大勢の前で演奏するシーン。彼女の手がわずかに震える描写、目が伏し目がちで、時おり周囲をうかがう視線の揺れ──こうした演技は、言葉で説明されずとも「彼女がどれだけ緊張しているか」を私たちに伝えます。このような繊細な動きが、視聴者の“感情の受信”を助けるのです。
| <ポイント> ・作画の目的を「情報」ではなく「感情伝達」に置く ・キャラクターの感情が揺れる場面では、視線・手・体の“微細な動き”を演出に組み込む ・色彩や構図も、感情の強弱に合わせて変化させる(例:不安な場面では寒色系、喜びは暖色系) ・アクションや演奏など“動きの多いシーン”ほど、“静”とのメリハリを意識して演出する |
「ぼっち・ざ・ろっく!」は、放送中からSNSでのトレンド入りを繰り返しました。理由は明確で、「投稿したくなる瞬間」が数多く用意されていたからです。
SNSでバズる作品とは、偶然拡散されたものではなく、“語られたくなる瞬間”が計算された上で配置されている作品です。
「ぼっち・ざ・ろっく!」が放送のたびにトレンド入りしたのは、ただ面白かったからではないかもしれません。感情が刺激されるセリフ、予想外な作画の変化、突如挿入される妄想演出など、見た瞬間に「誰かにシェアしたい」と感じさせる要素があちこちに散りばめられていました。
さらに、公式Twitterがリアルタイムで投稿し、視聴者と一緒に作品を“実況体験”するような流れを作ったことで、SNS全体がイベントのように盛り上がる構造になっていたのです。つまり、語りたくなる感情のトリガーと拡散のタイミングが計画されていたのです。
例えば、ぼっちちゃんが突然、過剰な作画で地面に崩れ落ちるシーンがあります。この“過剰すぎる”演出は、真面目すぎず、でも気持ちは分かる。だからSNSで「わかる!」「今日の自分」といった共感と笑いが爆発的に広がりました。
| <ポイント> ・セリフや動きの中に「共感・驚き・笑い」を含むシーンを1つは配置する ・“一枚絵でも意味が通じる構図”を用意することで切り抜きしやすくする ・ネタにされやすいフレーズを意図的に演出に組み込む |
アニメ化の成功は、原作を忠実に“再現すること”だけが正解ではなく、“原作でできなかったこと”を映像の強みで補完し、“再構築”することも重要です
「ぼっち・ざ・ろっく!」の原作は4コマ漫画で、エピソードが断片的かつギャグベースです。そのままアニメにすると、ストーリーがバラバラに見えて感情の流れがつかみにくくなってしまいます。
しかしアニメ版では、キャラクターの内面や心の成長を丁寧に描きながら、各話に小さな物語の起承転結を設け、“感情が積み上がっていくドラマ”として再構成されていました。
さらに、原作にはなかった心理描写や音楽の演出が加わることで、アニメならでは“映像でしか味わえない視聴体験”へと変貌した「アニメ化の成功例」と呼べるものになっています。
例えば、ライブ前に極度に緊張するぼっちちゃんのシーン。原作では1コマのギャグで終わるようなネタでも、アニメではその前後に彼女の葛藤や自問自答の演出が追加されました。そして音楽が入り、テンポが変わり、緊張が高まり──と、感情が積み上がる構成で「1つのクライマックス」へと仕上がっていたのです。
| <ポイント> ・台詞ではなく、表情・間・音楽で“内面”を語る演出を強化する ・原作ファンが期待するシーンは再現しつつ、“新たな解釈”や“深掘り”を加える |
今ヒットしているアニメには「コンテンツとプロモーションの一体化」という“戦略的な仕組み”があり、これを取り入れた作品だけが、“話題になるアニメ”を再現できるようになっているのかもしれません。
| 施策名 | 概要・目的 |
| 事前告知の抑制 | 放送時のサプライズ感を最大化し、リアルタイム視聴を促進 |
| 放送後の楽曲・MV公開 | 視聴者の熱量が高いタイミングで楽曲を提供し、話題を持続させる |
| 公式SNSの「ネタ画像」投稿 | ファンコミュニティの文化に寄り添い、親近感を醸成、話題を提供 |
| 声優のラジオ発言からコラボ | ファンの声や声優の発言から迅速に対応してコラボなどを実現 |
| 企業とのコラボレーション | 各ターゲットへのリーチ、コラボ企業のサービスへの関心喚起 |
| 舞台・ライブへの多角展開 | 作品のリーチ層を拡大し、長期的なエンゲージメントを維持 |
| 公式YouTube「弾いてみた動画」 | 楽曲の魅力を別の角度から伝え、演奏への興味を喚起 |
「ぼっち・ざ・ろっく!」は、作品自体の魅力だけに頼っているわけではなく、宣伝活動の在り方も革新的でした。
現代のアニメの宣伝では、「情報発信するだけ」では足りず、“ファンと共に物語を広げる仕組み”として設計されることが、共感と拡散を生むカギとなります。
実際、放送前は大々的にアピールされていた作品ではありませんでした。それにもかかわらず、放送後にはSNSの口コミが広がっていき劇中の楽曲アルバムがランキング入りするなどの人気となっています。
ここからは、作品の熱量を“観る人の中”で増幅させるよう設計された宣伝施策の特徴を掘り下げます。
「ぼっち・ざ・ろっく!」のプロモーションが革新的だったのは、放送前はあえて情報量を絞って宣伝を抑えていたことです。
最初から話題を作ろうとするより、「見つけた人だけが知っている」という空気をつくった方が、熱心なファンが自然と生まれやすくなります。
結果論かもしれませんが、情報を絞ったことで、視聴者が「なんか面白そうな作品を自分で見つけた」という感覚を持ちやすくなり、「この作品、もっと広めたい」と思えるようになったのです。
例えば、友達が教えてくれたマイナーなバンドがめちゃくちゃ良かった時、「もっと多くの人に知ってほしい!」と思うことはありませんか?それと同じで、「自分だけが先に知っている」という体験は、熱量の高い応援を生むのです。
| <ポイント> ・大げさな宣伝より、「自分で見つけた」と思わせるほうが、ファンの心に深く残る |
作品の世界観を壊さずに「バイトル」「ヤマハ」といった企業やサービスとのコラボも展開され、「ストーリーと違和感のないプロモーション」が実現されていたことも、視聴者に不快感を感じさせず認知度を上げられた大きな要因と言えるでしょう。
例えば、アニメの中でぼっちちゃんがバイトするライブハウスと、現実のライブハウス「下北沢SHELTER」がコラボするといった企画が実際に行われました。
こうした関連するサービスや店舗とのコラボにより、ファンは“作品の中に入り込んだような感覚”を味わえ、ただのコラボイベントではなく“参加型の物語体験”として楽しむことができたのです。
| <ポイント> ・情報発信を“ストーリーの一部”にする意識を持つ(例:キャラ口調での発信など) ・SNS投稿やファンアートなどUGCを歓迎する明確なスタンスを公式が表明する ・“ファンが参加できる要素”を入れる(例:投稿キャンペーン、リアルイベント) ・作品の世界観と矛盾しないコラボや広告表現を意識して設計する |
関連記事:【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介
参考:下北沢SHELTER × TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」コラボグッズ - ANIPLEX
SNSの投稿は“告知”ではなく、連動した“視聴体験の一部”として活用することで、作品自体がリアルタイムで盛り上がる空間になります。
アニメが放送されている時間帯に、公式アカウントが実況したり、セリフやシーンをリアルタイムでポストしたことで、視聴者は「みんなと一緒に観ている」感覚になりました。この同時体験が、SNS投稿を“作品の延長”に変えたのです。
「ぼっち・ざ・ろっく」劇場版の公開時には、新宿駅をサイネージジャックする形でSNSのネタとなるイベントも実施することで盛り上がりを演出していました。
例えば、運動会で同じチームの子が応援してくれたら、嬉しくてもっと頑張りたくなりますよね。それと同じで、アニメ中に“公式”が一緒に盛り上がってくれると、ファンはより感情が高まりやすくなるのです。
| <ポイント> ・SNSは“ファンと作品が一緒に盛り上がる場”として使うことで、熱狂が加速する |
関連記事:デジタルサイネージ広告って効果あるの?実施を検討する前に知っておくべきことを紹介
感情が一番高まった瞬間に、関連するコンテンツを出すと、感動が長く心に残ります。
アニメの放送終了後に合わせて、劇中ライブシーンの楽曲を配信したことで、「今すぐもう一回聴きたい!」という気持ちをそのまま行動に変えてもらえました。こうして、SNSでも曲が自然にシェアされていったのです。
例えば、感動した映画のエンディング曲を帰り道に聴けたら、もっと余韻にひたれますよね。それと同じで、「感情の熱」が冷めないうちに、音楽という形で思い出せる仕組みはとても強力です。
MVの表現方法についても、現在のトレンドである「リリックビデオ」を意識して制作されており、楽曲だけでなく映像と共に楽しめることまで考慮されています。
また、実写でもライブシーンを再現するなどで、アニメとは違う楽しみ方も展開されています。
| <ポイント> ・心が動いた“その時”に届けるコンテンツは、SNS上でも自然と広がります。 |
関連記事:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説
参考:新曲を収録したシングルCD「光の中へ」が5月24日㈬リリース決定! - ANIPLEX
宣伝は運営が全部やる時代ではなく、“ファンが広げたくなる仕掛け”を先に仕込んでおくことが重要です。
「ぼっち・ざ・ろっく!」では、思わず真似したくなるシーンや、描きたくなるキャラの表情などの「ファンが二次創作したくなる切り抜き」を公式からも投稿しました。これにより、アニメを観た人が“自分で広めたくなる”流れを自然に生み、UGCと話題性を生み出したのです。
つまり、ただ放送や商品情報を告知するのではなく、“ファンが自分から発信したくなる場”を作っていたということです。
例えば、面白い写真を見つけて、思わず自分も真似して撮りたくなるような時ってありますよね。それと同じで、「自分もやってみよう」と感じてもらえれば、ファンはどんどん動いてくれます。
こうしたUGCは、広告素材としても活用できるため、積極的に促していくと良いでしょう。
| <ポイント> ・ファンが勝手に動き出せる“余白”を用意することが今の時代の宣伝力 |
関連記事:TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介
「ぼっち・ざ・ろっく!」の宣伝が特別だったのは、単にアイデアが新しかったからではありません。
視聴者の感情、行動、創作、共有といったプロセスが“演出”の一部となっていたことが大きく影響したのかもしれません。
アニメに限らず、これからのコンテンツに必要なのは「届ける」よりも「巻き込む」設計ではないでしょうか。“主語がユーザーになるプロモーション”の時代は、もう始まっています。
ここまでのポイントをまとめます。
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」のヒットは、キャラクター・演出・音楽といった作品の作り込みに加えて、“観た人の心に自然と火が灯るようなプロモーション設計”に秘密がありました。届けるだけでなく、感じさせ、動かし、巻き込んでいく...その全体像が視聴者の共感と拡散を生み、社会現象へと育てたのではないでしょうか。
あなたの作品でも、ファンの感情と行動を引き出すために「SNSでキャラクターが発信する内容を企画するガイドブック」や「ストーリーテンプレート」を資料ダウンロードページで入手して、活用してみてください。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。
動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。
例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。
「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。
・Twitterのキャラクターアカウントって効果あるの?メリットや運用テクニックを紹介
・Twitterの「中の人」が親近感を得る秘訣だった?運用テクニックや参考例を紹介
・キャラクターを使ったSNS運用のメリットとは?成功例やコツを紹介
・キャラクターアニメーションをMVに活用するメリットとは?制作事例ごとに詳細を解説
・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介
・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る
・ゆるキャラの成功事例と作り方を解説!キャラクターでPR効果を生むには
・ファンのできるキャラクターはどうやって作るの?特徴や作り方のコツを紹介
・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?
・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?
・【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説
・PR目的のイベントを成功させるには?企画のコツや開催するメリットを解説
・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介
・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介
・セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介
・【PR事例】ゲーム・アニメをリアルに体験できるイベントとは?おすすめの成功事例を紹介
・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介
・【業種別】PR動画の活用事例8選!効果的な動画にする方法も解説
・NFT(画像・動画)をPR施策にどう活用するのか?参考事例も交えて解説
・NFTを会員権として活用するPR施策とは?参考事例や注意点を紹介
・リブランディングはデザイン変更だけでは解決しない?成功・失敗事例から学べるヒント
・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説
・SNSで漫画・イラストインフルエンサーとコラボする際のおすすめは?依頼方法まで紹介
・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介
・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?
・LINE VOOMをPRに活用して失敗しないためには?各SNSとの違いや運用テクニックを解説
・モーションコミックがPR活用におすすめの理由とは?参考事例を挙げて解説
・「WEBREEN」とは?注目される理由や企業での活用ポイントを紹介
・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説
・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説
・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介
・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。