NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。


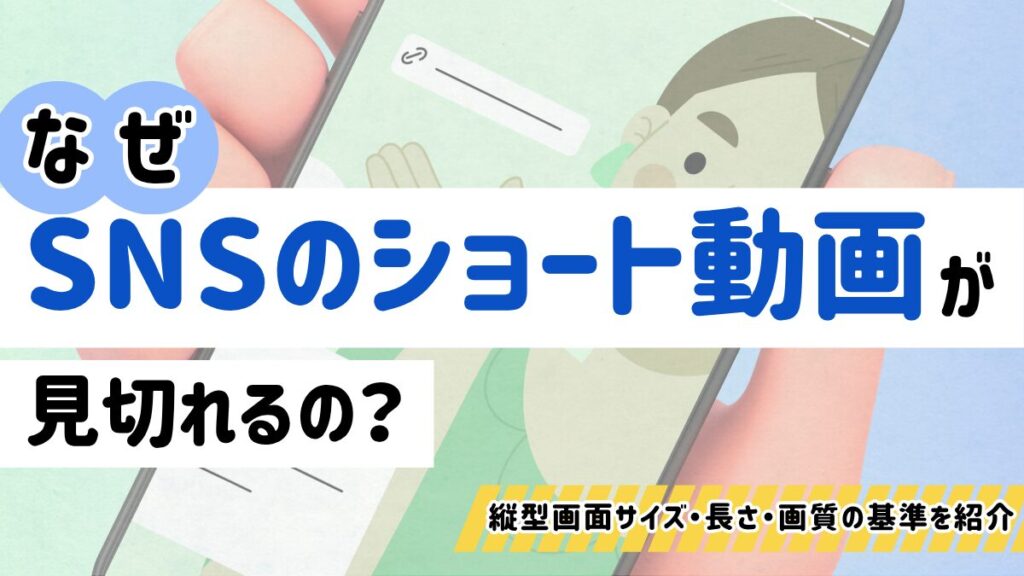
ショート動画をアップしたのに「なんか表示が変…」「文字が切れてる…」「思ったより見づらい…」と感じたことはありませんか?せっかく時間をかけて撮影・編集したのに、いざ投稿してみると肝心のシーンが画面からはみ出ていたり、字幕が見づらかったり...。
「スマホで縦型に撮れば、ショート動画としてちゃんと表示される」と、普通なら思ってしまいますが、編集アプリの書き出し設定次第で、動画が横向き扱いになってしまうことも珍しくありません。せっかくの縦型ショート動画でも、観づらいままでは視聴者の離脱が増え「なぜか見てもらえない」という状態になってしまいます。
また、動画の見た目は、スマホの向きだけでなく、編集時のアスペクト比や解像度、配置位置によって大きく左右されますが、どの比率や画質に設定すれば良いか基準が分からず余計に時間が取られてしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、ショート動画をSNSで投稿する初心者が「とりあえずこれで進めていけば問題ない」という動画のサイズ(比率)や解像度、容量の基準を紹介します。
縦型ショート動画についての詳細は「「WEBREEN」とは?注目される理由や活用ポイントを紹介」もチェックしてみてください。
ショート動画が見切れたり、表示が崩れたりするのは以下の原因に集約されます。
中でもやってしまいがちな失敗は、以下のようなケースが挙げられます。
このような状態では、どんなに良い内容でもスワイプされて見られません。対策としては、以下が基本的な方法です。
迷ったらまずは「9:16」「1080×1920」「情報を中央に集中させる」の3点を基準に投稿を作ると良いでしょう。これだけで、あなたのショート動画はどのSNSでも見やすくなります。
ショート動画の表示は縦型(9:16)が前提ですが、横向き(16:9)で作られた動画をそのまま投稿すると、SNS側で自動的にトリミングやリサイズが行われてしまいます。
これにより、意図しない部分が切れて表示される、もしくは黒帯がついて没入感が損なわれることになります。
・スマホで再生されるとき、横動画は上下に黒帯が出て小さく表示されてしまう
・また、中央だけ切り取って表示されるため、端にある字幕やロゴは見えなくなる
・フル画面表示されないことで、ユーザーの視聴意欲も下がる
・編集時に、必ず「9:16」で作ること(縦型フルHD=1080×1920)
・既存の横動画を使いたいときは、背景ぼかし+縦フレーム構成に変換する
・書き出し設定も「縦」で確認し、自動リサイズに頼らない投稿を心がける
参考:動画自動調整機能について - TikTokビジネスヘルプセンター
編集ソフトの書き出し時の解像度やアスペクト比を間違えると、映像の構図や比率が崩れます。特に、横向き設定のまま縦として書き出すと、画面が伸びたり端が見切れたりする原因になります。
・横サイズで作って、縦に書き出すと映像が縦に伸びる
・映像が細長くなったり、テキストや人の顔が歪んでしまう
・元の素材が良くても、最終的に「なんか変」に見えてしまう
・編集前に必ず「9:16 / 1080×1920」でプロジェクトを開始
・素材が横型なら、トリミングして構図を調整する or 中央だけを使う
・プレビューで縦動画として自然に見えるか確認してから書き出す
テロップが見にくい場合や、横動画をそのまま見せたい場合には「背景のぼかし」や「縁取り」を使うのが効果的です。
| ・黒の半透明ボックス(背景)をテキストの後ろに配置する ・白文字+黒縁取りにすれば、どんな背景でも文字が浮き上がる |
これにより、画面端にテロップを寄せなくても文字が“強く印象に残る”表示になります。
各SNSやスマホ端末によっては、画面の端に配置されたテキストやロゴは見切れる可能性があります。
・TikTokでは右側にボタンが縦に並び、右端のロゴが被って見えない
・Instagramは下部の説明文エリアが広く、下端の字幕が隠れる
・iPhoneとAndroidでも表示領域が微妙に異なるため、端ギリギリ配置は避ける
・上下左右に150px程度の“セーフゾーン”を設定
・ロゴ・テロップは画面中央寄りに配置する
・プラットフォーム別のUIマップを参考にした編集設計を行う
ありがちな失敗は、編集が終わったあとの動画(テロップも含む)を無理やりトリミング・縮小して収めようとすることです。これでは映像やテロップ自体が小さくなり、逆に見にくくなります。
| <代わりにやるべきこと> ・テロップ(字幕)レイヤーのみをサイズ調整 or 位置調整 ・中央寄りに移動して、画面の中心に収める ・フォントサイズを少しだけ下げてもOK(最小14pt程度を目安に) |
編集後の出力は時間もかかりますが、全体をまとめてリサイズするのではなく、該当する部分のみ編集して改めて出力し直しましょう。
文字数が多いテロップを1行に押し込めると、文字サイズが小さくなったり、画面から見切れてしまう状態になってしまいます。なにより、スマホ画面では一瞬で読み取れない字幕は離脱にもつながります。
・1行40文字以上になると、文字が縮小されて読みにくくなる
・テンポが速い動画だと、視聴者は読み切る前に次のカットに進んでしまう
・情報が多いと、どこが重要か伝わらず印象に残らない
・1行15〜20文字以内で複数行(別カット)に分割する
・キーワードだけを表示し、補足はナレーションにする
1行の文字が長いと、どうしても横幅ギリギリになってしまいます。そんなときは「内容を前後で分ける」ことで安全かつ視認性がUPします。
| Before:1カットに入れ込んでしまうケース「このアプリを使えば動画編集が誰でも簡単になります」 After:2カットで見やすくしたケース「このアプリを使えば」「動画編集が誰でも簡単になります」 |
なお、フォントはゴシック体か丸ゴシック系が読みやすく、画面でも太さが保たれやすくおすすめです。
各SNSアプリには、動画再生中に「UI(ユーザーインターフェース)」が自動的に重なるエリアがあります。ここにテロップや字幕を配置してしまうと、ボタンや説明文と重なって読みづらくなります。さらに、自動キャプション機能と自分で入れたテロップが同じ位置に重なってしまうこともあります。
TikTokの場合は、スマホ画面の右下にアイコン類(コメント・シェア)が縦に並びます。(下図参照)
このため、中央にテロップを配置する場合でも、横幅が広くなり過ぎないよう簡潔な内容にしたり、改行して見やすくすることがポイントです。
Instagramリールでは、下部にアカウント名・説明文・BGM名などが被ります。(下図参照)
TikTokをベースに配置を調整して、Instagramリールと併用するのも良いでしょう。
YouTube Shortsでは、TikTokと近い配置となっており、右下にチャンネル名やボタンUIが表示されます。(下図参照)
重要な部分が画面から見切れてしまうと、せっかく素晴らしい内容であっても伝わらなくなってしまいます。これらのUIに被らないよう注意して縦型ショート動画のサイズ調整とともにコンテンツを作りましょう。
・テロップは、上下左右150〜200pxを避けて中央寄りに配置する
・自作テロップは画面上部や中央に配置して、自動テロップと干渉させない
・自動キャプションを使う前提で、テロップを絞る(短く・少なく)
また、画面サイズにショート動画が合っていたとしても、各プラットフォームで「字幕が読まれる場所」は異なり、自動字幕といった仕様もあります。そのため、基本的には中央に内容を配置して、詰め込みすぎないことが大切です。
このような見切れを防ぐ工夫は、動画の内容以前に“見せ方の前提”として重要になるポイントです。それぞれに合った対策をして、見やすいコンテンツを投稿しましょう。
| 要素 | 推奨値 | 理由・効果 |
| アスペクト比 | 9:16 | 全画面で見せられ、没入感アップ |
| 解像度 | 1080×1920 | 画質とファイル容量のバランスが良い |
| フレームレート | 30fps | 滑らかさと軽さのちょうど良いバランス |
| ビットレート | 8Mbps前後 | 高画質を維持しつつ再生もスムーズ |
ショート動画の“サイズ”とは、単に画面の大きさを指すだけではありません。アスペクト比(縦横比率)、解像度、画面内レイアウトといったすべてが視聴体験を左右します。内容だけでなく、見やすいことも意識しましょう。
以下に当社が「とりあえずこの設定をしておけば良い」という基準をまとめましたので、参考にしてみてください。
| <おすすめの比率・画質・容量> アスペクト比:9:16(縦型、スマホ全画面) 解像度:1080×1920(フルHD縦) フレームレート:30fps(動きの自然さと容量のバランス) ビットレート:8Mbps前後(画質キープに最適) |
この「9:16・1080×1920」は、TikTok・Instagram Reels・YouTube Shortsなどの主要ショート動画プラットフォームで共通の推奨仕様です。
以下で、ショート動画制作においてよく使われるアスペクト比・解像度・フレームレート・ビットレートについて詳しく見ていきましょう。
アスペクト比とは、画面の横:縦の比率を表します。9:16は、スマホを縦に持ったときの“画面ぴったり”サイズです。
| <ポイント> ・TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsなど、すべて縦型9:16が基本 ・9:16だとフィード内で再生されたときに没入感が最大化される ・横動画や1:1動画だと、上下または左右に黒い余白が出てしまう |
解像度は、動画内のピクセル数(情報の細かさ)を示します。1080×1920は、フルHDの画質を「縦方向に使ったサイズ」です。
| <ポイント> ・スマホの画面に違和感なく視聴できる解像度でOK ・画質が高すぎる(例:4K以上)だとアップロードがスムーズにいかない場合もある ・画質が低すぎる(例:720p以下)だとモヤっとして素人感が出る |
「画質を良くしたいから4Kでアップする」という考えは、スマホ動画では“頑張り過ぎ”かもしれません。たしかに4Kは高精細ですが、ショート動画はほとんどの人がスマホで見るため、4Kの画質差に気づきにくいのです。それどころか、ファイルが重くなりすぎてアップロードや再生に支障が出ることさえあります。
例えば、スマホの画面で、巨大テレビ用の超高画質映画を見るようなもので、細部の違いはあまり感じられません。逆に、もたついた再生で損することもあります。
フレームレートは、1秒間に何枚の画像(フレーム)を表示するかを示す数値です。fpsは「frames per second」の略です。30fpsなら1秒間に30枚の画像で動画が構成されていることになります。
| <ポイント> ・自然な動きと滑らかさのちょうどよいバランス ・スマホの多くが30fps表示に最適化されている ・60fpsは滑らかな代わりにファイルが重くなり読み込みが遅くなりやすい ・24fps以下だと動きがカクカクに見えるリスクがある |
ビットレートとは、1秒間に使うデータ量(情報の濃さ)を示す数値で、動画の画質と容量を決定します。「Mbps(メガビット・パー・セカンド)」の数字が大きいほど画質が高いですが、ファイルも重くなります。フルHD解像度(1920×1080px)で30fpsの映像では、6Mbps程度のビットレートが必要と言われています。
| <実践のポイント> ・フルHD&30fps程度であれば、高画質を保ちながらファイルサイズも適正に保てる ・4Mbps以下だと圧縮で画質が荒くなることが多い ・10Mbps以上にしても、スマホ表示では差が出づらく不利になる場合もある |
動画の見た目がぼやけてしまう原因は、“カメラの性能”ではなく、“書き出しの設定”にあることが多いです。特に「ビットレート」と「フレームレート」は、画質を左右する大切な要素です。これらが低すぎると、映像がざらついたり、動きがカクカクしたりしてしまいます。
例えば、きれいな写真を、超圧縮してメールで送ったら、受け取ったときに画質が悪くなっていた…そんなイメージです。
これらの基準となる数値を参考に、見やすい動画を計画していきましょう。
毎回の作業は、事前に“テンプレート化”しておくと良いでしょう。CanvaやCapCutなどのツールでは、さまざまなテンプレートも用意されているので、それらに沿って素材を当てはめていくと簡単にサイズ調整できます。
| <ポイント> テンプレート化:編集ソフトに「9:16・1080×1920・30fps・8Mbps」をプリセット化 プレビュー投稿:各SNSに下書き投稿して表示を事前にチェック 構図設計:「上1/3に注目要素・中央に主役・下に補足」のレイアウトルールを守る ※音声も画質の一部と捉え、BGMとナレーションのバランスを調整する |
ショート動画のサイズ設定は、「どう作るか」よりも「どう見えるか」を最初に考えておくことが最も重要です。見た目で伝わらなければ、内容は届きません。これはエンタメだけでなく、企業PRや採用動画でもまったく同じです。
“サイズ=表示品質”という意識を持つことが、再生数・保存数・ファン獲得に直結する動画作りの第一歩です。
関連記事:CapCutについて - TikTok
ショート動画を作成する上で最も基本的で重要なのが「アスペクト比(画面の縦横比)」の設定です。推奨されるアスペクト比は「9:16」で、これはスマートフォンを縦に持ったときの全画面表示に最もフィットする比率です。
TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsなど、主要なショート動画プラットフォームはすべて「縦型フルスクリーン」での視聴を前提としています。9:16はそれにぴったりのサイズで、余計な黒帯や余白が発生しないため、視聴者の没入感を損なうことがありません。
例えば、16:9の横動画をそのまま投稿すると、縦表示では上下に黒帯が表示されたり、自動でリサイズ(トリミング)されてしまい、重要な情報が見えなくなることになります。
| <実践のポイント> ・動画編集ソフトで新規プロジェクトを作成する際は「9:16」「解像度1080×1920」を選ぶ |
動画を複数のSNSに投稿する際、「それぞれで比率を変えないといけないのでは?」と迷う人も多いですが、基本的には9:16で統一して問題ありません。
TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsはすべてスマホの縦画面での視聴を前提に設計されています。つまり、9:16(1080×1920)で作れば、どこに投稿しても見栄えが統一されます。
ただし、各SNSの“UI(アプリのボタン配置)”によって見え方が変わる点には注意しましょう。ショート動画の比率(アスペクト比)自体は同じでも問題ありませんが、各アプリがどこにボタンや説明文を重ねてくるかによって配置位置を調整する必要があります。
リサイズそのものより、「どこに何を置くか」の方が、もっと大事です。TikTok・Instagram・YouTube Shortsは、すべて9:16の縦動画に対応しています。
つまり、サイズを変える必要は基本的にありません。ですが、アプリごとにボタンやテキストの位置が違うため、同じサイズでも“見え方”が変わってしまうことがあるのです。
例えば、同じ写真を、LINEのプロフィールとInstagramのストーリーに使ったら、どちらかで顔が切れてしまった…そんな経験はありませんか?動画でも、文字やロゴが“アプリのボタン”に隠れてしまうことがよくあります。
| <実践のポイント> ・動画サイズは「9:16」「1080×1920」のままでOK ・テキスト・ロゴ・顔など大事な要素は中央に寄せる ・上下左右に余白(2〜3cm程度)を確保する ・各アプリでプレビュー機能を使って確認する |
本格的なカメラで撮影した横長動画(16:9)をショート動画として縦で使いたいとき、どうすれば良いでしょうか?
| ・方法1:中央を切り抜く「トリミング」方式見せたい部分(人物など)を画面中央に配置し、縦長フレームでクロップ(トリミング)して活用しましょう。これは最も自然な縦変換方法で、情報が詰まっている中央だけを抜き出すイメージです。 ・方法2:背景ぼかし+前景配置方式元動画を縮小し、背景にぼかした同じ動画や画像を敷く方法です。上下の余白が目立たなくなり、動画の情報も残しやすくなります。 |
撮影時点から「中央に見せたいものを集める」意識が大切です。横向き全体を活かすのではなく、“縦で見せる前提で横を撮る”ように意識しましょう。
“映像を縦にする”のではなく、“縦で見せる設計に直す”という意識が必要です。横動画を縦に変えると、左右の情報が切れてしまいます。
特に一眼レフのような広い画角のカメラで撮った映像は、意図した見せ方が崩れる可能性が高いため、縦型動画に合わせた“再構成”が必要になります。
例えば、テレビの画面をスマホで無理やり見ようとすると、人物の横にいた誰かが見切れていたり、文字が途中で切れて読めなくなったりしますよね。それと同じです。
| <実践のポイント> ・撮影時は被写体を画面の中央に配置する意識を持つ ・周辺が切れても違和感のない“余白ある構図”が理想 |
縦動画では、「画面の上1/3に注目が集まる」という“視線の法則”に沿ってテロップを配置することで、伝えたい情報が届きやすくなります。
スマホを縦に持って動画を見るとき、私たちの目線は画面の上あたりから流れるように下に向かうため、注目されやすいのは上1/3付近です。ここにテロップや重要な要素を置くと効果的です。
例えば、本を開いたとき、まずタイトルが目に入り、それから本文を読んでいくのが通常です。動画でも“最初に目がいく場所”が、印象を決めるポイントになります。
| <実践のポイント> ・メインとなるメッセージや顔の表情などは画面の中央〜上1/3に入れる ・下部は補足的な情報を入れてじっくり見られたときの対策に使う |
ここまでのポイントをまとめます。
どれだけ内容が優れていても、サイズが合っていなければ伝わりません。ショート動画では、視聴者の視線とスマホ画面に合わせた「見せ方の設計」が、再生数やエンゲージメントに直結します。
まずは「9:16・1080×1920・30fps・8Mbps」のテンプレートをベースに、表示される環境で“見切れずにちゃんと届く動画”をつくることが大切です。
SNSや動画作成のガイドブックも公開しているので、資料ダウンロードページもチェックしてみてください。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。
動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。
例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。
「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。
現代の視聴者は、無料でコンテンツが手に入り、見たくないものは簡単に非表示にできるため、強制的に見せる従来の広告手法は通用しません。特にTikTokなどのショート動画プラットフォームでは、視聴者の関心を瞬時に引きつけなければならないのです。
では、視聴者の関心を引く投稿にするためにはどうしたらいいのでしょうか?
じつは、アニメーション動画には、つい視聴してしまうようなエンタメ感があります。さらに、実写では伝わりにくいストーリーや抽象的なメッセージを、アニメーションなら表現しやすいのです。
このアニメーション動画に、視聴者の感情を刺激するキャラクターを起用することで、効果はさらに高まります。
ですが、TikTok向けのアニメーション動画を作るのは大変ですよね。そんなあなたにぴったりなのが、当社が提供している「TikTokアニメ」です。まずは、その魅力を以下のレポートを手に入れてチェックしてみてください。

基礎知識:企業でアニメーション動画が活用される理由とは?活用事例も解説
種類・費用:アニメーション動画制作の種類別の制作料金と活用例を解説
制作技法:インディーアニメの制作費用と仕組みを公開!MVにも使われる人気の秘密を解説
制作工程:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介
依頼方法・コツ:ショートアニメの制作を依頼するコツは?制作会社の選び方をプロがご紹介
依頼リスク:動画制作を依頼するのはリスク?後悔しないアニメーション動画制作の依頼方法を解説
制作会社:アニメーション動画の制作会社は増えている?上手な選び方をご紹介
MV制作:アニメMVで楽曲のファンを増やすには?最新マーケティング手法とMVの作り方を解説
実写比較:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法
企画方法:アニメの企画ってどうやるの?実は企画書のフォーマットは重要ではない理由
制作ツール:今話題のYouTubeアニメーション制作ツールとその特徴とは?
採用動画:多くの求職者を応募に導く!採用アニメーション動画を作るコツを解説
・TikTokでフォロワーを増やすアカウント作りのコツとは?個人・企業別の参考例を紹介
・TikTokショートドラマアカウントとは?新たなPR手法となる理由を紹介
・TikTok投稿の再生数を伸ばす投稿のコツは?分析方法やアルゴリズムの特徴も解説
・TikTokビジネスアカウントに切り替えるメリットとは?開設手順や参考例も紹介
・TikTokに楽曲提供するには?TikTokでオリジナル楽曲を収益化!
・日本版TikTokはフォロワーがいても広告収益が発生しない?複数の収益化するやり方を解説
・どうやってTikTokにInstagramを連携(解除)する?違いや使い分けのポイントも紹介
・【業者選び】TikTok運用の代行(コンサル)会社は何をしてくれる?サービス内容・費用まで紹介
・TikTok投稿のハッシュタグでバズり方が変わる?最適な数・選び方・付け方を紹介
・【TikTok広告】クリエイター起用動画を制作したいときは何をしたら良い?制作会社が解説
・TikTok事務所所属のクリエイターに制作依頼をするメリット・デメリットとは?
・【企業担当者向け】TikTokの動画制作はどうやるの?自社と外注制作を比較解説
・TikTokでフォロワーを増やす動画の作り方とは?良い投稿の特徴や事例を紹介
・成功するTikTok動画の種類とは?動画制作会社が徹底解説
・TikTokの投稿がおすすめに表示されるには?失敗原因や対策方法を紹介
・TikTok投稿が再生数0の理由はシャドウバン?急に再生されない(伸びない)原因と対策も解説
・TikTok投稿のバズり方は改善がカギ?具体的な9つの方法を紹介

NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。