NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。


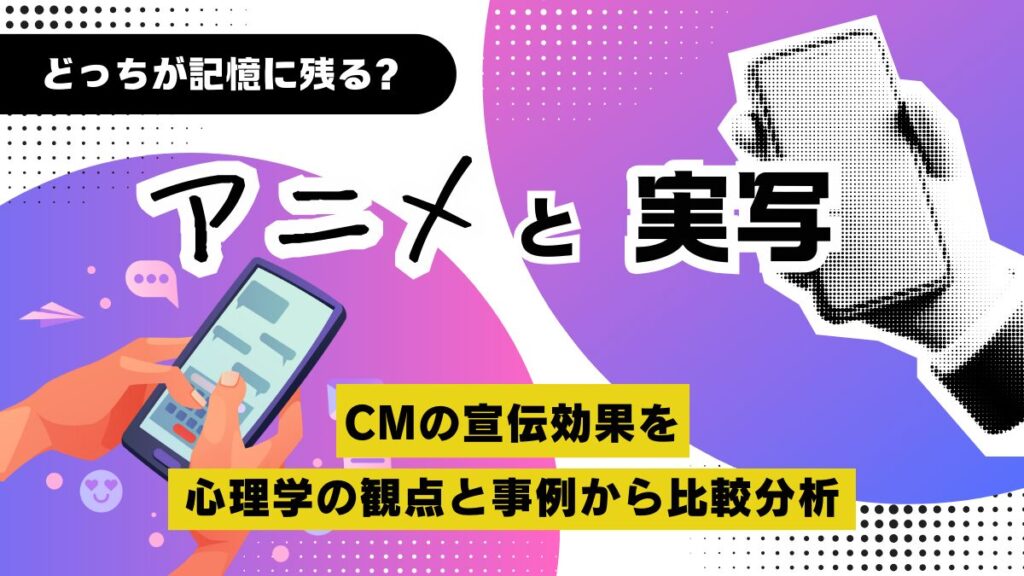
アニメや実写でブランドのCMを作っても「覚えてもらえない」「ブランド名が思い出されない」と感じたことはありませんか?企業が高額な広告費を投じても、視聴者の記憶に残らなければ意味がありません。
ですが、実写CMとアニメCMのどちらがより記憶に残るのか、その違いが曖昧なことも少なくありません。
「実写CMの方がリアルだから、視聴者に印象を残しやすい」と思っているケースもありますが、心理学的研究では、アニメCMは実写CMよりも記憶定着率が高いことが示されています。
つまり「リアルな映像=記憶に残る」とは限らないのです。
記憶に残らないCMには、共通する問題があります。それは、「見た目の特徴が弱い」「感情に訴える要素が少ない」「視聴者の想像力を刺激しない」といった点です。
また、実写CMでは「タレントの演技」や「商品そのものの映像」に頼りがちですが、これでは競合と差別化しにくいのが実情です。一方、アニメCMは制作に時間がかかるものの「非現実的な表現」を活用し、視聴者に強い印象を残しやすいのです。
そこで今回は、アニメCMと実写CMのどちらが宣伝効果があるのか?事例や心理学を考慮して比較分析して見解を紹介します。
CM制作を外注する場合は「実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介」もチェックしてみてください。
「TikTokアニメ運用ガイド」では、アニメーション動画を活用したTikTokアカウントの運用方法を公開しています。実写投稿の多い中でアニメーション投稿を行うことは注目を集めやすく、顔出しなしで可能なため自社のキャラクターを活用することと非常に相性が良いと言えます。企業でTikTokを活用したい際にご活用ください。他にも「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ入手してみてください。
| <記事のポイント> ・アニメCMと実写CMの記憶定着率の違いが分かる ・学術的に見たアニメCMの強み&相性の良いジャンルが分かる ・実写CMにアニメCMの強みを取り入れる制作技法が分かる |
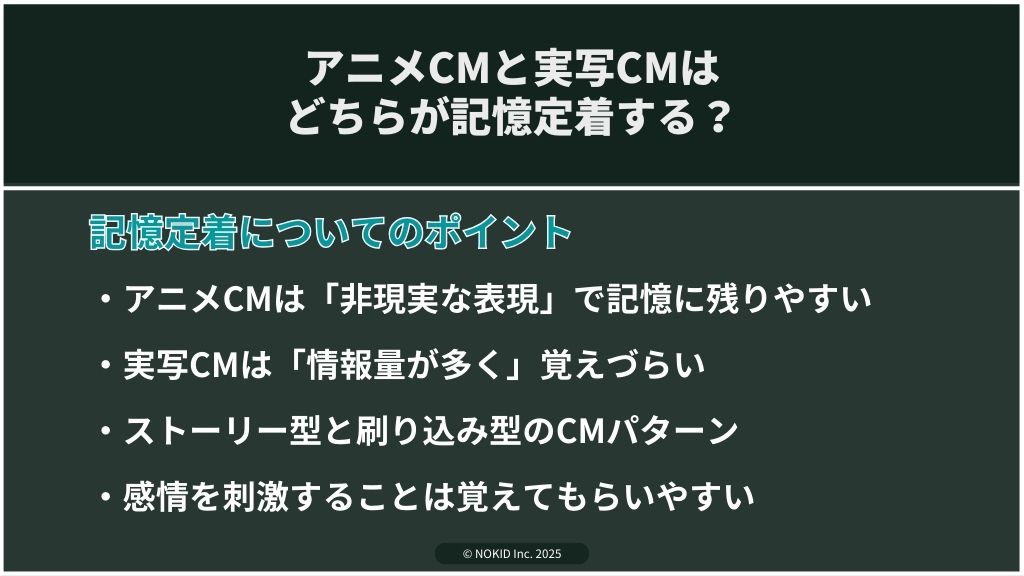
アニメCMは、色彩・キャラクターデザイン・背景などが自由に調整できるため、実写CMと比べて「独特のビジュアル」を持たせやすく、視聴者の印象に残りやすいのです。
普通の料理と、カラフルなデコレーションケーキが並んでいたら、どちらが目を引くでしょうか?アニメCMは、視聴者にとって「目を引くデコレーションケーキ」のような存在です。
人間は、現実ではありえないものに対して強い興味を抱く性質があります。これを「魔法的思考」と呼びます。アニメCMは、現実では起こりえないような設定やキャラクターを使うことで、この心理を刺激し、長期的な記憶に残りやすくなります。
例えば、「話すネコが登場するCM」と「普通の人間が登場するCM」があったとします。話すネコのほうが、現実ではありえないため、「えっ? なんでネコが話してるの?」と脳が強く反応し、印象に残りやすくなります。これが「魔法的思考」を利用したCMの特徴です。
アニメCMは、視聴者が意識的に理解しようとしなくても、ビジュアルや効果音などの影響で無意識に記憶に残りやすいのです。(Kim, Jin, & Choi, 2007)
好きな曲を何度も聴くと、歌詞を覚えようとしなくても自然に口ずさめるようになりますよね?アニメCMも、見た人が「意識しなくても覚えてしまう」ような作りができるのです。
人間は、同じものを何度も見ると、自然と好意を持ちやすくなるという性質を持っています。これを「ザイオンス効果」と呼びます。
アニメCMは、独特のキャラクターや色彩を活用して繰り返し見せることで、ブランドに対する親しみを深めることが可能です。
例えば、新しいクラスメイトがいたとします。最初はあまり気にならなくても、毎日顔を合わせているうちに「なんとなく親しみが湧く」ことがありますよね?CMでも同じで、繰り返し目にするキャラクターやロゴは、次第に記憶に刷り込まれ、親近感を持ちやすくなります。
記憶に残るCMを作るには、「視聴者の感情を動かす」ことが不可欠です。感情に訴えかけるストーリー、非現実的なキャラクター、繰り返し見せる戦略を組み合わせることで、ブランドが長く記憶され、消費者の購買行動につながるCMが作れるのです。
| 1.CM内に統一感のあるキャラクターを配置する 2.シリーズ化してCMを繰り返し放送する 3.同じフレーズや音楽を使い続ける |
実写CMは、登場人物の表情・背景・商品・字幕など、多くの情報を同時に伝えようとするため、視聴者の脳が情報を整理しきれず、結果的に記憶に残りにくくなります。リアルな情報は、無意識のうちに処理を制限しているため、記憶に残りにくいのです。
例えば、ビルが立ち並び、あらゆる看板があるような都会の人混みの映像では、何らかのポイントに意識を集中させる必要があるため、事細かに覚えることは難しいはずです。そして、リアルな画像ほど容量が大きいことからも負担が大きいことが分かります。
実写CMは、現実の風景や人物を用いるため、視聴者の脳が「ありふれたもの」として処理しやすく、他のCMと区別しづらくなります。
例えば、「白いTシャツ」を100枚並べたら、どれがどのブランドのものか分からなくなりますよね?でも、「派手なデザインのTシャツ」なら、一目で違いが分かります。アニメCMはまさに「派手なTシャツ」のような存在なのです。
| 1.アニメーションの要素を入れてシンプルにする 2.個性のある演者や設定を採用する 3.舞台設定を工夫して非現実な状況を取り入れる |
関連記事:テレビCMを配信するメリットとは?Web広告との連携や効果測定の仕組みを解説
記憶に残るCMは、「体験として心に刻まれるCM」と「反射的に思い出すCM」の2種類に分けられます。前者は、ストーリーが印象的なCMが該当し、後者は、繰り返し見ることでブランドロゴやキャラクターが記憶に刷り込まれるCMが該当します。
この2つの記憶の違いを理解することで、「CMが消費者の行動にどう影響するのか」をより深く考えることができます。
エピソード記憶は、日記に書き残された思い出のようなものです。「子どもの頃に見た感動的なCMを今でも覚えている」というのは、エピソード記憶の働きです。
一方、手続き記憶は、信号機の色を見ただけで進むべきか止まるべきかを判断できる感覚に似ています。「このロゴを見るとこの会社を思い出す」「この音楽を聞くとあのCMが浮かぶ」というのが手続き記憶に該当します。
| 1.エピソード記憶を狙うなら、ストーリー性を重視する 2.手続き記憶を強化するなら、繰り返しの要素を入れる 3.どちらの記憶も活用するなら、両者を組み合わせたCMを作る |
関連記事:ファンに愛される"企業の公式(マスコット)キャラクター"の作り方は?知名度を上げる方法も紹介
感情の強さがCMの記憶定着率を左右するのは、脳が「強い感情を伴った情報」を優先的に記憶する性質を持つためです。
ポジティブな感情が伴うCMは、視聴者に好印象を残しやすく、ブランドイメージの向上につながります。一方、ネガティブな感情を利用したCMは、視聴者の注意を引き、行動変容を促すのに適しています。
例えば、楽しいことがあった日や、大切な人との思い出は、特に鮮明に覚えていますよね。同じように、「面白かった」「感動した」「驚いた」と感じたCMは、何年経っても忘れにくいのです。
| 1.ポジティブな感情を引き出すなら、笑いや感動を入れる2.ネガティブな感情を使うなら、視聴者の関心を高める方法を考える3.状況に応じて、適切な感情の使い方を選ぶ |
関連記事:ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説
ブランドの名前を記憶してもらうには、単に「商品を紹介する」だけではなく、感情を動かすストーリーを作ることが重要です。人は感情が揺さぶられると、その体験を強く記憶する傾向があります。
例えば、友達と何気なく話したことはすぐ忘れてしまうのに、大好きな映画の感動的なシーンは何年経っても覚えていることを考えてみてください。
これは、「ただの情報」ではなく、「ストーリー」として記憶に刻まれているからです。CMも同じで、物語があるとブランドの記憶に残りやすくなります。
| 1.CMに「問題 → 解決 → 未来」のストーリー構成を取り入れる 2.家族の絆や青春の思い出など、人が共感しやすいテーマを扱う 3.CMを見た瞬間にブランドを連想できる要素(キャラ・音楽)を入れる |
参考:Thorson, E., & Friestad, M.S. (1984). The Effects of Emotion on Episodic Memory for TV Commercials.
参考:Tsiotsou, R.H. (2007). The Effect of Emotions On The Memory Of TV Commercials.
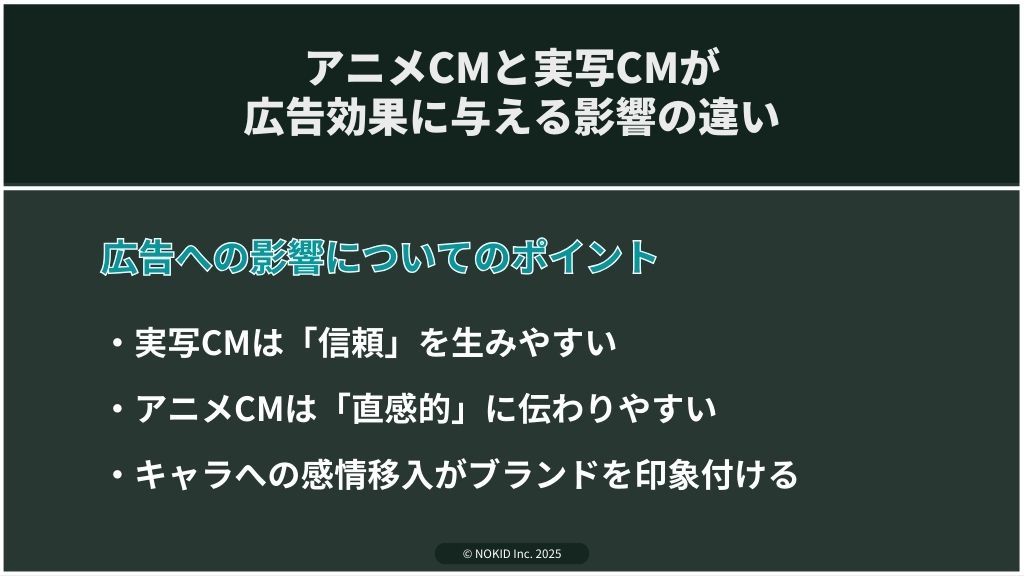
実写CMは、視聴者に「この商品は本当に存在し、信頼できるものだ」と思わせる力を持っています。その理由は、実写CMが視聴者の理性的な判断を引き出しやすいからです。一方で、アニメーションを使用すると、リスクの認知度が低下する可能性があるという研究結果が出ています。
特に、高級ブランドや医薬品のCMでは「本当に効果があるのか?」「品質は確かか?」という疑問を解消することが重要になります。
飲食店のメニューに載っている写真と、実際に目の前に出された料理では、どちらが本当においしそうか?と考えてみましょう。実際の料理を見たほうが、より美味しそうな印象を持ちやすいですよね。実写CMも同じで、リアルな映像を見せることで、「実際にこの商品を使ったらこんな感じになる」という確信を持たせやすいのです。
| 1.商品をリアルに見せることで、信頼感を生む ※例:スキンケア商品では、実際の肌を映すことで納得しやすい 2.ブランドの社会的信用を強調する ※例:企業の歴史や専門家の推薦を盛り込む 3.ターゲットに合わせて演出を変える ※例:若年層には刺激的な映像、シニア層には落ち着いた映像を使う |
関連記事:アニメーションPRと実写PRの違いとは?自社サービスをPRする最適な方法
アニメCMは、視聴者が深く考えなくても自然と記憶に残るため、保険やテクノロジー商品など、仕組みが難しいもののCMに適しています。アニメの柔軟な演出により、情報を「楽しく」「直感的に」理解できるのです。
研究結果では、アニメCMは低負荷な情報処理ルートを活用するため、視聴者の関心を引きやすいことが分かっています。
例えば、学校の授業で、先生がただ説明するよりも、図やイラストを使った方がわかりやすいことがありますよね?アニメCMは、まさにその「わかりやすい図解」のような役割を果たし、視聴者の負担を減らしながらブランドを記憶に残します。
| 1.抽象的な概念をアニメで具現化する ※例:保険CMなら、リスクを「嵐」や「道の分かれ道」など表現する2.視聴者の注意を引くために、ユニークなキャラクターを活用する ※例:企業のマスコットを登場させ、商品をシンプルに説明する3.色や動きで情報の重要度を強調する ※例:特に強調したいポイントを、鮮やかな色やアニメの動きで目立たせる。 |
関連記事:【広報担当者必見】企業や商品のブランディングにアニメーションを活用するメリットとは?
アニメCMは、視聴者の「懐かしい!」という感情を引き出し、それを購買行動に結びつける強力な力を持っています。このノスタルジー効果は、過去の楽しい思い出や安心感とブランドを結びつけ、商品への愛着を強化するからです。
昔遊んだおもちゃを見つけると「懐かしいなぁ」と思い、つい手に取ってしまうことはありませんか?これは、記憶の奥にある「楽しかった気持ち」がよみがえり、もう一度その体験をしたくなるからです。
CMでも同じで、懐かしいアニメキャラクターや昔流行った音楽を使うことで、「このブランド、昔から知ってる!」「また買おうかな」と思わせることができるのです。
| 1.ターゲット層の「懐かしさ」を刺激する要素を入れる 2.昔流行ったメロディーや、当時のアニメ風の色使いをCMに取り入れる 3.昔のキャラクターを現代風にアレンジし、「懐かしくて新しい」感覚を作る |
アニメCMでは、動物やモノを擬人化することで、視聴者の感情を引き出し、ブランドの印象を強く定着させる効果があります。「キャラクター=ブランド」として記憶に残るため、ブランドリコール(ブランドを思い出す確率)が高まります。
例えば、地域のマスコットキャラクターを思い出してください。そのキャラを見るだけで地域の名前や特産品を思い出しませんか?CMでも同じで、キャラクターをブランドの顔として使うことで、視聴者の記憶に残りやすくなるのです。
| 1.実写でもキャラを用いてブランドを一緒に認識させる 2.「このキャラが頑張ってるから応援したい!」と思わせるような物語を作る 3.シリーズ化してCMに登場させ、ブランドとの結びつきを強化する |
実写CMとアニメCMは、それぞれ異なる記憶のメカニズムを活用しています。実写CMは「信頼感」を強化し、アニメCMは「イメージ重視の理解と感情の共鳴」を生むという特性を持っています。
それぞれの特徴と、ターゲット層やブランドの目的に合わせて適切な手法を選び、CMの効果を最大化していきましょう。
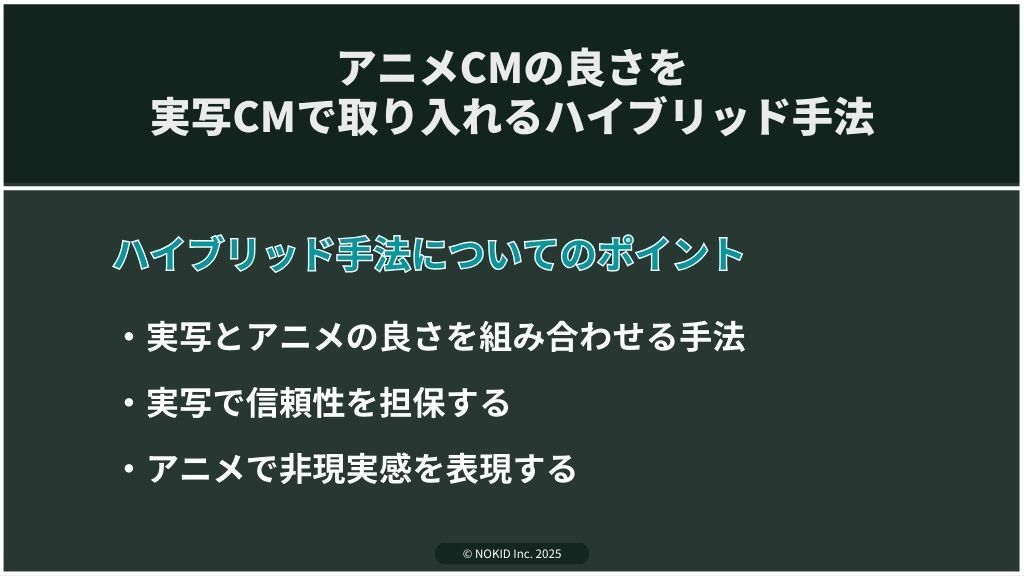
ハイブリッド手法は、実写の「リアルさ」とアニメの「独創性」を組み合わせる手法のことです。この手法により、アニメと実写の良さを併せ持った視聴者の記憶に残りやすいCMを作ることができます。
具体的には、アニメの「見慣れない映像」を生み出せることで記憶に残りやすくなり、実写によって商品の使用シーンを見せたり信頼性を担保できるのです。
例えば、映画で「実写の俳優がアニメの世界に入るシーン」を見たことはありませんか?ロトスコープは、まさにそのような手法で、視聴者に「現実と非現実が融合した特別な体験」を提供します。
| 1.ブランドの個性を活かしたビジュアルを作る ※例:スポーツブランドなら、選手の動きをロトスコープでスタイリッシュに描く 2.実写のリアルな要素を活かす ※例:商品の質感や光沢をリアルに表現しつつ、アニメならではの演出を加える 3.視聴者が「見たことない」と感じる演出を入れる ※例:人間の動きを実写のままにしつつ、背景だけアニメ化して世界観を作る |
関連記事:実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介
| 目的 | 最適なCMの種類 | 理由 |
| 信頼感を高めたい(医薬品・高級ブランド) | 実写CM | リアルな映像が信用を生む(O’Donoghue et al., 2021) |
| 若年層の関心を引きたい(ゲーム・エンタメ) | アニメCM | 非現実的な演出が記憶に残る(Subbotsky & Matthews, 2011) |
| ストーリー性を重視(飲料・食品) | 実写CM or ハイブリッドCM | 感情を刺激するストーリーが有効(Thorson & Friestad, 1984) |
| 実物と世界観を同時に見せたい(スポーツ・ファッション) | アニメCM or ロトスコープ | 動きの自由度が高く、ブランドイメージを強調しやすい |
「実写かアニメか」という選択は、ブランドが何を伝えたいかによって決まるものです。「信頼感」を重視するなら実写、「楽しく印象に残したい」ならアニメが適しています。
例えば、服を買うとき、「スーツ」はフォーマルな場に適し、「Tシャツ」はカジュアルな場に適していますよね?CMも同じで、状況に応じて最適なスタイルを選ぶことが大切です。
| 1.「誠実さ」なら実写、「親しみやすさ」ならアニメなどのメッセージに合った選択をする 2.若者向けの商品ならアニメ、中高年層向けなら実写などの視聴者に合った選択をする 3.実写に非現実感を加えるためにハイブリッド手法(実写×アニメ)も検討する |
企業がCMを制作する際は、「どんな印象を持たせたいのか?」を明確にし、それに合った手法を選ぶことが重要です。こうした表現も取り入れながら、視聴者に強く記憶される広告を作っていきましょう。
関連記事:実写・アニメーションの映像制作を外注する流れとは?費用や依頼時のポイントをご紹介
ここまでのポイントをまとめます。
視聴者の記憶に残るCMを目指すには、「リアルだから伝わる」「派手だから印象に残る」といった単純な視点では不十分です。アニメCMと実写CM、それぞれの特性と心理的効果を理解し、目的に合った戦略を選ぶことが、効果的な広告展開のカギとなります。
アニメCMづくりに活用できる広告設計やストーリーテンプレートなどのガイドブックも資料ダウンロードページにご用意しています。ご興味があれば、ぜひダウンロードまたは無料相談をご利用ください。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。
動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。
例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。
「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。
・Twitterのキャラクターアカウントって効果あるの?メリットや運用テクニックを紹介
・Twitterの「中の人」が親近感を得る秘訣だった?運用テクニックや参考例を紹介
・キャラクターを使ったSNS運用のメリットとは?成功例やコツを紹介
・キャラクターアニメーションをMVに活用するメリットとは?制作事例ごとに詳細を解説
・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介
・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る
・ゆるキャラの成功事例と作り方を解説!キャラクターでPR効果を生むには
・ファンのできるキャラクターはどうやって作るの?特徴や作り方のコツを紹介
・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?
・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?
・【事例紹介】プロジェクションマッピングを活用したイベントとは?仕組みや作品例も解説
・PR目的のイベントを成功させるには?企画のコツや開催するメリットを解説
・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介
・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介
・セミナーを売上に最大限つなげるためには?対面型とオンラインの違いやメリットを紹介
・【PR事例】ゲーム・アニメをリアルに体験できるイベントとは?おすすめの成功事例を紹介
・地域イベントで町おこしをするには?効果的なPR方法や過去のイベント事例を紹介
・【業種別】PR動画の活用事例8選!効果的な動画にする方法も解説
・NFT(画像・動画)をPR施策にどう活用するのか?参考事例も交えて解説
・NFTを会員権として活用するPR施策とは?参考事例や注意点を紹介
・リブランディングはデザイン変更だけでは解決しない?成功・失敗事例から学べるヒント
・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説
・SNSで漫画・イラストインフルエンサーとコラボする際のおすすめは?依頼方法まで紹介
・イベント集客を広告で成功させるには?運用テクニックから広告に頼らない施策まで紹介
・【事例紹介】3DCG/VR/ARをイベントで活用した新たなプロモーション手法とは?
・LINE VOOMをPRに活用して失敗しないためには?各SNSとの違いや運用テクニックを解説
・モーションコミックがPR活用におすすめの理由とは?参考事例を挙げて解説
・「WEBREEN」とは?注目される理由や企業での活用ポイントを紹介
・【企業向け】ブランディングに成功する動画の要素とは?参考事例も挙げて解説
・3DCG動画広告で効果的なPRを行うには?相性の良い広告手法から反応を得るための内容までを解説
・反応を得られるプロモーション動画の作り方とは?企画方法から外せないポイントまで紹介
・TikTok広告で使うUGC(風)動画とは?効果的に活用する方法を紹介

NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。