NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。


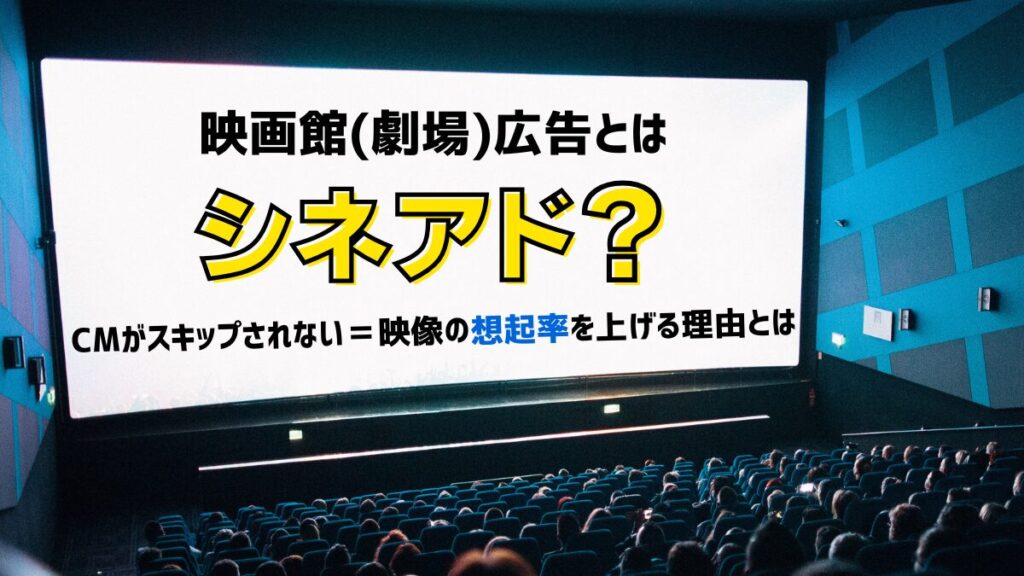
あなたも、せっかく時間と費用をかけて作った広告が、ほんの数秒でスキップされてしまう…そんな経験があるのではないでしょうか?
Web広告やSNS広告は視聴者の集中が続かず、伝えたい内容が届かないどころか、存在すら認識されないまま終わることも少なくありません。「広告はスキップされるのが当たり前」と考え、それでも観たいと思えるような広告を作っていくことも良い方法ですが、じつは視聴環境も考えるべきポイントです。
視聴者が広告を飛ばすのは、広告がつまらないからだけではなく、“他のことに意識が向いて視聴しないだけ”の場合もあるからです。つまり、広告がどれだけ良い内容でも、集中や共感を生まないと、広告は“存在しなかったこと”になってしまうのです。
こうした点で、シネアドといった映画館(劇場)広告は、スキップされないだけでなく、感情が動きやすい状況でメッセージを見てもらえるため、印象に強く残ります。
この手法は、ブランドイメージを重視したい企業や自治体、またはターゲットの感情を動かす必要があるプロモーションに適しています。一方で、短期的なCVだけを目的とした広告などには向かない場合もあるため、使用目的と親和性をしっかり見極める必要があります。
単に広告を流すのではなく、「物語」として観客の心に残るような設計をしている点です。今こそ、自社の広告も“観る価値がある体験”に変えてみませんか?
スキップされない環境で、感情と記憶に届く広告を届けるというのが劇場広告という新たな可能性です。
そこで今回は、シネアドを例に映画館(劇場)広告の特徴や他メディアとの違いなどを紹介します。
同時に検討されやすいデジタルサイネージ広告についての詳細は「デジタルサイネージ広告って効果あるの?実施を検討する前に知っておくべきことを紹介」もチェックしてみてください。
SNS、YouTube、TikTok──私たちは今、毎日大量の広告を目にしています。正確に言えば、“目にしているように見えるだけ”です。本当は、ほとんどの広告が「数秒でスキップ」されているというのが現実です。
あなたの広告は、どうでしょう?本当に誰かが見て、最後まで理解して、記憶に残してくれているでしょうか?
多くの企業や広報担当者が、「出せば届くはず」という幻想を抱き、膨大な広告費と時間をかけています。しかし結果は、スワイプひとつで消され、再生から数秒で離脱…これはもう、個人や企業の努力がどうこうではありません。視聴環境そのものが変わってしまったのです。
現代は、“見てもらう前提”が通用しない時代です。だからこそ重要なのは、「どう作るか」より先に、「どこで見せるか」なのかもしれません。
メッセージを届けたいなら、まず“目の前に立つ”ことです。そのために、広告の考え方自体をアップデートする必要があります。
| <実践のポイント> ・「飛ばされる前提」で広告を考える ・広告が再生された=見られた、ではないと認識する ・最初の3秒以内に“見たい”と思わせる仕掛けを作る |
「うちは10万回も動画が再生されました!」
これは、本当にすごいことでしょうか?
Googleによれば、インストリームフォーマット(動画内でテレビCMのように広告が挿入される手法)では、視聴完了率がわずか10~15%程度が「すべての業界での平均」と考えられていると記載の通り、多くがスキップされてしまうのです。そのため、広告で訴求する以前に「観てもらうことがもっとも難しい」ハードルなのは明らかです。
再生された回数ではなく、“最後まで観られた回数”に注目してください。多くの動画広告では、視聴完了率は10%程度です。つまり、9割近くの広告費が一部しか観られていない=しっかりとメッセージが伝わっていないかもしれないということです。
それは、見られる前にスキップされた広告、あるいは途中で離脱された広告です。あなたが伝えたかった大切なメッセージは、誰の心にも残っていない可能性が高いのです。
広告に関わると、どうしても数値に目が行きます。表示回数・クリック率・コンバージョン…しかし、その裏にある“体験”を見失ってはいけません。
真の効果とは、「あとで思い出す」「人に話す」「行動を起こす」といった“記憶に残る体験”が、広告の本質です。
| <実践のポイント> ・再生数より視聴完了率をKPIにする ・短くてもストーリー性のある構成に工夫する ・最後まで観て飽きさせない工夫を盛り込む |
関連記事:YouTubeチャンネル運用の重要指標「視聴者維持率」の対策方法を徹底解説
広告がスキップされるのが当たり前だからこそ、スキップされない環境にも目を向けてみましょう。そのための方法のひとつが映画館広告なのです。
映画館(劇場)でのCMは、観客が逃げられない環境で流れる広告です。席に着いた観客が、真っ暗な空間で、巨大なスクリーンに集中している…そのタイミングで、あなたのCMが流れたらどうなるか...?全員が、黙って見るのです。
多くの人が、「広告の内容を変えれば見てもらえる」と考えます。けれど、本当に重要なのは、“適切な人に集中して見てもらうことです。伝える環境を変えるだけで、同じ内容でも見られ方、残り方、伝わり方が大きく変わるのです。
見られない広告を作り続けるのか?それとも、見られる場所で、届く広告を作るのか?ペルソナや広告クリエイティブだけでなく、届ける場所も改めて考えてみましょう。
| <実践のポイント> ・スキップされない環境(劇場広告)を戦略に取り入れる ・観客の「全集中」が得られる空間で広告を見せることで記憶にも残る ・SNSやWeb広告と使い分けて、見せる場所を選ぶ視点を持つ |
関連記事:実写・アニメを融合した合成CM(MV)が増加中?理由や魅力・事例を紹介
記憶に残る広告には、必ず“集中できる環境(または視聴する意欲)”と“感情が動く体験”が必要です。映画館はこの両方を兼ね備えた、極めて希少な空間です。
広告の記憶定着率は、一般社団法人日本民間放送連盟の調査結果によると、テレビCM(動画広告)接触者の「広告認知率」の平均は約18%となり、動画広告は約10%という結果が出ています。対して、劇場・映画館CM(シネアド)は、接触者の約70%が内容まで理解していることからも、集中しやすい環境での視聴が重要なことは明らかです。
これは当社の経験上でも同じ印象であり、理由は映画館では観客が“広告を観る(メッセージを受け取る)準備ができている”からだと考えられます。照明が落ち、私語が禁じられ、スマホも使えず、全員が前を向く空間──この集中の場に流れるCMは、他のどのメディアよりも深く心に刺さります。
広告は、“出す”ことが目的ではありません。“届く”こと、そして“残る”ことがなければ、どんなに費用をかけても意味がありません。
広告内容を見直す前に、その広告が届けられている「空気」や「空間」を見直してください。
映画館という場所は、広告が“きちんと届く環境”の、今や数少ない選択肢です。メッセージをちゃんと受け取ってもらえる場所に届けましょう。
| <実践のポイント> ・CMを作るときは「何を伝えるか」よりも「どこで伝えるか」にも着目する |
映画館CMは「没入感が強い」と言っても、観客が観に来た映画のジャンルによって、その感情の状態は大きく異なります。
例えば、アクション映画を観に来た人は、テンションが高くスピード感を求めています。その中で流れるCMは、「勢い」や「興奮」を刺激する演出が合うでしょう。
一方で、家族向けアニメや感動系ドラマを観に来た観客は、「優しさ」や「共感性」にチューニングされているため、柔らかいトーンのCMの方が記憶に残りやすいのです。
このように、映画の内容=観客の心理状態に合わせた広告設計ができるのも、劇場広告ならではの強みです。貴社の伝えたい想いを、観客の心にしっかり届けるなら、スキップされない“感情の舞台”=映画館CMという選択を加えてみてください。
| <実践のポイント> ・シネアドを出稿する際は「どの映画と一緒に流れるか」を重視する |
映画館(劇場)でCM上映ができるシネアドは、「上映前の大スクリーンで流れる動画広告」として知られていますが、じつはその種類や表現の幅は非常に広く、さまざまなターゲットと目的に応じて活用できます。
まず、一般的な15秒〜60秒のスポット型CMはもちろん、作品のジャンルに合わせたストーリー仕立ての広告や、地域性を活かしたご当地CMといった活用まで可能です。
例えば、地元の中小企業が制作した15秒の簡潔な広告が、上映される地域で大きな話題を呼ぶことも少なくありません。
また、全国一斉配信だけでなく、「○○県の△△映画館で、○○系のアニメ映画が上映される期間中だけ」といったように、作品やエリアをピンポイントで指定できる柔軟性も、テレビ広告やWeb広告にはない大きな特長です。
つまり、シネアドは「予算が限られている中でも、しっかり“伝える”ことに集中した広告設計」が可能な、非常に戦略的な広告手段なのです。
テレビCMやYouTube広告と劇場広告(シネアド)の最大の違いは、“スキップされない”という環境にあります。
YouTubeのインストリーム広告などは「一定の秒数が経過したらスキップ」、テレビでは「CMになったらスマホに目を落とす」など、視聴者が広告から目をそらす方法はいくらでもあります。しかし映画館では、観客が着席し、照明が落ち、集中してスクリーンに視線を向けているタイミングで広告が流れるため、視聴を避けることができません。
さらに、映画を見るという行為自体が“感情を揺さぶられる体験”なので、その中で流れる広告は自然と心に刻まれやすくなります。感動的なストーリーの直後に続く温かいメッセージや、期待感を持って観るアニメの前に流れるPRなどは、記憶にも感情にも強く残ります。
つまり、広告がただの「宣伝」から、「思い出の一部」になるというのが、劇場広告が持つ最大の魅力です。
映画館広告(シネアド)は、ただの「映像メディアの一種」ではなく、「広告を伝える力が最大化される環境」でもあります。スキップできず、没入感があり、記憶に残る...こうした特性を知り、自社で活用できないか考えてみましょう。
関連記事:【YouTube広告】インストリームとインフィード動画広告(ディスカバリー広告)を最適化するには?効果的なアカウント設定を解説
映画館CMにおける動画広告の「長さ」や「形式」は、ある程度のガイドラインはありますが、テレビCMよりはるかに柔軟です。
基本的には15秒、30秒、60秒などの尺での設計が多く、上映映画との調整も行われたうえで放映されます。映像の形式も、一般的なHD〜4K画質に対応しており、ナレーション、音響設計、字幕などの要素も含めて設計することで、映画館の空間に最適化された演出が可能です。
ただし注意したいのは、「映像制作=テレビCMの使い回し」では効果が落ちるということです。映画館という特殊な環境を前提にした構成、メッセージの出し方、感情への訴求が必要不可欠です。
映画館(劇場)広告のシネアドは、ターゲティングが難しいと感じられがちですが、実際には"明確なターゲット層"にリーチしやすいメディアです。
特に効果的なのは、以下のような層です。
| ・映画を"体験"として重視する層(20代〜40代)・夫婦や家族連れで来館する地域密着型の観客・映画のジャンルによって特定の嗜好やライフスタイルが読み取れる層 |
例えば、アニメ映画を観に来る親子層には、自治体の子育て支援策や教育コンテンツが刺さりやすく、アクション映画を観る若年男性には、自動車やエンタメ系のサービス広告が響きます。劇場広告は、作品選定を通じてターゲットの心理や生活スタイルに直接届くため、より共感されやすいのです。
広告出稿時には、「どんなジャンルの映画を観る人に伝えたいか」を明確にし、その上で「どの作品に広告出稿するか」を選定しましょう。
映画館(劇場)広告のシネアドは、意外にも"エリア×作品"で非常に精緻なターゲティングが可能なため、大企業だけでなく中小企業や自治体でも活用可能です。全国一律に出す必要はなく、対象の出稿場所(市区町村単位・特定の映画館単位など)で出稿できるため、地域密着型のマーケティングにも扱いやすい媒体です。
例えば、三大都市か指定県内のスクリーンや作品に限定して上映している事例があります。他にも、15秒CMの上映を映画館1館だけ=月間60万円ほどに費用を抑えて、6ヶ月間上映する長期継続を重視した活用方法もあります。
さらに、作品のジャンルや上映スケジュールを活用して、季節イベントや特定のキャンペーンに合わせた出稿も良いでしょう。
| 例:・地元のアニメ映画館で流す"子育て支援"の行政CM・夏休みのファミリー映画に合わせた"地元遊園地"のCM・年末の話題作に合わせた"ふるさと納税"訴求CM |
どの作品がいつ・どこで上映されるか、配給スケジュールを確認し、キャンペーンと連動させた出稿戦略を立てましょう。
ここまでのポイントをまとめます。
スキップが前提となった時代の中で、広告が“きちんと見られる場所”はごくわずか。その中でも映画館広告(シネアド)は、集中力と感情を引き出す特別な舞台です。ターゲットに合ったジャンルやエリアを選定することで、メッセージを深く届けられる唯一の選択肢となり得ます。広告を「流す」から「心に届く」に変えたい方は、今すぐシネアドの戦略ガイド資料をダウンロードください。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。
動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。
例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。
「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。
・ブランディング動画で感動を与えるには?効果・活用方法・作り方のコツを解説
・【事例付き】アニメブランディング動画を制作する際に抑えたいポイント
・ブランディング動画制作を依頼する際の注意点とは?アニメーションが活用されやすい理由も紹介
・企業ブランディングに成功する動画の内容は?参考事例を挙げて解説
・キャラクターを使ったSNS運用のメリットとは?成功例やコツを紹介
・Twitterのキャラクターアカウントって効果あるの?メリットや運用テクニックを紹介
・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介
・TwitterでUGC(口コミ)が爆増した事例は?ユーザーを巻き込むコツも解説
・YouTubeショートの活用方法とは?企業の事例やZ世代へのアプローチ方法を解説
・ファンのできるキャラクターはどうやって作るの?特徴や作り方のコツを紹介
・ファンコミュニティサイトとは?SNSとの違いや運営方法を紹介
・Discordがコミュニティ作りに活用される理由とは?熱狂的なファンが勝手にできる仕組みを解説
・NFTホルダー限定コミュニティの作り方とは?おすすめ管理ツールや事例を紹介
・コミュニティ運営は難しい?具体的な課題やマネジメントのコツを紹介
・コミュニティマーケティングとは?企業で取り組む価値やファンベースとの違いを紹介

NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。