NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。


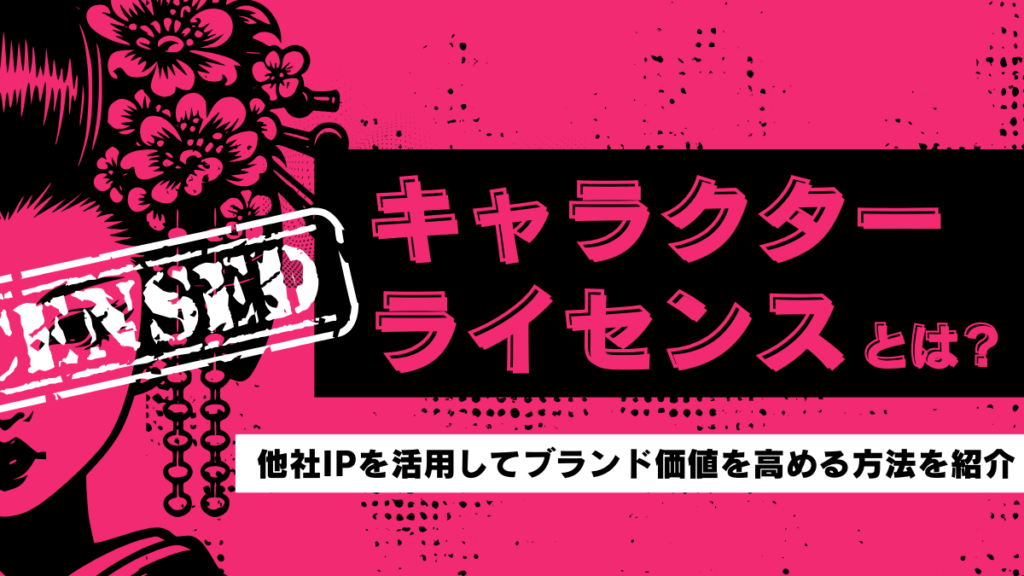
キャラクターライセンスに関する契約の複雑さや高額な費用に苦労していませんか?これまで、人気キャラクターを使ったプロモーションが予算オーバーで断念されたり、契約条件の不明瞭さでトラブルが発生した企業も少なくありません。
「キャラクターライセンスは高そうで大企業しか割に合わない」というイメージがあるかもしれませんが、そうではないのです。ライセンス料は柔軟に交渉可能であり、使用範囲や期間を工夫すれば中小企業でも効果的に利用できます。また、必ずしも有名キャラクターにこだわらず、ターゲット層に合ったキャラクターを選ぶことで、より高い費用対効果を得ることが可能です。
キャラクターライセンスの難しさは、契約の複雑さや費用の不透明さにあります。特に、ロイヤリティ計算や使用範囲の制限を理解しないまま契約を進めると、追加費用が発生したり、想定していた成果が得られないことがあります。さらに、市場調査を怠ると、ターゲット層に響かないキャラクターを選び、プロモーションの効果が半減してしまいます。
キャラクターライセンスは、適切に活用すれば、ブランド価値を高める非常に強力なツールです。次のステップとして、自社のターゲット層を明確にし、その層に合致するキャラクターを選ぶことから始めましょう。また、契約条件を事前に詳しく確認し、必要であれば専門家に相談することで、成功への道を確実に進むことができます。
IPについては「【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?」をチェックしてみてください。
キャラクターを「自社に合う見栄えか?」だけで作っても、顧客から受け入れられないことがほとんどです。なぜなら、ユーザーは多くの情報に晒されており、自分が興味を持つものしか見ないからです。興味を持つことは、共感したり何らかの感情的な刺激が必要になります。そのためには、キャラクターの人格や設定などが重要だということです。魅力的なキャラクターを作る要素などの「キャラクター作りのポイント」を「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ活用してみてください。
| <記事のポイント> ・キャラクターライセンス(IP版権)についての詳細が分かる ・キャラクターライセンス(IP版権)の使用料(相場)が分かる ・キャラクターライセンス(IP版権)の契約で注意するポイントが分かる ・キャラクターライセンス(IP版権)を活用したプロモーション方法が分かる |
2023年の世界におけるライセンス小売市場規模は3,565億ドルであり、その中でも、エンターテインメント・キャラクター分野が1,476億ドルで全体の41.4%を占めることが分かっています。このように、アニメやゲーム、映画のキャラクターは、商品の魅力を高め、ブランド価値を向上させる強力なツールとなっています。ここからは、具体的にどのような活用ができるかを紹介します。
キャラクターライセンスとは、キャラクターを商業的に活用するために権利者(ライセンサー)が他社(ライセンシー)に使用を許可する契約です。
この契約によりライセンシーは、キャラクターを商品のパッケージや広告、グッズ展開に使用して「ブランド価値や売上アップ」を目指せます。一方で、権利者は収益化を図りながらキャラクターの認知度を広げることが可能です。
例えば、人気キャラクターが、コンビニの商品パッケージに使用されるケースを考えてみましょう。この場合、キャラクターの認知度により、商品が親近感を持たれるだけでなく、消費者の購入意欲が高まります。
| 1.使用するキャラクターが自社ブランドの価値観やメッセージに一致していることを確認する 2.子ども向けなら親しみやすさ、大人向けなら懐かしさなど、顧客が反応するキャラクターを選定する 3.一時的な使用ではなく、継続的な使用でキャラクターをブランドの象徴に育てる戦略も検討する |
関連記事:認知・ブランディング広告って必要なの?運用のテクニック・考え方を解説
ライセンス契約は、以下の流れで進められることが一般的です。各段階で、条件の明確化やリスク管理が重要なポイントとなります。
例えば、カフェチェーンが人気キャラクター「スヌーピー」のライセンスを取得して季節限定のプロモーションを行う場合を考えてみましょう。
| <例> 1.選定:親しみやすいキャラクターがターゲット層にマッチすると判断して「スヌーピー」を選ぶ 2.アプローチ:キャラクターの権利を管理するライセンスエージェントに連絡を取り、条件を確認 3.交渉:使用範囲を「店舗の装飾とSNSキャンペーン」に限定し、ライセンス料を抑える交渉を実施 4.契約:契約書で使用範囲やロイヤリティ、違反時の対応を明確にして合意形成する 5.使用:条件に従い使用を開始&契約に従ってロイヤリティを支払う |
| 1.目的、予算、ターゲット市場を明確にし、キャラクターライセンスに必要な情報を揃える 2.条件を細かく確認し、ロイヤリティや使用制限など、両者が納得できる内容に合意する 3.使用許諾を受けたキャラクターをプロモーションや製品に活用して結果を測定する |
関連記事:【顧客拡大】キャラクター活用のリブランディング戦略とは?失敗例も紹介
ライセンス契約には、以下のような条項が含まれます。特に、使用範囲、ロイヤリティ、期間の3つは、権利を使用する企業(ライセンシー)と権利者(ライセンサー)の双方にとって最も重要な条項です。これらの条項が明確でない場合、後々トラブルに発展するリスクがあります。
| 条項 | 内容 | 参考例 |
|---|---|---|
| 使用範囲 | ・商品化の対象となる製品カテゴリー ・使用可能な地域や期間 ・キャラクターの使用方法(デザイン、色など) | ・製品カテゴリー:Tシャツのみ ・使用可能な地域や期間:日本国内(店舗)、1年間の期間限定 ・キャラクターの使用方法:特定のデザイン、サイズ ・色は都度承認が必要 |
| ロイヤリティ | ・売上高の一定割合の設定 ・最低保証金額の設定 ・支払い頻度(月次、四半期ごとなど) | ・売上高の一定割合:売上の10% ・最低保証金額の設定:年間500万円 ・支払い頻度:月次 |
| 品質管理 | ・製品のサンプル承認プロセス ・品質基準の遵守 | ・製品のサンプル承認:事前承認が必要 ・品質基準の遵守:指定の印刷精度を遵守 |
| 契約期間 | ・契約の開始日と終了日 ・更新条件 | ・契約の開始日と終了日:開始日は未定、期間は1年間 ・更新条件:双方の合意で1年単位の更新 |
| 独占性 | ・独占的ライセンス ・非独占的ライセンス | ・独占的(非独占)ライセンス:非独占 |
| サブライセンス | ・サブライセンスの許可(または禁止) | ・サブライセンスの許可(または禁止):禁止 |
| 商標・著作権の表示 | ・製品への適切な権利表示の方法 | ・権利表示:「©︎(企業名など)」の表記が必須 |
| 監査権 | ・ライセンサーによる売上や在庫の監査権利 | ・監査権利:売上報告、在庫記録を年1回まで監査可能 |
| 契約終了後の取り扱い | ・在庫の処分方法 ・知的財産の返還 | ・在庫の処分:指示に従い販売停止を行う ・知的財産:関連資料を返還する |
こうした条件を明確にしながら範囲を限定することで、キャラクターの使用を実現しつつ収益拡大を狙っていくことが可能です。
| 1.ブランドイメージや市場戦略に応じて、使用範囲を決定する 2.売上予測をもとに、最適なロイヤリティモデル(固定/変動)を選択する 3.キャンペーンや商品の販売計画に合わせ、契約期間を調整する |
関連記事:キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説
人気キャラクターは一見すると魅力的な選択肢ですが、ブランドとの相性が悪ければ逆効果になります。
単なる知名度だけでなく、ブランドの価値観やメッセージと一致するキャラクターを選ぶことで、消費者に一貫したイメージを伝え、ブランドロイヤリティを高めることができます。
例えば、高級感を売りにするブランドがコミカルなキャラクターを使用すると、ブランドイメージに齟齬が生じる可能性があります。同じように、ヘルスケアブランドが暴力的なイメージのキャラクターを使えば、消費者はブランドの信頼性に疑問を感じるでしょう。
| 1.自社ブランドのミッションやコアバリューに一致するキャラクターを探す 2.キャラクターが持つ背景やイメージが、自社ブランドのターゲット層に適しているか確認する 3.顧客インタビューやアンケートなどを活用して、キャラクターの印象や適性についての意見を収集する |
同じキャラクターでも、独自のストーリーや使い方で差別化できます。こうした場合、独自性のあるストーリーやプロモーション展開を工夫することが大切です。
例えば、キャラクターの異なる側面や設定を強調したり、独自のストーリーラインを作成することで、他社とは異なるブランド体験を提供できます。他には、キャラクターと自社製品の独自の組み合わせや限定版商品を展開することも効果的です。
| 1.自社ブランドの商品やサービスとキャラクターを絡めたオリジナルのストーリーを展開する 2.自社だけが提供できる特別な体験やコンテンツを用意する 3.SNSやイベントなど、競合が使っていないプロモーションチャネルを選ぶ |
関連記事:キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る
キャラクターを選ぶ際には、ターゲット層のニーズや嗜好を徹底的に分析することが不可欠です。ターゲット層のライフスタイルや価値観に基づいて選ぶことで、キャラクターがブランドの「共感を引き出す役目」を担ってくれます。
例えば、若年層向けにレトロなキャラクターを選ぶと、トレンドに敏感な層には逆効果となることがあります。一方、懐かしさを感じる中高年層からは大きな共感を得ることができるかもしれません。
| 年齢層:キャラクターのファン層が自社のターゲットと一致しているか 性別:キャラクターが特定の性別に強く支持されている場合、その点を考慮する 文化的背景:キャラクターが特定の文化や地域に関連している場合、ターゲット層に適しているか |
| 1.ターゲット層の趣味や好きなキャラクターの傾向をリサーチする 2.地域や国ごとの文化や流行に合わせたキャラクターを選ぶ 3.キャラクターがブランドの理念やビジョンと一致しているか評価する |
これらのポイントを踏まえて、自社ブランドに最適なキャラクターライセンスを選定し、消費者との深い関係を構築しましょう。
キャラクターライセンス契約の盲点を見逃すと、ブランド価値を損なうリスクが高まります。
キャラクターライセンス契約でよくあるトラブルとして、当社が関係各社を見てきた中で多かったケースは「使用範囲の解釈がズレる」「ロイヤリティ計算方法が不明確」「契約終了後の処理違反」が挙げられます。
これらを防ぐためには、契約書に具体的な使用方法や計算式を明記し、双方の理解を一致させることが重要です。実際に、文化庁の「著作権契約ガイドライン」にも、契約条件を明確にすることの重要性が繰り返し強調されています。
例えば、某アパレルブランドが、人気キャラクターをTシャツに使用する契約を結んだとします。契約書では「国内販売」のみ許可されていたにもかかわらず、オンラインショップで海外販売も行ったため、高額な違約金を支払う結果となるようなケースです。
| 1.キャラクターを使用できる範囲(地域、媒体、用途)を明確に記載する 2.契約満了後に発生する制約や権利の扱いを確認する 3.キャラクターの使用が競合他社や第三者にどの程度制限されるかを確認する |
権利者(ライセンサー)は、自分たちに有利な条件を提示することが一般的ですが、その意図を読み取れば交渉の余地を見つけやすくなります。特に「使用範囲」「ロイヤリティ」「契約期間」は、契約者間の期待値を合わせるために設けられています。
例えば、「売上比率制」は、ライセンサーが一定の権利収入をすぐに得るよりも、長期的に多くの利益を期待していると読み取れます。
| 1.条項がライセンサーにどのような利益をもたらすのかを考え、バランスの取れた提案をする 2.具体的な数値や事例を提示して、契約の妥当性を示す 3.専門家や法務担当者に契約書をレビューしてもらい、見落としを防ぐ |
文化庁の調査報告書によると、著作権契約における紛争が契約内容の解釈の違いから発生することもあります。交渉前に双方の期待をすり合わせるためにも、特に利用料に関連した部分は理解しておきましょう。
ライセンス料の適正価格は「売上への影響」と「費用対効果」のバランスで決まります。多くのライセンス契約では、売上の5〜15%を基準とすることが一般的ですが、その背景にはライセンサーの利益確保とライセンシーの負担軽減のバランスがあります。
例えば、人気アニメのキャラクターを使ってスナック菓子を販売する場合を考えます。売上5%がライセンス料となる契約では、ライセンサーはキャラクターの認知度で権利収入アップを期待できます。一方、ライセンシーにとっては、固定料金制よりもリスクが下がる代わりに、費用の負担が増える可能性があります。
ライセンス料の算出方法は、キャラクターの市場価値、使用範囲、契約期間などの要素などを考慮して、固定料金制、売上比率制、またはそのハイブリッドモデルが用いられます。
| 1.契約前に、ライセンス料率が適切かどうかを市場調査や類似事例と比較して確認する 2.提携するキャラクターの市場での認知度やファン層の購買力を分析する 3.使用範囲を地域限定や期間限定に絞ることで、ライセンス料の効率が改善する |
※上記の相場や目安はあくまでも一般的なものであり、実際のライセンス料は個別の契約によって異なります。 正確な情報を得るためには、ライセンサーに直接問い合わせることをお勧めします。
固定料金と売上比率は、それぞれに異なるリスクと利益があるため、企業の規模や商品の特性に応じて、最適な方式を選ぶ必要があります。どちらのロイヤリティ構造を選ぶべきかは、ライセンシーの事業規模や収益予測、キャラクターの影響力に左右されます。
例えば、売上が安定している場合は固定料金制が適していますが、売上予測が不確実な場合は売上比率制がリスクを抑えやすい選択肢となります。
売上比率制は、双方にとって利益を最大化する手法として広く採用されており、リスクを分散しやすい仕組みです。一方、固定料金制はコストが明確で、予算計画を立てやすいものの一定の売上が見込めなければ成り立ちません。
| 1.事業規模や売上見込みに基づいて、固定料金と売上比率のどちらが有利か計算する 2.キャラクターが売上に与えるインパクトが大きい場合、固定料金も検討する 3.試験運用では売上比率、事業が軌道に乗れば固定料金に切り替えられる条項を検討する |
参考:ライセンシング・インターナショナル、2023年度のライセンス業界のグローバルな売上概要を発表 - ライセンシングインターナショナルジャパン
一般的には、ブランドの知名度が高いブランドほどロイヤリティ料率も高くなる傾向があるため、影響力がライセンス料に関係することが分かります。ただし、キャラクターの人気度が高くても、契約条件を工夫すればライセンス料を抑えることが可能です。
人気キャラクターであることは、高額なライセンス料に直結しますが、使用範囲や期間、プロモーション方法を調整することでコストを削減できます。
上記の調査の通り、著作物の多くは「文章・言語」「音楽」「映像」が多くの割合を占めており、何らかのプロモーションのみと限定できるケースがほとんどではないでしょうか。
例えば、ハイブランドのバッグはフルセットで購入すると高価ですが、限定デザインや部分的な使用を選べばコストを抑えられるのと同じです。キャラクターも使用方法を絞れば費用が軽減できます。
| 1.媒体の限定:使用媒体(テレビCM、Web広告、店頭POP)を限定し、それ以外の利用を契約から外す 2.地域の限定:使用地域を国内または特定地域に限定して無駄なコストを抑制する 3.人気の限定:人気になりそうなニッチキャラを選んでコストを抑えつつ先行者利益を狙う 4.期間の限定:特定のキャンペーン期間やシーズンに限定して使用する |
参考:知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書 ~知的財産(資産)価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握~ - 経済産業省
参考:特許庁産業財産権制度問題調査研究について - 特許庁
(資料:特許の技術的価値の評価指標策定のための実施料率データベースの在り方に関する調査研究報告書)
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、さまざまなキャラクター(IP)とのコラボレーションを同時に行い、独自のエンターテインメント体験を提供しています。
USJは、米国ユニバーサル社からテーマパーク運営のライセンスを受けています。初期のキャラクターは、米国ユニバーサル社が各ライセンサーと契約し、USJにサブライセンスする形でした。近年では、USJが直接各ライセンサーと交渉し、契約を締結するケースが増えています。
特に、「ハリー・ポッター」の世界を再現したテーマエリアを導入し、来場者数と売上が飛躍的に増加したケースは有名です。映画ファンにとって物語の中に入り込めるような体験が、ブランド価値の向上に影響を与えたと言えるでしょう。
| ハリウッド映画:「ハリー・ポッター」「ジュラシック・パーク」など アニメ・マンガ:「鬼滅の刃」「進撃の巨人」「ワンピース」など ゲーム:「スーパー・ニンテンドー・ワールド」 キャラクター:ミニオン、セサミストリート、ハローキティなど 企業:日本マクドナルドとのコラボなど |
| 期間限定性:コラボは期間限定のものが多く、新鮮さを保つよう設計されている 没入型体験:VRやXR技術を活用したアトラクションなど、最新技術と組み合わせている 多角的展開:アトラクション、グッズ、フード、ホテルなどの形でコラボを展開している 地域性考慮:「ユニバーサル・クールジャパン」などの企画を実施して海外にも目を向けている |
| ターゲット拡大:映画ファン以外にも、ファミリー層や関西圏外、海外からの来場者を獲得できる 継続的な新規性:定期的なコラボ更新により、リピーター需要と新たな層へリーチできる ブランド価値向上:著名IPとのコラボにより、USJ自体のブランド価値を高められる |
ローソンは、アニメやゲームのライセンスを中心にコラボ商品を展開したり、独自のキャンペーンを展開して来店する理由を作っています。
ローソンは、各ライセンサーと直接契約を結んでコラボレーションを実施しています。期間限定の商品やキャンペーンとして、キャラクターやコンテンツとのコラボレーションを展開しています。
| アニメ・マンガ:「鬼滅の刃」「ドラゴンボール」「ポケモン」など ゲーム:「モンスターハンター」「学園アイドルマスター」など キャラクター:「リラックマ」「すみっコぐらし」など 映画・ドラマ:「スター・ウォーズ」「ハリー・ポッター」など |
| 期間限定性:基本的にはキャンペーン単位(期間限定)のコラボ実施となり新鮮さがある 商品開発:コラボ限定のオリジナル商品を開発・販売して独自性がある 多角的展開:商品、キャンペーン、店舗装飾などの形でコラボ方法が多彩 地域性考慮:一部の地域限定コラボも実施している |
| 集客力向上:人気キャラクターとのコラボで、新規顧客の獲得や来店頻度の向上につながる 商品差別化:オリジナルコラボ商品により、他社との差別化になる ブランドイメージ向上:人気コンテンツとのコラボにより、ブランドの好感度が上がる |
マクドナルドは、スタンダードな商品だけでなく、さまざまなライセンスで期間限定のコラボ商品などを展開することでリピーターを飽きさせないようにしています。
マクドナルドは、グローバル本社と各国法人が連携して、ライセンサーと契約を結んでいます。世界規模のコラボレーションと、各国独自のコラボレーションを展開しています。
| 映画:「ミニオンズ」「スパイダーマン」など アニメ・マンガ:「ドラゴンボール」「ポケモン」など キャラクター:「ハローキティ」「ディズニーキャラクター」など スポーツ:オリンピック、サッカーワールドカップなど |
| グローバル展開:世界規模でのコラボキャンペーンを実施している ハッピーセット:子供向けのおもちゃとのコラボを常時行って想起されやすい 限定メニュー:ロングセラー商品とコラボ限定メニュー開発・販売の使い分けをしている デジタル活用:アプリやARを活用したキャンペーンも展開している |
| ファミリー層の取り込み:子供向けコラボにより、ファミリー層の来店を促進できる ブランド価値向上:グローバルブランドとしてのイメージ強化を図れる 話題性創出:大規模なコラボキャンペーンにより、メディア露出や口コミを獲得できる |
関連記事:【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介
ここまでのポイントをまとめます。
キャラクターライセンスは、ブランド価値を高めるための強力なツールです。適切なキャラクターを選定し、契約条件を慎重に設計することで、消費者との感情的なつながりを深め、ビジネスの成長を後押しできます。これを実現するためには、市場動向の分析や契約条項の詳細な理解が不可欠です。
まずは、キャラクターに関する具体的なガイドブックを以下のダウンロードページでチェックしてみてください。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。
動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。
例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。
「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。
・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介
・キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説
・【顧客拡大】キャラクター活用のリブランディング戦略とは?失敗例も紹介
・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?
・海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説
・【企業向け】VTuberの始め方は?新規プロジェクトを成功させるポイントを紹介
・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る
・ブランドのファンを増やすオリジナルグッズ・ノベルティとは?具体的な効果や制作方法を紹介
・にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた
・なぜ企業同士のコラボ事業が注目されるのか?参考事例までPR会社が解説
・【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介
・【IPコラボ】学習教材×マンガが売れた秘密とは?活用事例・ポイントも紹介
・キャラクターライセンスとは?他社IPを活用してブランド価値を高める方法を紹介

NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。