NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。


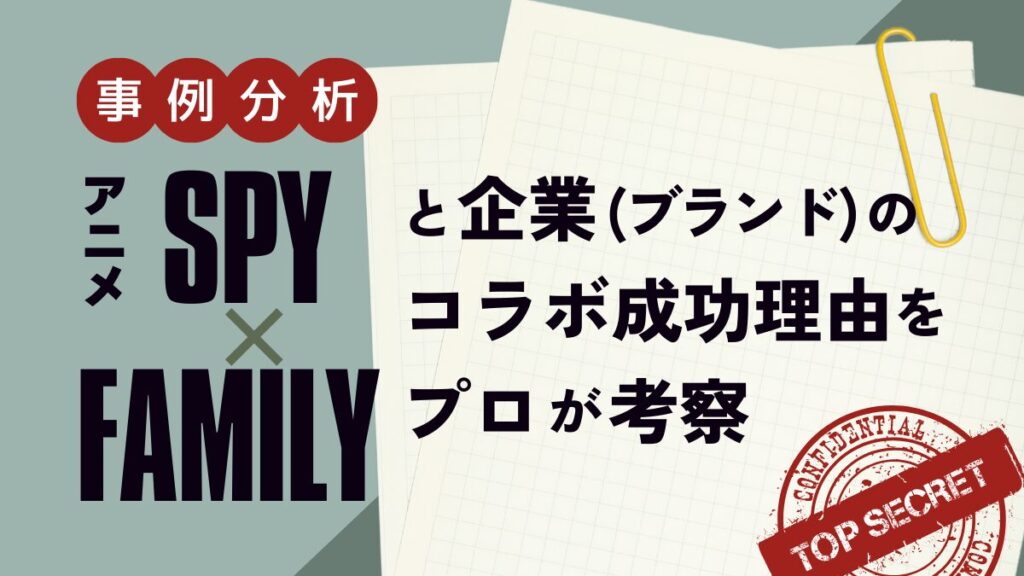
| 「このアニメとのコラボ、意味あるの?」 上司の冷たい一言が、胃の奥に突き刺さるようだった。企画会議の室内は静まり返り、誰もが自分に注がれる視線を感じている。パワーポイントのスライドには、『SPY×FAMILY』とのコラボ企画案が映し出されているが、誰も前向きな反応を示さない。 「アニメ?ファミリー向け?ターゲットが曖昧じゃないか?」 企画部長が腕を組みながら首をかしげる。これまで準備してきた市場分析、ターゲット戦略、SNSの拡散計画、どれも今、この場では無意味なものに思えてくる。自分の声は震えそうだったが、なんとか絞り出した。 「でも、ファンは絶対に興味を持ちます。他社のコラボ事例もあります…」 「有名作品と組めば売れるわけじゃない。で、本当にこの企画、やる意味があるのか?」 その瞬間、胸が押しつぶされそうになった。確かに、ただのコラボでは埋もれてしまうかもしれない。だが、ファンの心を掴む仕掛けがある。数字だけでは測れない熱量が、そこにはある。 「意味があるか、ないか…それを決めるのは、俺たちじゃない。ファンだ。」 |
これは先日、当社がプロモーションの相談を受けた地方の食品企業であった社内会議の様子です。
この話から分かるように、アニメ作品と企業のコラボは「有名作品だから売れるわけではない」ということです。商品やイベントなどと親和性を持たせた上で、人気を借りるという発想が大切になります。
そこで今回は、どのような点がコラボ成功のポイントになるのかを、アニメ「SPY×FAMILY」と企業のコラボ事例を分析しながら紹介していきます。
コラボ戦略については「キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る」もチェックしてみてください。
キャラクターを「自社に合う見栄えか?」だけで作っても、顧客から受け入れられないことがほとんどです。なぜなら、ユーザーは多くの情報に晒されており、自分が興味を持つものしか見ないからです。興味を持つことは、共感したり何らかの感情的な刺激が必要になります。そのためには、キャラクターの人格や設定などが重要だということです。魅力的なキャラクターを作る要素などの「キャラクター作りのポイント」を「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ活用してみてください。
コラボレーションする際に重要なのは、影響力と親和性です。アニメ「SPY×FAMILY」では、人気がある上に、各ブランドとマッチしやすいことがコラボされやすい理由だと考えられます。特に重要な要素は、以下の3つが挙げられます。

アニメ『SPY×FAMILY』がコラボレーションの対象として選ばれやすいのは、作品の高い人気は前提として、幅広く支持されるテーマ性も影響していると言えます。
本作は、スパイである父、殺し屋の母、そして超能力を持つ娘が偽装家族を演じるというユニークな設定で、家族愛や絆をテーマに描かれています。この普遍的なテーマは、多くの人々の共感を呼び、作品の人気を支えています。
実際、2022年に放送された『SPY×FAMILY』第1期は高い視聴率を記録し、老若男女問わず幅広い年齢層から支持を集めました。
登場キャラクターのアーニャは、その愛らしさで多くのファンの心を掴みました。このようなキャラクターの魅力が、作品全体の人気をさらに高めています。
企業にとって、これほど多様な層に支持される作品とのコラボレーションは、自社商品の認知度向上や新たな顧客層の獲得に大いに役立ちます。具体的には、商品の売上向上だけでなく、ブランドイメージの刷新や強化にも影響を与えます。
作品の持つ「家族」「秘密」「スパイ」といったテーマは、多様な業界との親和性を持ち、さまざまな商品やサービスとの組み合わせが可能です。この柔軟性も、企業がコラボレーションを検討しやすい要因となっています。
これらの要素が相まって、企業とのコラボレーションが成功しやすい環境を作り出しています。
参考:なぜ、『SPY×FAMILY』には起用希望が殺到するのか? 『販促会議』2月号(12月28日)発売 - PR Times
アニメ『SPY×FAMILY』とサントリー「BOSS」のコラボレーションは、ファミリー層に強く訴求する企画として話題を呼びました。特に、父の日をテーマにしたマーケティング戦略が、消費者の感情に訴えかける形で成功を収めています。さっそく、その成功の背景を分析します。
このキャンペーンが効果的だった要因の一つは、ターゲット層と商品のコンセプトが見事に一致していた点にあります。
単なる人気キャラクターの起用ではなく「BOSS」というブランドイメージと、『SPY×FAMILY』の“偽装家族”の父・ロイドのキャラクター性が絶妙にリンクしていました。コーヒーという商材も、日常的に親しまれ、家庭の中での“ひと息つく”シーンと親和性が高かったのです。
このコラボによって「仕事に向かう父が、リビングで家族と過ごすわずかな時間」と商品がリンクし、父親たちは“家族と過ごすひととき”を想起して自然とキャンペーンに共感を抱く構造が作られていました。
このコラボは、“家族”というストーリーを軸にしていた点がポイントです。
多くの企業がアニメとコラボする際は、人気キャラを採用するだけで終わってしまうケースが多いものですが、このキャンペーンでは、キャラクターの個性だけでなく“家族愛”という感情を引き出す演出が施されていました。
広告や販促キャンペーンでも、まるで「映画のワンシーン」のように、働く父がコーヒーを手にとりながら家族を想うシーンを連想させ、“日常の中の小さな幸せ”を感じられるメッセージが散りばめられていました。
| 1.キャラクターの背景とブランドストーリーを一致させる ※例:「BOSS」は“働く大人のためのコーヒー”というブランドイメージと、ロイド・フォージャーの“表向きは精神科医、裏の顔はスパイ”というキャラクター設定を結びつけた 2.購入者が自身のライフスタイルと重ねられる仕掛けを作る ※例:「父の日」のテーマに沿って「家族の絆」を感じられるストーリーを演出 3.限定アイテムやプレゼント企画を活用する ※例:限定パッケージやプレゼントで、キャンペーン自体が話題となるような仕掛けを作った |
このコラボキャンペーンは、単にアニメファンをターゲットにしたものではなく“家族”という多くの人が共感できるテーマとブランドをマッチさせることで、より幅広い層への訴求に成功しました。
今後、企業とアニメ作品のコラボは、キャラクターの知名度だけに頼るのではなく、「ブランドストーリーとキャラクターの物語が自然に交差するポイント」を見極めることが重要になっていくでしょう。
参考:「割るだけ ボスカフェ」が『SPY×FAMILY』とコラボ! - サントリー食品インターナショナル株式会社
参考:「サントリー」と『SPY×FAMILY』のコラボレーション開催決定! - SPY×FAMILY
参考:「BOSS」と『SPY×FAMILY』が“ちちの日”コラボ!“アーニャ”が大好きなピーナッツフレーバーの「ボス とろけるカフェオレ 幸せ香るピーナッツ」新発売 - PR Times
アニメ『SPY×FAMILY』とロッテ「ガーナチョコレート」の母の日キャンペーンは、ファン層だけでなく幅広い層にリーチし、大きな成功を収めました。本記事では、キャラクターのイメージと商品コンセプトが一致したことで生まれた相乗効果について、マーケティングの観点から分析します。
ロッテのガーナチョコレートは、「お母さんが家族のために一生懸命なのはこれまでも、これからも変わりません。」と担当者が語ったように、「母の日=ガーナ」という強いブランドイメージを持っています。『SPY×FAMILY』もまた、擬似家族ながらも“家族の絆”をテーマにした作品であり、これらが掛け合わさることで自然な形でのコラボレーションが実現しました。
サントリーの事例と同様、単なるアニメキャラとのコラボではなく「母の日に贈るチョコ」という商品特性と、作品内の“母”であるヨル・フォージャーのキャラクター性が見事にリンクしていた点が良いコラボレーションを生み出した一因でしょう。
ヨルは表向きは優しい母親、裏では凄腕の殺し屋という二面性を持つキャラクターですが、家族のために全力を尽くす姿が視聴者の共感を集めています。この設定が、「母親に感謝の気持ちを伝える」というガーナチョコのブランドメッセージと強く結びついたのではないでしょうか。
ヨルが作中で、家族のために料理を振る舞おうとするように、消費者も「母に何かを贈りたい」という感情を自然に引き出せるキャンペーンでした。
このコラボでも前述と同様、消費者に「購入しないと後悔するかもしれない」と思わせる心理戦略が巧みに設計されていました。
このキャンペーンでは「母の日」というイベント性と、キャラクターのストーリーを組み合わせることで、消費者の感情に深く訴えかける仕掛けが施されていました。
母の日にガーナチョコを渡すことで、「自分もロイドのように家族を大切にする存在でありたい」と思えるストーリーが生まれました。
関連記事:コミュニティメンバーが参加したくなるイベント企画のコツは?具体的なステップを公開
| 1.キャラクターの持つストーリーと商品メッセージを一致させる ※例:ヨルの「家族を思う気持ち」を、ガーナの「母の日に贈るチョコ」と結びつける 2.消費者が“贈るシーン”を想起できる演出を施す ※例:パッケージデザインには、母の日の贈り物として使いたくなる特別なビジュアルを採用 3.親子のコミュニケーションを促す仕掛けを作る ※例:SNSを活用し「母の日にチョコを贈るエピソード」を投稿できる場を提供する |
このキャンペーンの最大のポイントは、「消費者自身の体験と結びつく要素を持たせたこと」です。
アニメコラボは基本的に「アニメや原作ファン」に向けた影響力を得るために活用されがちですが、このキャンペーンは「母の日」という関連性のあるイベントとリンクさせることで、アニメファン以外の層にも自然にリーチできる設計となっていました。
「チョコを贈る」というシンプルな行為が、「家族の関係を深めるきっかけ」になるという考え方は、ヨルが家族のために料理を作って関係を深める姿と重なり、消費者が自分自身の生活に置き換えて考えやすくなる効果を生んだのではないでしょうか。
参考:【『ガーナ』と『SPY×FAMILY』が初タイアップ】ヨルがアーニャにぎゅっとハグ!描き下ろし「母の日」ビジュアル全5種を公開 - PR Times
パイン株式会社は、アニメ『SPY×FAMILY』の人気キャラクターのアーニャを活用した「アーニャアメ」を発売し、話題を集めました。
食品業界のアニメコラボは数多くありますが、パインの「アーニャアメ」は、ターゲット層ととてもマッチするコラボと言えるでしょう。
「アーニャアメ」は、アーニャの髪色をイメージしたピンク色のキャンディで、甘酸っぱいフルーツミックス味が特徴です。こうしたキャラクターの個性を活かした味とデザインを採用したことで、ファンにとって「思わず買いたくなる」欲求を刺激していました。
具体的には、キャラクターのイメージする限定の味を作ったことで、アーニャをきっかけにパイン飴を好きになってもらう流れが作れたのではないでしょうか。
さらに、2023年10月には「アーニャアメ2」としてパッケージデザインを一新して再発売され、新たな描き下ろしイラストなどでリピーターや新規顧客の興味を引く工夫が施されています。
このコラボ商品は、全国の各店舗での販売チャネルに加えて、キャラクターの魅力とSNS拡散を活用し、ファン層以外にも認知を広げました。
「アーニャアメ」は通常の可愛いパッケージと、変顔で面白さのあるパッケージで、ファン以外にもSNSで自然に拡散してもらえる仕掛けになっています。実際、パッケージの可愛らしさや限定デザインが注目を集め、多くのユーザーが投稿やレビューを行いました。
シークレットパッケージとなる「アーニャの変顔パッケージ」は、まるで“ガチャ”のような感覚で、見つけたらシェアしたくなる気持ちが刺激されます。
関連記事:Twitterのキャラクターアカウントって効果あるの?メリットや運用テクニックを紹介
| 1.キャラクターの好物を商品化し、ストーリー性を加える ※例:作品の設定とリンクした味を採用し、ファンの「共感」を引き出す 2.SNS映えを意識したデザインで拡散を促進 ※例:パッケージにはアーニャの表情を採用し、写真を撮って投稿したくなる仕掛けを作る 3.購入体験に“遊び”の要素を取り入れる ※例:ランダム要素のあるパッケージデザインで、何度も買いたくなる仕掛けを作る 4.ファン層以外にも刺さる設計 ※例:「アーニャの表情」を前面に押し出し、ライト層にも興味を持たせる |
「キャラクターと一緒に楽しむ」ような感覚を与える商品設計は、ファンの購買意欲をより強く刺激します。今後のアニメ作品とのコラボでは、「キャラクターの魅力をどこまで商品に反映できるか」が成功のカギを握るでしょう。
この事例を参考に、単なるキャラグッズではなく、「ファンがキャラクターとのつながりを感じられる体験」まで計画していきましょう。
参考:“パインアメ” が TVアニメ『SPY×FAMILY』 とコラボ! 「アーニャアメ2」発売 昨年大好評だったアーニャアメのパッケージがバージョンアップ - パイン株式会社
アニメ『SPY×FAMILY』と日清食品の「どん兵衛」「U.F.O.」のコラボは、描き下ろしパッケージとユーモラスな販促動画を活用し、大きな話題を呼びました。
日清食品のカップ麺ブランドは、これまでも独自性のある広告戦略で知られています。『SPY×FAMILY』とのコラボでも、作品の世界観やキャラの魅力を活かしたパッケージでプロモーションが実施されました。
本キャンペーンでは、アーニャというキャラクターの持つシュールさと愛らしさを取り入れ、まるで「スパイミッションのように、手軽においしい食事を完成させる」感覚を演出しています。
| ・どん兵衛の「和風だしの温かみ」が、フォージャー家の家族愛とリンク ・U.F.O.の「ワイルドな焼そば」のイメージが、アーニャの自由奔放さとマッチ |
日清食品は『SPY×FAMILY』のキャラクターを商品体験に融合させ、アニメのファン層と既存のカップ麺ユーザーの両方にリーチしました。「日常の中に潜むスパイの世界観」を再現した、ブランディングとエンタメが融合した好例といえます。
このコラボのもう一つの強みは、SNSでのシェアを狙った戦略的な展開でした。キャンペーンをSNSで公開するだけでは、シェアされるケースは多くありません。一方で、本キャンペーンでは、消費者が「思わずシェアしたくなる」要素が組み込まれていました。
特に、パッケージデザインや限定グッズはシェアされやすい仕掛けと言えるでしょう。まるでアーニャが“どん兵衛”を諜報活動の報酬にしているようなパッケージデザインがファンの笑いを誘い、SNS上での拡散が加速する作りになっていました。
限定グッズの活用によって、購入理由を作っている点も参考になるポイントです。
関連記事:【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介
| 1.ハッシュタグキャンペーンで参加型企画を実施 ※例:「#スパイ家族どん兵衛」などのタグを設定し、ファンが投稿しやすい環境を作る 2.販促動画に“ネタ要素”を加え、自然な拡散を促す ※例:キャラの表情や名セリフを活かした「つい友達にシェアしたくなる」構成 3.インフルエンサーやVTuberとのコラボで認知度UP ※例:顧客にリーチしやすいYouTuberやVTuberと連携し、実際に商品を試すレビュー動画を展開 4.限定パッケージや特典で購買欲を刺激 ※例:アニメファンが「コレクションしたくなる」ような描き下ろしイラストを使用 |
このコラボで注目したいポイントは、「食卓をエンタメ化する」というマーケティングの方向性です。
食品ブランドのコラボは、ファン向けグッズ的な要素が強くなりがちですが、日清食品は「誰でも楽しめるキャラの可愛らしさを出した広告」と「思わず手にとってしまうパッケージデザイン」によって、ファン以外にも受け入れられる状態を作っています。
今後のアニメコラボは、より“日常に溶け込む”形や“面白さ”を重視した展開が重要になっていくのかもしれません。
参考:「SPY×FAMILY」限定パッケージ3品 (10月2日発売) - 日清食品
参考:おいしさ、わくわくっ!「日清のどん兵衛・日清焼そばU.F.O.」の「SPY×FAMILY」限定パッケージ商品が10月2日(月)に新発売! - SPY×FAMILY
参考:「日清のどん兵衛」「日清焼そばU.F.O.」とTVアニメ『SPY×FAMILY』がコラボ決定! - SPY×FAMILY
アニメ『SPY×FAMILY』とユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のコラボレーションイベント「シークレット・ミッション」は、体験型アトラクションとして話題を集め、多くの来場者を魅了しました。本記事では、なぜこのコラボが成功したのか、その仕掛けとマーケティングの視点から分析します。
USJは過去にもさまざまなアニメ作品とコラボしてきましたが、『SPY×FAMILY』の世界観を生かした「シークレット・ミッション」は、他のコラボとは一線を画すユニークな設計になっていました。
アニメのコラボイベントは、一般的に「キャラクターのグリーティング」や「限定グッズ販売」が中心ですが、USJの「シークレット・ミッション」は、それだけでは終わりませんでした。このイベントでは、来場者自身がスパイとなり、フォージャー家と共にミッションを遂行するという「体験型アトラクション」の要素を全面に押し出したのです。
これはまるで、映画『ミッション・インポッシブル』の世界に入り込んだかのような体験で、参加者は特定のミッションを受け取り、USJのパーク内を移動しながらスパイ活動を体験できる仕組みになっていました。
関連記事:【PR事例】ゲーム・アニメをリアルに体験できるイベントとは?おすすめの成功事例を紹介
このコラボイベントの最大のポイントは、「ただのアトラクション」ではなく、来場者が『SPY×FAMILY』のキャラクターの一員として活躍できる「ストーリー体験型アトラクション」であった点です。
多くのアニメコラボは「原作の再現」にとどまりがちですが、USJは「来場者が作品の世界観に入り込める設計」を採用することで、より没入感のある体験を生み出しました。これは、「映画の観客」から「映画の登場人物」に変わるような体験となるため、まるで自分もアニメのキャラになったかのような気持ちを味わえるはずです。
今後、アニメとテーマパークのコラボレーションは、より「参加型」「没入型」へとシフトしていくでしょう。「現実世界とフィクションの境界が曖昧になるような」仕組みを作ることで、来場者は単なるファンではなく、「物語の一員」へと変わるのです。
| 1.「観る」から「参加する」へシフトする・映像や展示だけでなく、ゲスト自身がストーリーに関与する形にする2.リピート来場を促す仕掛けを組み込む・ミッションの内容を定期的に変更し、「何度も遊びたくなる」設計を実施3.キャラクターと直接関われる仕掛けを導入する・たとえば、ミッション成功後に「アーニャからの特別メッセージ」が届くなどの演出を追加 |
「シークレット・ミッション」の成功は、単なるキャラクターコラボではなく、「ファンが自ら作品の一部になる体験」を提供した点にあります。これからのアニメ×エンターテイメントの融合は、より「消費者の参加」を重視した体験型コンテンツへと進化していくでしょう。
参考:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと期間限定でコラボレーション決定! - SPY×FAMILY
これらの成功事例から、アニメの世界観とブランドの親和性を高めることが、コラボレーションの成功に直結することがわかります。
具体的には、商品のコンセプトやターゲット層とアニメのテーマやキャラクター性を一致させることで、消費者の共感を得やすくなります。
筆者の見解としては、以下の要素がポイントになると考えました。
| ・作品の人気度が一定数あり影響力を持つこと ※例:シーズン3期の放送決定や劇場版など影響力がある ・ブランドと作品のテーマがマッチすること ※例:家族の絆と日常生活で楽しむお菓子 ・商品と作品やキャラの親和性があること ※例:ピーナッツ味という形で親和性も考える |
ですが、もっとも重要になるのはブランドや商品とマッチしていることでしょう。
また、限定デザインや特別な体験を提供することで、ファン層の購買意欲を刺激し、話題性を生み出すことが可能です。
このように、アニメの世界観を活かし、ブランドとの親和性を高める戦略は、企業のマーケティング活動において非常に有効であると言えます。今後もこの手法を活用したコラボレーションが増えることが期待されます。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。
動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。
例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。
「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。
・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介
・キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説
・【顧客拡大】キャラクター活用のリブランディング戦略とは?失敗例も紹介
・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?
・海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説
・【企業向け】VTuberの始め方は?新規プロジェクトを成功させるポイントを紹介
・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る
・ブランドのファンを増やすオリジナルグッズ・ノベルティとは?具体的な効果や制作方法を紹介
・にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた
・なぜ企業同士のコラボ事業が注目されるのか?参考事例までPR会社が解説
・【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介
・【IPコラボ】学習教材×マンガが売れた秘密とは?活用事例・ポイントも紹介
・キャラクターライセンスとは?他社IPを活用してブランド価値を高める方法を紹介

NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。