NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。


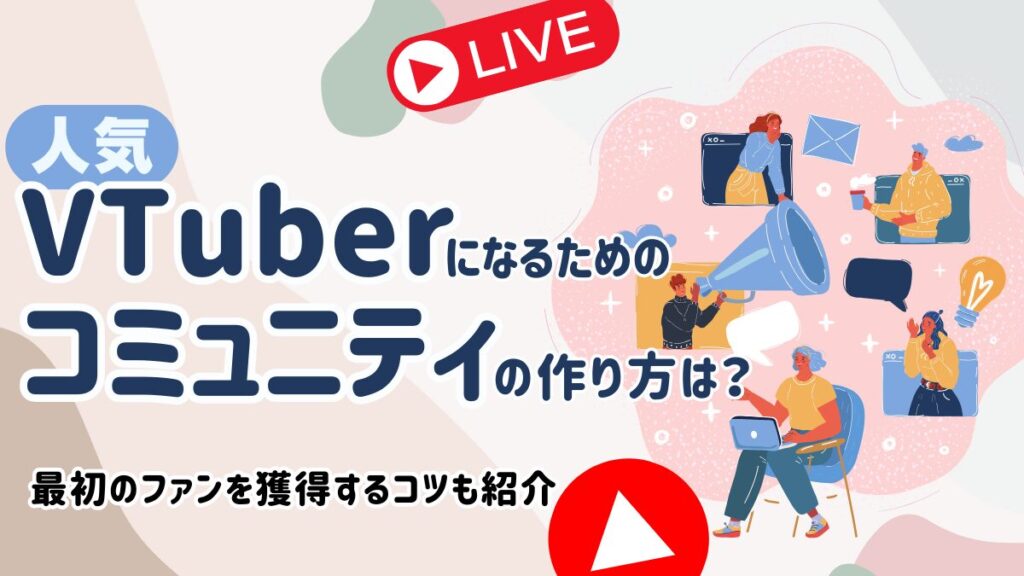
VTuberとして成功するためには、視聴者との絆を築く「コミュニティ作り」が欠かせません。しかし、多くの初心者が「どうやってファンを作ればいいのか分からない」と悩む声も少なくありません。
SNSに投稿しても反応が薄い、初配信で視聴者が集まらない…そうした状況に心が折れてしまう人もいるでしょう。ですが、本当に大切なのは「数」ではなく、熱心に応援してくれる「質の高いファン」を集めることなのです。
最初から多くの人に注目される必要はありません。小さなコミュニティをターゲットにして、視聴者との距離感を大切にしながら絆を深めることで、長く愛されるVTuberになれます。
そこで今回は、初心者VTuberがコミュニティ作りで直面する3つの壁とその対策や、視聴者との関係を強化する方法をわかりやすく解説します。ぜひ続きを読んで、次に取るべき一歩を見つけてください。
X(Twitter)コミュニティの作り方は「X(Twitter)コミュニティの効果的な使い方は?作る手順や実際の事例も紹介」をチェックしてみてください。
キャラクターを「自社に合う見栄えか?」だけで作っても、顧客から受け入れられないことがほとんどです。なぜなら、ユーザーは多くの情報に晒されており、自分が興味を持つものしか見ないからです。興味を持つことは、共感したり何らかの感情的な刺激が必要になります。そのためには、キャラクターの人格や設定などが重要だということです。魅力的なキャラクターを作る要素などの「キャラクター作りのポイント」を「無料資料ダウンロードページ」で公開中です。ぜひ活用してみてください。
| <記事のポイント> ・コミュニティ作りの際にぶつかる問題が分かる ・コミュニティ作りの基本的な考え方が分かる ・コミュニティ作りの戦略やアイデアが分かる ・コミュニティ作りで起こりがちな炎上リスク回避の方法が分かる |
VTuberはただ配信を始めるだけではファンを増やすことは難しく、多くの人が次のような問題に直面しています。
「頻繁に投稿しても、思ったほど視聴者が増えず、何が間違っているのか分からない。」と、どうすべきか迷う時が来るかもしれません。
頻繁に配信や投稿をしても思ったように視聴者が増えないのは、コンテンツがターゲット層に響いていない可能性が高いからです。解決するためには、誰に向けて発信しているのかを明確にし、その層が求める内容に合わせた投稿やハッシュタグの工夫が必要です。
「自分のキャラクターに合ったターゲット層が掴めず、コンテンツの軸がぶれてしまう。」と、テーマやコンテンツの方向性に悩む時が来るかもしれません。
方向性が定まらないと、ファンが何を期待すればよいか分からず、結果として興味を失ってしまいます。自分のVTuberとしてのキャラクターやストーリーを深掘りし、それに共感する層をターゲットにしたテーマを掲げることで、継続的な関心を得られます。
「配信やSNSでの些細な発言が批判を受け、コミュニティに悪影響を及ぼすかもしれない。」という不安に感じる時が来るかもしれません。
些細な発言が大きな問題として拡散されるのは、視聴者との距離感や誤解が原因です。このリスクを軽減するには、常に配信や投稿内容を慎重にチェックし、自分の発言に一貫性を持たせることが重要です。また、万が一批判を受けた場合でも、誠実な対応で信頼を回復する方法を学んでおきましょう。
これらの課題は、特に配信を始めたばかりのVTuberにとって大きな壁となります。せっかく頑張って作ったコンテンツが注目を集めないことで、やる気を失うことも少なくありません。
多くのVTuberが「初配信でできるだけ多くの視聴者を集める」ことに集中しがちですが、最初は熱狂度を重視するべきです。
視聴者数を短期間で増やそうとするアプローチには次のようなリスクがあります。
数だけを追い求めると、一時的に増えたフォロワーが実際にはVTuberやコンテンツに興味を持っていない可能性が高くなります。
その結果、最初はたくさん集まったフォロワーが段々と配信に参加しなくなり、やがて離れていきます。
初期段階で広告費やキャンペーンを投入して視聴者数を稼ぐ方法は「認知」してもらうためのコスト割合が増えるため、掛けた予算の割には効果を実感しづらくなります。
余程の資金と人員の余裕があるプロジェクト、または強力なコンテンツが揃っている場合を除き、着実に目の前のファンとの関係構築に力を注ぐことが大切です。
無理に幅広い層を狙うと、VTuberとしてのキャラクター性やメッセージがぼやけ、結果的に誰の心にも響かない存在になってしまう可能性があります。
だからこそ最初の段階は「数ではなく絆を重視する」進め方が必要です。初期段階では、小規模な熱心なファン層を形成し、その中でVTuberとしてのキャラクターを確立することが重要です。
つまり、最初の一歩は「大きな目標ではなく、近くのファンとの深い関係を築くこと」から始めるべきなのです。
前述の通り、最初の段階は「視聴者の数ではなく絆を作ることを重視する」ことで、熱心なファン層を形成していくことが長期的なプロジェクトにする上で欠かせません。さらに、小規模な熱心なファンコミュニティは、SNS上での口コミ拡散も積極的に行ってくれます。
例えば、にじさんじやホロライブでは、ファンとの深い交流を重視し、配信中にチャットを読む、一緒にゲームをプレイするなどの工夫を取り入れています。
この「ファンとの距離感を縮める」戦略によって、グッズやコラボ商品の販売で売上を確保しています。
| ・ファンの「帰属意識」が高まり、VTuberの成功を自分のことのように喜んでくれる ・応援する意欲が高まり、配信の視聴率やグッズ購入率が上がる ・VTuberが「特別な存在」になることで、競合との差別化が図れる |
単なる視聴者数の増加を目指すのではなく、視聴者との絆を深めて口コミを増やし(話題になり)、自然と新しいファンが増えるようにしていきましょう。
関連記事:にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた
初心者VTuberにとって、最初の数人のファンを見つけることは最大の課題です。まずは扱うテーマを特化させて、共感を持つ最初の視聴者を見つけやすくしましょう。
例えば、ゲーム実況をする場合、特定のゲームコミュニティ(フォーラムやSNSのハッシュタグ)をターゲットにして配信を開始します。
また、初期のファンが配信内容やキャラクターの魅力をSNSでシェアすることで、徐々にファンの輪が広がります。
1.配信テーマを趣味や関心のある分野に特化させる(例:レトロゲーム、料理、特定のアニメ解説など)。
2.関連するSNSコミュニティに参加し、コメントや投稿を通じて存在をアピールする。
3.初期のファンを大切にし、彼らのリクエストやフィードバックを積極的に取り入れる。
SNSはVTuberがファンとつながるための強力なツールです。しかし、ただ告知や宣伝をするだけではエンゲージメントが生まれにくく、フォロワーを定着させるのは難しいのです。
例えば、Twitterで「次回の配信内容を選んでください!」といったアンケートを実施したり、Instagramで「今日の配信ハイライト」を投稿して、視聴者の意見を反映する工夫をします。
また、配信中のスクリーンショットや短いクリップをSNSに投稿することで、新しい視聴者にもアピールできます。
| 1.SNSで関連ハッシュタグを使いながら配信予告やコンテンツのハイライトを投稿する 2.フォロワーに向けたアンケートや質問投稿を行い、双方向のコミュニケーションを促進する 3.配信後の感想や視聴者コメントをSNSでシェアして、ファンへの感謝を伝える |
ファンアートやコメントは、ファンとの絆を深める重要な仕掛けとなります。しかし、視聴者が行動を起こすには「自分の貢献が評価される」と感じられる仕掛けが必要です。
配信中に「お気に入りのファンアートを次回の配信で紹介します」と告知することで、視聴者のモチベーションを高めます。
また、SNSで特定のハッシュタグ(例:#〇〇推し)を設定し、投稿内容をVTuber側で定期的に取り上げることでファンの行動を促すことも良いでしょう。
| 1.ファンアートやコメントを募集するキャンペーンを定期的に開催する 2.視聴者からのクリエイティブな投稿を配信やSNSで紹介し、感謝の言葉を添える 3.配信内で「コメント大賞」や「アート大賞」を設け、視聴者が参加しやすい仕組みを作る |
小さな行動を積み重ねてファンベースを作り、コミュニティとともに成長するVTuberを目指しましょう。
さらに、以下の文献によれば、視聴者がVTuberに対して一方的に親近感やつながりを感じる「パラソーシャル関係」が、視聴動機として重要な役割を果たしており、VTuberの個性、コンテンツの質、アバターデザインが視聴者の関心を引くカギとなることが示されています。
これらの要素を追求して、新規参入しても魅力を感じてもらえるようにしていきましょう。
参考:Li, Yijin. "Why does Gen Z watch virtual streaming VTube anime videos with avatars on Twitch?" Online Media and Global Communication, vol. 2, no. 3, 2023, pp. 379-403. doi: 10.1515/omgc-2023-0030
多くのVTuberが「初配信で多くの視聴者を集めなければならない」と考えがちですが、実際には、初期段階で無理に拡大しようとするとエンゲージメント(反応)が悪くなります。代わりに、小さなコミュニティに焦点を当て、そこから「共感」を育てる方法が有効です。
| ・10〜50人規模の特定のテーマに特化した層をターゲットにした内容を発信する ・そのグループのニーズを深掘りし、専用の企画やコラボを通じて彼らの「推し」になる ・熱心なファンが口コミで広めることで、徐々に大きな輪を形成する |
まずはコアな少数のファンを大切にして、土台作りをしていきましょう。
公式感やブランド力を出しすぎると、VTuberとしての「距離感」が出やすくなり親しみやすさを失います。
逆に、初期のプロモーションであえて「アンダーグラウンド感」を演出し、ファンに「自分たちが発掘した」と感じさせる方法もあります。
| ・配信スタート時はSNSの投稿を少しカジュアルにして「まだ発展途上のVTuber」という印象を与える ・ファンにキャラ設定やストーリーの一部を投票してもらい「自分たちが育てている感覚」を持たせる ・スタッフや舞台裏をあえて公開して距離感を縮める工夫をする |
アイドルに近い存在の売り方は、人気になる前だからこそ支えたいという層も存在します。知名度がないからこその強みを活かしましょう。
新しいVTuberがゼロからファンを集めるのは非常に難しく、誰もが「既に人気のあるVTuber」を見がちです。そのため、初期のファンを「単なる視聴者」ではなく「共犯者」や「仲間」として巻き込み、コミュニティの中核に据えてみましょう。
こうして、ファンが「自分たちがこのVTuberを育てた」と感じられる環境を作っていく流れです。
| ・小規模なディスコードやSNSグループを作成し、限定コンテンツや意見交換の場を提供する ・配信で「このコミュニティはみんなで作っていくもの」と明確に語りかける ・企画段階でファンからの提案を受け入れるコーナーを作り、実際に採用する |
VTuberを応援していても、ファン同士が交流するきっかけが少ないという状況がよくあります。そこで、ファンがコメントや活動をすることでポイントが貯まり、そのポイントに応じて特典や称号が得られる「ゲーミフィケーション要素」を導入してみましょう。
| ・コメント回数や配信への参加で「エンゲージメントポイント」を付与する ・ポイントランキング化し、上位者にはVTuberとの特別イベントへの招待や特製グッズをプレゼントする ・ファン同士で協力してミッションをクリアするチームイベントを開催する |
コミュニティが一方通行の状態では、次第にファンは関心を失いやすくなります。そのため、ファンが主体的に動きやすいよう、ファン主催のイベントやコンテンツを公式がサポートしてみましょう。
| ・ファンが主催するアートコンテストやリアルイベントを公式で告知する ・特定の条件を満たすファンイベントには、公式のリソース(VTuberの録音メッセージなど)を提供する ・二次創作を促進するためのガイドラインを作り、自由度を保証する |
ファンコミュニティの中で、「推し活を頑張るファン」自体をVTuberの物語の一部に取り込む共創企画も良いでしょう。
ブランドは熱狂的なファンが主体的に活動することで成長が加速します。コミュニティがVTuber中心に一方的なまま完結してしまい、ファン同士の絆が弱くならないよう巻き込んでいきましょう。
| ・何らかのランキング上位者に専用ストーリーで特別な役割を与える(例:VTuberの冒険仲間として登場) ・ファンがVTuberの物語に影響を与えられる選択肢を提示する ・「みんなで作る物語」配信を開催し、ファンの投票で次回の配信内容が決定する仕組みを作る |
炎上はコミュニティの分裂や衰退を招きますが、リスクなしで活動するのは不可能です。SNS上で「ポジティブなミーム」を広め、コミュニティ内での炎上リスクを回避しつつ、盛り上がりを演出しましょう。
| ・ファン同士で共有できる「VTuber専用のミーム」を用意し、配信中に使う ・コメントやチャットで「ありがとう」や「応援」の言葉が溢れる仕掛けを作る ・配信でネガティブな話題を扱う際は、あえて明るいミームやジョークで流れを切り替える |
活動休止はファン離れや関心の低下を招きやすいため、VTuberが活動を一時的に休止する際は「期待を高める時間」として上手く活用しましょう。
| ・休止期間中、ファンに限定コンテンツを公開する(例:未公開エピソードやメッセージ) ・「復帰記念プロジェクト」をファンと共に計画し、復帰後の大規模イベントを準備する ・休止理由を正直に共有し、ファンと共に「応援の時間」を作る |
これらのアイデアを活用して、コミュニティ作りを進めていきましょう。
炎上はVTuberにとって大きなリスクですが、炎上を恐れるあまりに消極的な行動を取るとコミュニティの活性化が難しくなります。適切なリスク管理と出すべき情報を隠さないコミュニケーションによって、健全なコミュニティ運営を実現することが可能です。
SNSでファンと交流する際、感情的なコメントやデリケートなテーマについて慎重に対応することが重要です。トラブルが発生した場合には早期に対応し、誤解を防ぐための説明を迅速に行います。ファンとの意見交換を促しながら、コミュニティのガイドラインを共有することも効果的です。
| 1.配信開始前に、デリケートなテーマや炎上リスクのあるトピックをリストアップして避ける 2.ファンとの間に透明性を保つため、SNSや配信中でコミュニティのルールやポリシーを明示する 3.万が一トラブルが発生した場合には、謝罪や説明を迅速かつ明確に行い、信頼を失わないように対応する |
コミュニティの成長において、VTuberがすべてを担うのは非効率です。熱心なファンをコミュニティリーダーとして育成し、運営をサポートしてもらうことで、VTuber自身はコンテンツ制作に集中できるようになります。
ディスコードサーバーやファンコミュニティ内で、定期的に「ファンミーティング」を開催し、コアファンに特別な役割(例:モデレーター、イベント企画担当)を任命するのも良いでしょう。
また、コミュニティでの貢献を表彰することで、他のファンにも積極的な行動を促しましょう。
| 1.コミュニティ内で積極的にコメントをしたり、サポートをしてくれるファンをリストアップする 2.そのファンに対して特別な役割(例:モデレーター、アンバサダー)を依頼し、信頼関係を築く 3.ファンリーダーが円滑に活動できるよう、定期的にフィードバックや感謝の気持ちを伝える場を設ける |
競合VTuberが増加する中で、視聴者が複数の選択肢を持つことは一般的です。他のVTuberと同じようなコンテンツを提供するだけでは埋もれてしまい、ファンの心を掴むことは困難です。独自性を前面に出し、視聴者が「このVTuberだからこそ」と感じられるポイントを明確にすることが重要です。
たとえば、特定の趣味やトピック(例:ミニマルライフ、レトロゲーム、ボードゲーム)をテーマにすることでも差別化は可能です。配信中に視聴者のコメントやリクエストを取り入れ、双方向のやり取りを重視することで、親しみやすさと独自性を演出できます。
| 1.自分の得意分野や好きなテーマをリスト化し、配信テーマを絞り込む 2.他のVTuberをリサーチし、彼らが取り上げていないユニークな切り口を見つける 3.視聴者のリクエストやリアクションを積極的に取り入れ、「ここでしか見られない体験」を提供する |
VTuberが長く愛されるためには、他にはない独自のコミュニティ文化を作って独自性を出すことも良いでしょう。
ただの視聴者とVTuberの関係ではなく、特別な「仲間意識」や「価値観の共有」を持つファンコミュニティを形成することで、ファンとの絆を深めることができます。その文化がコミュニティの中核となり、新規ファンの定着や既存ファンの忠誠心を高めます。
例えば、「リスナーが宇宙船の乗組員」という設定を作り、ファンがそれぞれ自分の役割を持つように設計しました。
このような独自の設定やキャッチフレーズを用いることで、ファンがVTuberの世界観に没入しやすくなります。さらに、特定の挨拶やスローガン、内部用語(例:「〇〇族」「△△クルー」など)を作ると、ファン同士の結束が強まります。
VTuberのキャラクター設定やストーリーに基づき、ファンが参加できる世界観を明確に作る。
例:ファンタジーの国、ゲーム内のギルドなど
ファンが配信開始時やコメントで使えるお決まりの挨拶を設定する。
例:「○○団、出発!」など
アクティブなファンに、リーダーやイベント企画者などの役割を与え、彼らが中心となってコミュニティを運営できる仕組みを作る。
例:コミュニティリーダーなど
コミュニティ内での振る舞いや価値観を共有できるよう、他のコミュニティでは見られない独自のルールを明示する。
例:「ポジティブなコメントを必ず入れる」「楽しんで参加する」など
独自の世界観やスローガンを活用したオンラインイベントや、ファン同士の対話を促進する活動を企画する。
例:特定のミッションをクリアするためのヒントを視聴者が提供するなど
独自のコミュニティ文化を作ることは、VTuberが「他にはいない存在」になるためのポイントです。ファン同士の結束を強めて、新規ファンも魅力的なコミュニティに引き込んでいきましょう。
ここまでのポイントをまとめます。
VTuberが人気になるためには、知名度を追う前に「絆」を深めることが最も重要です。最初の小さなコミュニティからスタートし、視聴者の共感や参加を通じて徐々に成長することを意識して、長期的な成功を支える土台を作りましょう。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。
動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。
例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。
「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。
・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介
・キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説
・【顧客拡大】キャラクター活用のリブランディング戦略とは?失敗例も紹介
・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?
・海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説
・【企業向け】VTuberの始め方は?新規プロジェクトを成功させるポイントを紹介
・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る
・ブランドのファンを増やすオリジナルグッズ・ノベルティとは?具体的な効果や制作方法を紹介
・にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた
・なぜ企業同士のコラボ事業が注目されるのか?参考事例までPR会社が解説
・【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介
・【IPコラボ】学習教材×マンガが売れた秘密とは?活用事例・ポイントも紹介
・キャラクターライセンスとは?他社IPを活用してブランド価値を高める方法を紹介

NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。