NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。


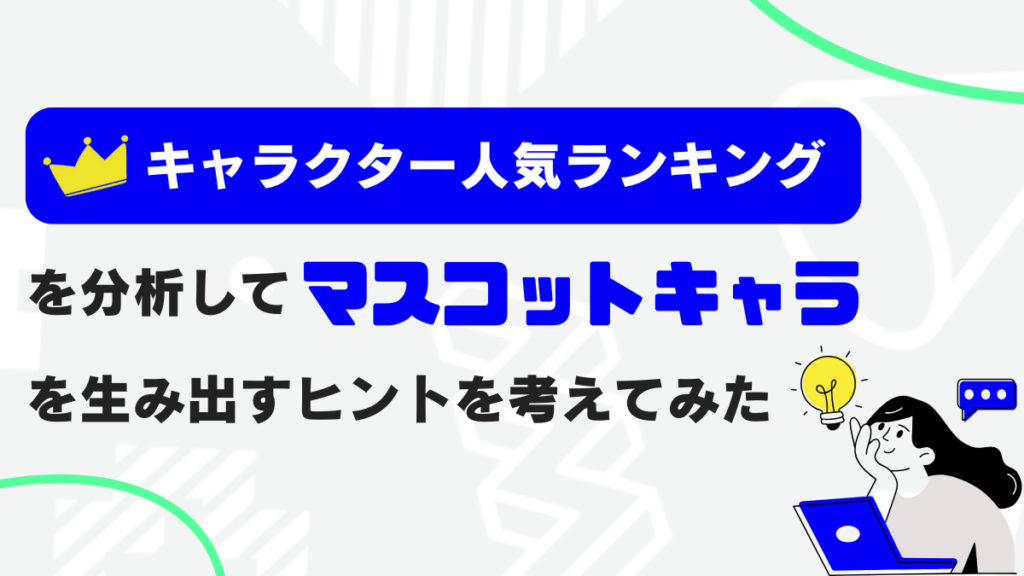
「せっかく作ったマスコットキャラクターが、社内資料のアイコンで終わってしまった...」
これは、ある中堅企業の広報担当者の言葉です。プロジェクトとして立ち上げ、デザイナーにもこだわり、社内では「かわいいね」と評判だったマスコット。でも、外に向けた“推し活”やファンとの接点は生まれず、いつの間にか存在感が薄れていったと言います。
当時の私は、「やはり知名度がないと難しいのかもしれない」と思っていました。
しかし、ちいかわがSNSから爆発的に人気を広げていく様子を見て、「ゼロからでも、推されるキャラクターはつくれるのではないか」と考えが大きく変わったのです。
そこから私は、ポケモンやハローキティ、くまモン、キウイブラザーズなど、国内外で推されてきたキャラクターたちを調べ直しました。売上ランキングや人気投票の結果だけでなく、その背後にある“仕掛け”や“感情の流れ”まで細かく見ていく中で、ある共通点が浮かび上がってきました。
それは、「可愛い」や「有名」といった要素よりも、“語りたくなる背景”や“誰かと共有したくなる関係性”が、最初から設計されていることです。
SNSで発信される日常、応援できる仕組み、共感できる“弱さ”など、人気キャラには、推されるべくして推される“構造”が備わっていたのです。
もし、私たちがこれからマスコットキャラクターをつくるとしたら?
目指すべきは、「売れるキャラ」でも「認知される存在」でもなく、“誰かの心の中に棲みつく存在”を最初から設計することではないでしょうか。
そこで今回は、キャラクターの売上・投票人気・SNSでの拡がり方などから、「推されるキャラクターの共通点」を徹底的に整理しました。
人気キャラクター投票というと「名前を知られているキャラが上位に来るだけ」と思うかもしれません。ですが、実際に上位に入るキャラは、“応援したい理由”を持つ存在ばかりです。
例えば、サンリオキャラクター大賞では、シナモロールやポムポムプリンのように、やさしさや寂しがりやな「放っておけない」一面を持ったキャラが支持されています。これらのキャラには、「この子を応援したい」「そばにいてほしい」と感じさせる“感情のスイッチ”があるのです。
さらに、この投票には「グッズを買うと投票できる」という仕組みや、キャラクターからXのリプライが届くなどの巻き込む仕掛けもあります。
つまり、ファンは“気持ち”だけでなく“行動”でも推しを支えており、票数はその熱量の大きさを示しています。
ファンはなぜ「このキャラに投票しよう」と決めるのでしょうか?それは、キャラの中に「自分に似た部分」や「こうありたい姿」を見つけているからです。
例えば、クロミは見た目はクールですが、努力家で不器用な一面があります。こうした“ギャップ”や“共感できる弱さ”が、ファンの感情を強く揺さぶります。
共感で人気を得た「ちいかわ」や「ぼっちちゃん」もまた、「うまくいかなくても毎日がんばっている」という姿が多くの人の心に響いています。
このように、投票で人気になるキャラは、単に「かわいい」だけでなく、“語りたくなる背景”と“自分と重ねられる物語”を持っているのです。
どれだけ好きなキャラですが、応援する“機会”がなければ気持ちは続きません。逆に、応援できる「場」があると、ファンの気持ちはどんどん育ちます。
サンリオのように、年に1度の投票イベントがあると、ファンはそこに向けて気持ちを高め、グッズを買ったりSNSで発信したりします。
そして、結果が発表されると「応援してよかった」という感動体験が残り、さらにそのキャラを好きになるのです。
こうした「参加できる」「貢献できる」仕組みがあるキャラほど、ファンとの関係が深くなり、推し続けられる存在になります。
経済効果を生むキャラクターは、単体というよりもストーリー作品やさまざまなキャラクターたちの集団によって実現されるケースが多くなります。
こうした「売れるように作られている」という設計の力が大きく関わっているのです。
例えば、2024年時点で世界で最も収益を出しているキャラは、「ポケモン(約921億ドル)」と「ハローキティ(約800億ドル)」です。
どちらも、ゲーム・アニメ・映画・グッズ・コラボなど、いくつもの入り口(接点)を持っています。しかも、ポケモンには1000種類以上のモンスターがいて、誰でも「自分の推し」が見つかります。
ハローキティも、仲間キャラが多数いて、コラボを繰り返して認知度を保ちながら、ライセンス収入やグッズの販売が広がっています。
つまり、多様性があることで共感の“幅”が広がり、導線があることで感情が“行動”に変わるのです。
売れるキャラの中ですが、何十年も愛される存在には、特別な共通点があります。それは「子どもと一緒に育てることができる」という設計です。
例えば、「アンパンマン」や「ドラえもん」は、親と子が一緒に見たり、グッズを買ったりすることで、“家族の記憶”に残るキャラになっています。
アンパンマンは、ただ正義の味方ではなく、「困っている人に顔をちぎってあげる」ような自己犠牲の優しさを持っています。
ドラえもんは、失敗してばかりののび太くんをいつも見守りながら、少しずつ成長していく姿を描いています。
こうしたストーリーが、子どもだけでなく親にも届き、世代を超えて「一緒に育つキャラ」として残っていきます。
つまり、そのキャラと一緒に感情を共有した思い出こそが、リピートされ続ける理由なのです。
人気キャラの多くが売れているのは、「かわいいから」「話題だから」だけではありません。
本当に売れるキャラには、「この子を応援したい」という気持ちが、自然と“お金や行動”につながるような仕掛けが存在します。
例えば、ちいかわは「白くて丸いからかわいい」という単純な話ではなく、さまざまな接点とストーリーテリングの組み合わせでグッズを買いたくなるように仕掛けられています。
また、ポケモンは「ゲームで遊ぶ→好きなキャラができる→アニメで観る→グッズを集める→SNSで語る」というように、感情から行動へと移る階段がたくさん用意されています。
このように、推したくなる気持ちを“止めずに流す導線”を用意していることが、売れるキャラには共通しているのです。
関連記事:「ちいかわ」のキャラクターグッズが爆売れする理由は「可愛い」だけじゃなかった?
人がキャラクターを“推す”とき、それはただ一方的に見るだけの存在に対してではありません。「自分も頑張ろう、こっちを見てくれている」といった原動力となるかどうかが、推す行動につながるのです。
SNSでキャラが定期的につぶやいたり、ファンの声に反応する…または、季節やイベントに合わせて変化するなどです。こうした「リアクションのあるキャラ」は、まるで“生きている”かのように感じられます。
例えば、初音ミクは喋らないキャラでありながら、楽曲・衣装・ライブ・イラスト・ゲームなど、ファンの創作に応える「場」と「変化の余地」が無限にある存在です。
この双方向のコミュニケーションがあるだけで、ファンとの関係は「静的」から「動的」に変わります。この視点で見ると、初音ミクは極めて優れた事例です。
結果として、「こっちの想いが届く」「一緒に作品を作っている」という感覚を生み出しています。
関連記事:キャラクターを使ったSNS運用のメリットとは?成功例やコツを紹介
ファンがキャラクターに惹かれる理由の1つに、「このキャラに感情を預けられるから」というものがあります。
つまり、キャラは“見られる存在”であると同時に、“感情を預ける器”でもあるのです。
例えば、怒りを共有してくれるキャラ、不安なときに寄り添ってくれるキャラ、疲れているときに癒してくれるキャラ…このように、ファンは「自分の状態」に応じて、キャラとの関係を選んでいます。
ちいかわが疲れている人に人気なのは、「うまく言えないけど、不安やプレッシャーを感じながら毎日がんばる姿」が自分の気持ちと重なるからです。
初音ミクも、「自分では言葉にできない感情を、歌にして代弁してくれる存在」として、多くの人に愛されています。
つまり、「この気持ちをわかってくれる」と思える理解者のような存在なのです。
完成されすぎたキャラは、憧れにはなっても「育てたい」「支えたい」と思わせる存在にはなりません。一方で、どこか未完成だったり、不安定だったりするキャラには、「一緒に育っていきたい」という気持ちが生まれます。
例えば、ちいかわは強くありません。よく泣き、がんばっても報われないことが多くあります。だからこそ、「自分と似ている」「支えてあげたい」と感じる人が多いのです。
初音ミクも、明確な人格やストーリーを持たない“余白のある存在”です。
そのため、ファン一人ひとりが自由に「理想のミク像」を描き、「自分だけのミク」を応援することができます。この“自己投影の余白”こそが、深い愛着や参加意識を育てているのです。
つまり、推されるキャラとは、「まだ完成していない」からこそ、一緒にいたくなる存在なのです。
関連記事:【IP展開事例】“ただの歌声合成ソフト”だった初音ミクが今も人気の理由は共創にあった?
キャラクターにとって、「可愛い」「わかりやすい」という見た目はたしかに大事ですが、それは“最初に知ってもらうための条件”でしかありません。
例えば、くまモンやキウイブラザーズのように、色が少なく、輪郭が丸くて、すぐに覚えられるキャラは印象に残りやすいため、この条件を採用する企業は多く存在します。「記号のように覚えてもらえる」ことは、キャラ育成においてとても有利です。
ただし、それだけでは、ファンが“応援したい”とまでは思いません。見た目がよくても「それ以上、知りたいと思えないキャラ」は、いつの間にか忘れられてしまいます。
つまり、見た目はスタート地点。そこからどんな感情を生むかが、推されるかどうかを決めるのです。
関連記事:【初心者向け】魅力的なキャラクターデザインで大切な要素とは?企画手順も紹介
キャラが「長く応援される存在」になるには、そのキャラが“なぜそこにいるのか”が必要です。見た目だけでなく、「どんな役割を持っているか」「どんな意味を伝えているか」があるキャラは、人の心に残ります。
例えば、前述で触れたキウイブラザーズは「キウイをもっと知ってほしい」という目的から生まれました。兄弟で性格がそれぞれ異なる兄弟のやり取りも、見ていて楽しく感情移入がしやすい状況を作っています。
ゼスプリ公式YouTubeチャンネルでは、誕生の背景などもキャラクター自身に語らせています。
このように、キャラの“存在理由”がわかると、ただの飾りではなく「一緒に目的を応援する相棒」に見えてきます。だからこそ、ファンは行動したくなるのです。
参考:スター街道ばく進中!「キウイブラザーズ」の制作チームに聞いた舞台裏 - Walkerplus
人気キャラの多くは、“そばにいてくれる”ような存在として日常の一部になっています。それは、「関係性を作る工夫」があるからです。ぬいぐるみや雑貨を持ち歩く人も多く、「一緒にお出かけしているような感覚」が、日常の中に生まれています。
例えば、グッズ展開以外にもSNSでキャラクター自身の投稿が更新され、見る人は「今日はどうなってるかな?」と見に来てもらえる状態を作っているなどです。
こうして、キャラは「見るもの」から「一緒に過ごす仲間」へと変わっていきます。そして、ファンは“そばにいてくれる”ことで愛着が増し、もっと応援したくなるのです。
つまり、推されるキャラには、ファンが「関われる余地」があり、それが“推し活”のきっかけになります。
関連記事:「ちいかわ」のキャラクターグッズが爆売れする理由は「可愛い」だけじゃなかった?
ここまでのポイントをまとめます。
推されるマスコットキャラクターには、単なる“可愛さ”以上の工夫が必要です。投票人気や収益ランキングで上位に来るキャラクターには、「応援したくなる背景」「一緒に過ごしたい関係性」「感情を預けたくなる余白」といった設計が存在していました。
これらは偶然ではなく、意図された“心理設計”です。私たちがゼロからマスコットをつくる際にも、ただ見た目を整えるのではなく、「心の中に棲みつく構造」をつくることが、ファンに長く愛されるためのカギになるのではないでしょうか。
ぜひキャラクター作りのヒントをまとめた資料も以下のダウンロード資料ページから入手して、自社マスコットキャラの開発にご活用ください。

キャラクターを活用したPR、ブランドのイベント企画といったPR活動は、動画制作だけでなく数々のイベントの認知拡大を支援してきた我々NOKID(ノーキッド)なら、幅広いご提案とクリエイティブ制作が可能です。

アニメーションという表現方法の中にも、スライドに動きをつけたものから3DCGを活用したもの、セル画など多岐に渡るテイストがあります。
動画を制作する場合には、要望通りに動画を制作することだけでは効果を発揮しないことが多くあります。NOKIDでは、動画の活用目的に沿った構成や表現を計画しております。
例えば、TikTokであれば認知に適したアルゴリズムになっておりユーザーが次々と動画をスワイプして観ていきます。そのため、冒頭の2〜3秒で注意を引くためのアイデア、PRに繋げるためにどのような情報を発信すべきかといった"ビジネス視点とクリエイティブ視点"のバランスを意識しております。
「初めてのアニメーション制作」「PRまで考慮した映像」をご検討の方はお気軽にご相談ください。
・キャラクターをマーケティングで活用するには?アニメコラボCMの事例や戦略を紹介
・キャラクターを活用するメリットとは?デメリットや効果も解説
・【顧客拡大】キャラクター活用のリブランディング戦略とは?失敗例も紹介
・【キャラ活用】IPビジネスがアニメ事業のチャンスに!自社IPの可能性とは?
・海外でアニメを展開するやり方は?失敗原因・リスクを事例にもとづいて解説
・【企業向け】VTuberの始め方は?新規プロジェクトを成功させるポイントを紹介
・キャラクターを用いたコラボ戦略と活用事例から成功の秘訣を探る
・ブランドのファンを増やすオリジナルグッズ・ノベルティとは?具体的な効果や制作方法を紹介
・にじさんじのコラボ商品は何がある?他社事例を分析してまとめてみた
・なぜ企業同士のコラボ事業が注目されるのか?参考事例までPR会社が解説
・【IPコラボ商品・キャンペーン】参考になる事例から学ぶ!成功させるポイントを紹介
・【IPコラボ】学習教材×マンガが売れた秘密とは?活用事例・ポイントも紹介
・キャラクターライセンスとは?他社IPを活用してブランド価値を高める方法を紹介

NOKID編集部
1000件以上の映像制作実績を誇る株式会社NOKIDの編集部メンバーが監修。キャラクター・アニメーション分野のノウハウやトレンドの活用手法の紹介が得意です。